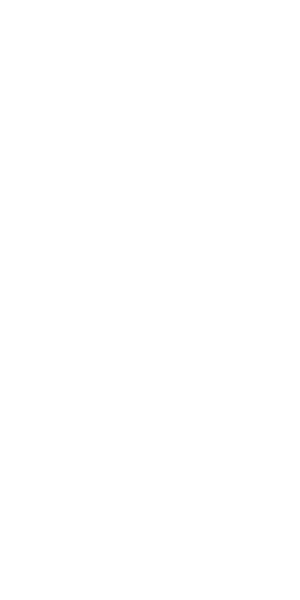2020年6月現在、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、多くの企業が経済的ダメージを受けています。事業の縮小や希望退職を募るなど、さまざまな対策が考えられますが、従業員の雇用を守りながら会社の存続を考えた場合、従業員の給料を減らす「減給」をせざる負えないケースもでてくるかと思います。
ただし「減給」は当然ながら簡単に行えるものではありません。この記事では、ポライト社会保険労務士法人の榊 裕葵様に、給与の減額方法から、減給の限度額までわかりやすく解説して頂きます。
▶︎ 給与計算ソフトならシェアNo.1のfreee人事労務!
目次
従業員の給与を減額する方法とは?
減給に関する規則
従業員は会社と雇用契約を結び、雇用契約で定められた条件に基づいて就労をしています。給与額についても、もちろん雇用契約で定められた条件の1つです。
雇用契約は、会社と従業員の双方の合意による法的な約束事なので、たとえ経営が厳しくなっても、会社の判断で、一方的に従業員の給与を減額することはできないというのが大原則です。
減給が可能となる5つの場合
ただし、その大原則のもと、例外的に従業員の給与の減給が許される場合もあります。代表的なケースとして、次の5つの場合が挙げられます。
1つ目は、会社と従業員の間で合意が成立した場合です。
労働契約法第8条には、次のように定められています。
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
雇用契約は、会社と従業員の間の約束事ですから、お互いに納得の上、契約内容を変更すれば、それが新たば雇用契約の内容になります。すなわち、給与を減額した雇用契約書が労使の間で再締結されれば、給与の減額は可能ということです。
2つ目は、就業規則の変更による間接的な減給です。
労働契約法第9条には、次のように定められています。
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
この条文でいう「就業規則」には、賃金規程も含まれます。たとえば、基本給のテーブルを一律引き下げるとか、これまで存在していた手当を廃止するといった形で、間接的に減給をすることは許されないというのがこの条文の趣旨です。
しかし、条文の冒頭部には「労働者と合意することなく」という表現がありますので、従業員1人1人と合意をすれば、合意が成立した従業員に関しては、就業規則の変更による間接的な給与引き下げも許されます。
そして、条文の末尾の「ただし、次条の場合は、この限りでない。」という表現に関してですが、「次条(労働契約法第10条)」の条文は次の通りです。
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。(以下略)
すなわち、就業規則の変更に対する同意を得られなかった従業員についても、会社の倒産の危機を回避するためなど、やむを得ない状況であって、従業員に生ずる不利益も社会通念上容認できるものであり、かつ、会社が従業員に説明を尽くしたというような場合は、就業規則の変更によって間接的に給与を引き下げることが、従業員本人の同意無しに可能になるということです。
3つ目は、業績給・調整給による減給です。
基本給の一部を「業績給」や「調整給」という名目で支給したり、あるいは、同様の趣旨を持つ手当として支払うことで、経営環境が悪化した場合には、「業績給」や「調整給」を減額することで、柔軟に減給をできる仕組みを給与体系に組み込んでいる会社も存在します。
雇用契約書や就業規則で、あらかじめ「業績給」や「調整給」を定めておけば、会社の業績が悪化した場合に「業績給」や「調整給」が減額されるということは、当初の雇用契約に定められた「想定の範囲内」ということで、減給は合法となります。
4つ目は、人事評価の結果による減給です。
人事評価が一定基準に満たない場合に減給(マイナス昇給)になることが定められている人事評価規程を持つ会社は、人事評価規程に定められた内容に沿って行われた評価結果に基づいて減給を行うことが可能です。
雇用契約を結ぶ時に、昇給に関する事項については会社に説明義務がありますので、人事評価が一定水準に満たない場合には減給になるということも雇用契約の条件の一部になっており、「想定の範囲内」と、捉えられ合法になります。
5つ目は、懲戒処分による減給です。
就業規則に定められた懲戒事由に該当した場合には、懲戒処分としての減給が可能です。基本給や諸手当の額自体は変えずに「減給10分の1、3か月」のような形で一時的に減給を行うパターンと、役職を解いたり降格させたりして、基本給自体を減額したり、下位の職位になったため役職手当等を減額または不支給とするような永続的な減給のパターンがあります。
減給にあたっての注意点
減給のプロセス
上記の1~5に該当した場合でも、無条件に減給を行って良いわけではありません。各場合において、減給を行うプロセスにおける具体的な注意点を説明したいと思います。
まず、1つ目および2つ目の場合ですが、雇用契約や就業規則の変更に会社が従業員の同意を求めるにあたっては、各従業員の真意に基づいた同意を得ることが必要です。会社が圧力をかけて同意をさせたような形になってしまわないよう気を付けてください。
会社が精神的にプレッシャーをかけたり、嘘を述べたりして、従業員の意に反し、不適切な形で減給に合意させた場合は、民法上の「脅迫」や「詐欺」、あるいは「錯誤」に該当する恐れがあります。そうなった場合、減給に対する従業員の同意は、法的に取消対象、あるいは無効となります。
以上の事から、減給を行う場合は従業員に対して、会社の置かれている状況を誠心誠意説明し、業績が回復した際には従業員へも充分な還元を行うことを示して、従業員側の納得を得られる形で同意を得るように努めてください。
2つ目の場合の、就業規則の変更に従業員の同意が得られないパターンにおいても、同意なしの就業規則の変更の有効性をめぐり裁判になった際には、「会社側がどれだけ丁寧に説明をしたのか」また、「充分な代替措置や経過措置を提案したのか」など、同意を得られなかった状況に至るまでのプロセスも重視されます。よって、結果的に同意を得られなかった場合においても、誠心誠意の説明は重要であるということです。
3つ目の場合の「業績給」や「調整給」を減額するにあたっては、もともと業績が悪化した場合に減額することを想定した給与体系なので、法的には、会社の裁量によって減給は幅広く認められます。減額にあたっての法的な意味でのリスクは相対的に小さいと言えるでしょう。
だからといって安易に減給を行うと、従業員に不安や不信を与え、退職者の増加や、従業員満足度の低下につながります。なので、法的に可能であったとしても、実務上は慎重に対応したいものです。
4つ目の人事権の行使による減給は、①合法的な評価基準に基いていること、②評価が恣意的でないこと、③どのような評価になるとどれくらい給与が下がるのかの評価と減給幅の関係が明確であること、の3つが主な注意点になります。
①については、性別や国籍などで差別をしたり、育児休業や介護休業などの取得者を不利に扱ったりするような、法令に違反する評価基準は違法です。②については、評価者が好き嫌いで評価の甘辛に手心を加えたり、給与を引き下げることを前提で低い評価を付けるようなことがあってはならないということです。③については、「全然ダメだから、今回は2割減給ね」というような、行き当たりばったりの減給ではなく、「C評価だったので、基本給が2ランク下がって〇円になります」というような、評価と減給の客観的なリンクが必要であるということです。
上記①②③を満たさない減給は、法的に無効となる可能性が高く、従業員が裁判に訴えた場合、会社が敗訴して、従前の給与額と、減給後の給与額の差額を、損害賠償として追加支給しなければならないリスクが生じます。
5つ目の懲戒処分による減給は、就業規則等の社内規程に定められた手順を守って行うことが重要です。就業規則で定められた減給の対象となる懲戒事由に該当していることはもちろんのこと、本人に弁明の機会を与えたり、懲戒処分を行う場合には懲戒委員会を開催することが定められている場合には当該委員会に諮問するなど、懲戒処分を行うまでのプロセスに不備があってはなりません。
また、就業規則に定めれば何でも減給処分にして良いというわけではなく、非違行為の重さが減給に値するものでなければなりません。たとえば、身だしなみやあいさつなど、軽微な就業規則違反は、まずは始末書にとどめ、繰り返されるようであれば、より重い処分として減給を行うほうが妥当です。
適切なプロセスを踏まなかったり、非違行為に対して処分が重すぎる場合、懲戒処分による減給は無効となります。
減給の限度額
次に、減給額はどこまでが許されるのか、ということについて説明します。
この点に関しては法的な定めはほとんどありません。
明確な基準が置かれているのは、懲戒処分による減給は、1日の賃金の半額、1か月の賃金の10分の1までが上限であるということくらいです。
1つ目や2つ目の場合の、従業員との合意による減給の場合は、合意さえ成立すれば減給幅に上限はありません。しかし、あまりにも減給幅が大きいと従業員は同意をしない可能性があるので、現実的には10%程度を目安とし、大きくても20%くらいが限度ではないかというのが筆者の実務感覚です。
また、同じ10%の減給であっても、基本給が20万円の人の10%と、基本給が100万円の人の10%では、生活に与えるインパクトが全く異なります。パーセンテージで減給を考える場合には、基本給が低い新入社員や若手社員ほど、慎重に対応しなければなりません。まずは経営者や幹部社員の給与から減額し、一般社員の給与に手を付けるのは最後の最後とすべきでしょう。
3つ目の場合の「業績給」や「調整給」を減額するにおいては、業績給や調整給の額そのものが減給の上限となります。しかし、賃金規程の定めにもよりますが、業績給や調整給の全額を減額する必要はありませんので、会社の置かれている財務状況を踏まえ、最小幅の減額とすることが望ましいでしょう。
4つ目の場合の人事評価による減給の場合は、人事評価制度や給与体系を設計するのは会社の考え方次第なので、評価に応じてどのような減給幅にするかは、原則として会社の自由です。ただし、従業員の生活を考えると、やはり1回の評価において減給される幅は10%~20%程度とするのが妥当な線ではないでしょうか。
5つ目の場合の懲戒処分による減給の場合は、前述した通り「1日の賃金の半額、1か月の賃金の10分の1」が上限です。ただし、この上限が適用されるのは一時的な減給のパターンの場合のみで、懲戒処分による降格等の結果として給与が減額になるパターンの場合には上限の適用はありません。
給与を減額した後に必要な手続き
続いて、給与を減額した際に行うべき手続をご説明します。
まずは、社内で行うべき手続です。
1つ目の雇用契約の見直しによる減給を行う場合は、合意した事実を証拠として残すため、雇用契約書の再締結が必要です。
2つ目のの就業規則の変更による間接的な減給の場合も、就業規則の変更に対する同意書を、変更に同意があった従業員1人1人から個別に回収することを目指します。全員の同意が得られなかったとしても、1人でも多くの同意書を集めることがポイントとなります。
3つ目の、業績給や調整給による減給の場合、あるいは4つ目の人事評価による減給の場合は、雇用契約書の再締結までは必要ありませんが、給与辞令を配布することが望ましいでしょう。
5つ目の懲戒処分による減給の場合は、懲戒辞令の中に、どのような形で減給になるのかを明記する必要があります。具体的には、「令和〇年〇月〇日支給分給与に対し、減給10%とする」とか、「令和〇年〇月〇日付で課長職を解任し、基本給を〇円に引き下げるとともに、以後、役職手当を支給しない」といったような記載が想定されます。
なお、懲戒辞令を社内に公開する場合には、対象者の給与額をマスキングして分からないようにするなど、プライバシーへの配慮も行うようにしてください。
次に、対外的に必要となる手続や届出です。
2つ目の就業規則の変更による間接的な減給の場合において、変更後の就業規則は、忘れずに所轄の労働基準監督署に提出をしましょう。なお、添付書類に関して、就業規則の不利益変更の場合であっても、従業員1人1人の同意書は添付不要で、通常の就業規則変更と同様、労働者代表の意見書だけを添えれば大丈夫です。
また、1つ目から5つ目、いずれのパターンによる減給であっても、社会保険の標準報酬で2等級以上の変動があった場合には、随時改定の対象となります。減給後の給与を3か月分支給した後、速やかに所轄の年金事務所へ提出を行うようにしてください。
労務トラブルにならない為に必要な事とは?
減給は、従業員にとって最も重要な労働条件である給与を不利益に変更するものですので、繰り返しになりますが、常に慎重な対応が必要となります。
従業員とのトラブルを避けるために、会社は具体的にどのような対応をとるべきでしょうか。そのポイントは3つあります。
1つ目のポイントは、丁寧な説明をして従業員の理解・納得を得ることです。
今回のような新型コロナウイルスの影響の結果としての減給であれば、会社の売上がどれくらい急減したのかということや、会社にキャッシュが現在どれくらい残っているのかということなどを具体的な数字で説明し、従業員と客観的に状況を共有することが、望ましいでしょう。従業員と危機意識を共有すれば、理解・納得も得られやすくなります。
2つ目のポイントは、まずは、経営者が率先して「身を削る」ことです。
従業員にだけ減給を求めて、経営者が役員報酬を満額もらうような形になってしまっては、気持ち的にも従業員は減給を受け入れることができません。
確かに、役員には「定期同額給与」というルールが税法上あり、原則として決算期の途中で役員報酬を変更することはできません(変更すると損金扱いにできなくなってしまう)。
ですが、新型コロナウイルスによる大幅売上減のように、経営状況に激変があった場合は、役員報酬の減額も税法上認められています。また、「自主返納」という形をとることも可能です。
役員報酬を減額するかどうかは経営判断事項なので、通常は、社労士が口出しをすべきことではありませんが、従業員との信頼関係という観点を踏まえると、従業員の給与を減額する前に、まずは役員報酬の減額が先にあるべきというのが筆者の考えです。
3つ目のポイントは、「書面」で減給の証拠を残す、ということです。
口約束だけで減給を行ってしまうと、後になって「私は減給に同意したつもりは無かった」とか、「減給自体に同意はしたが、減給額が私の認識とは違う」など、「言った言わない」のトラブルになってしまうリスクがあります。
このようなリスクを防ぐためには、書面で、しっかりと証拠を残しておくことが重要となります。具体的には、再締結した雇用契約書、就業規則不利益変更の同意書などですが、従業員の署名押印のある原本や、電子契約書で取り交わしたデータなどは、しっかりと会社側で保管をしておいてください。
まとめ
本稿では、減給を行うことができる場合と、注意点について解説をさせて頂きました。
減給は従業員の生活に大きな影響を与えますので、できれば回避をしたいものです。しかし、新型コロナウイルスの影響が長期化し、やむを得ず減給を行わなければならない会社も少なくはないというのが現状です。
減給を行う際には、本稿で紹介させていただいたよう、法的な注意点を守ることと、従業員の気持ちに配慮すること、その両面からの慎重アプローチが大切です。
減給を含めた緊急対応により、1社でも多くの会社が新型コロナウイルスの大波を乗り切り、状況が落ち着いた後には、再び成長・発展していくことを願ってやみません。

執筆: 榊 裕葵(社会保険労務士)
こんにちは。ポライト社会保険労務士法人マネージング・パートナーの榊です。当社は人事労務freeeをはじめ、HRテクノロジーの導入支援・運用支援に強みを持っています。ITやクラウドを活用した業務効率化や、働き方改革法対応は当社にお任せください。