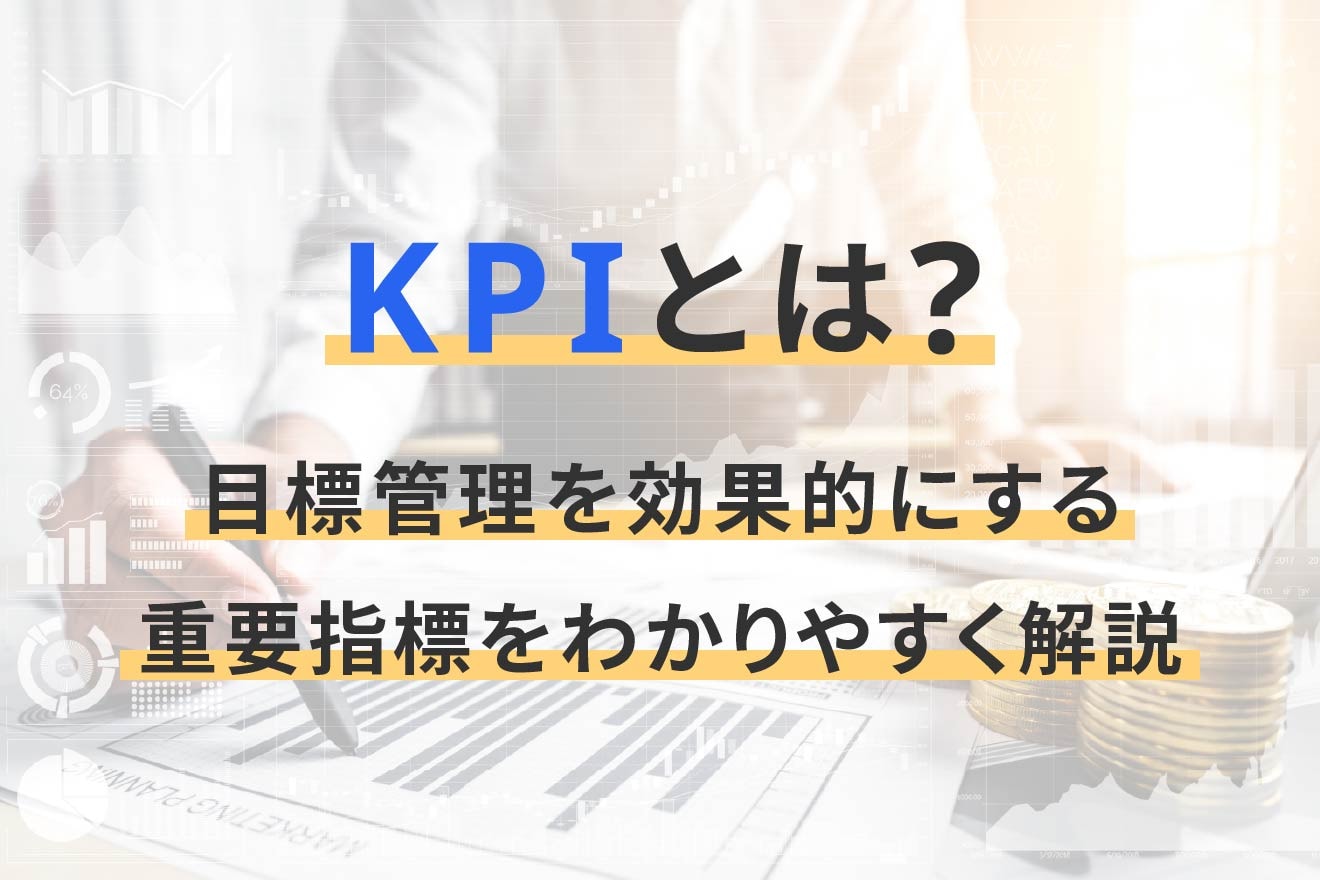
「KPI」とは、ビジネスの進捗管理や成果を測定するために用いられる「重要業績評価指標」のことです。最終的なゴールに至る過程の中間に設定される目標を指します。
KPIを正しく設定・運用すればチームや個人のやるべきことや判断が明確になり、組織全体の生産性向上につながります。
本記事では、KPIの基本概念からその設定方法や日常業務での活用法についてわかりやすく解説します。営業やマーケティングなどの現場でKPIを効果的に活用できるようになるため、ぜひ参考にしてください。
目次
- KPIとは
- KPIの具体例
- KPIと混同しやすい用語
- KGIとの違い
- KSF(CSF)との違い
- OKRとの違い
- KPIを設定する4つのメリット
- 社員一人ひとりが取るべき行動がクリアになる
- 会社全体のモチベーションの向上につながる
- 目標達成までのプロセスが可視化できる
- 評価基準が統一されわかりやすくなる
- 【職種別・部署別】KPI設定の具体例
- セールス(営業)
- マーケティング
- 人事・採用
- 経営・事業企画
- 開発
- カスタマーサポート
- KPI設定の流れを3ステップで解説
- STEP1:「KGI=最終目標」を設定する
- STEP2:「KSF=成功のために必要な要因」を特定する
- STEP3:「KPI=中間目標」を設定する
- KPIをうまく設定するためのポイントと注意点
- 「SMARTモデル」を活用する
- 「KPIツリー」でフローを可視化する
- 複雑に考えない
- KPI設定後のマネジメント方法
- PDCAサイクルを回す
- KPIは必要に応じて修正する
- まとめ
- 従業員エンゲージメントを高め、組織を活性化する福利厚生とは
- よくある質問
KPIとは
KPIとは「Key Performance Indicator」の略称で、日本語では「重要業績評価指標」と呼ばれます。企業やチームが掲げる最終目標に向けて達成度合いを計測するための、中間的な指標のことです。
たとえば、「年間売上1,000万円」という目標を立てたとします。この目標達成のために「年間受注数500件」が必要であれば、これがKPIとなります。
KPIは、ゴールへの進捗を測る物差しのような役割を果たします。「半年経過した時点で受注件数が200件なので、目標達成にはペースアップが必要だ」といったように、定期的に状況を確認し、軌道修正するための客観的な判断材料になります。
長期にわたる目標であればあるほど、ゴールまでの道のりにおいて現在地を正確に把握する作業が欠かせません。
KPIの具体例
KPIの種類は、職種や仕事のチーム次第で非常に多岐にわたります。その中でも、一般的によく用いられるKPIの種類を確認しておきましょう。
| 職種 | KPIの具体例 |
|---|---|
| 営業 | 売上・受注数・成約率・リピート率・アポイント獲得率・平均顧客単価・解約数 |
| 財務 | ROE(自己資本利益率)・ROA(総資産利益率)・固定資産回転率・当座比率・固定比率・負債比率 |
| マーケティング | 広告インプレッション数・広告クリック率・SNSエンゲージメント数・メール開封率 |
| 製造 | 生産量・稼働率・利用効率・事故発生件数・在庫回転率・廃棄率・不良率 |
| 人事 | 応募者数・採用者数・辞退者数・離職率・非正規雇用比率・女性管理職比率・社員満足度 |
KPIと混同しやすい用語
目標管理の場面では、KPIに似た用語として「KGI」や「OKR」などが使われることもあります。それぞれ明確に違いがあるので、正しく理解しておきましょう。
KPIと混同しやすい用語
- KGI
- KSF(CSF)
- OKR
それぞれの用語について以下で解説します。
KGIとの違い
KGIとは「Key Goal Indicator」の3つの頭文字を取った言葉で、「重要目標達成指標」と訳されます。端的にいえば「最終目標」を数値化した指標です。
KPIがビジネスにおける中間目標の達成度を示す「プロセス」の指標であるのに対し、KGIは最終的な目標に関する達成度を示す「ゴール」の指標である、という違いがあります。
たとえば、「年間売上1,000万円」というKGIに対して「年間受注数500件」「平均顧客単価2万円」といったKPIが設定されます。
KSF(CSF)との違い
KSFは「Key Success Factor」の略称で、「重要成功要因」と訳されます。また、「Critical Success Factor」の略称であるCSFも、KSFと同じような意味合いで用いられます。両者の言葉の使い方に違いはありません。
「業績を評価する」定量的な指標であるKPIに対し、KSF(CSF)は「なぜその業績になったのか」という定性的な要因を意味している、という点が異なります。
たとえば「年間受注数500件」というKPIに対し、その達成に必要な「相手の心を掴む顧客対応」「受注したくなる商品の品質」などがKSF(CSF)に該当するでしょう。
OKRとの違い
OKRとは「Objectives and Key Results」を略した言葉で、「目標と主要な成果」と訳されます。具体的には、「目標」と「その目標の達成に必要な複数の成果」を合わせて管理する手法を指します。
KPIが「ゴールまでの道のりの途中に設定された中間目標」であるのに対し、OKRは「ゴールはどこか」という目標と「どの道のりが適切か」という手法を示しているという点で違いがあります。
たとえば「年間受注数500件」というKPIに対して「固定客へのルート営業の割合を昨季比で20%増やす」「インターネットショップからの集客を2倍に伸ばす」など複数の手法を管理するのがOKRです。
KPIを設定する4つのメリット
ビジネスシーンでよくKPIが広く用いられるのは、企業にとって多くのメリットがあるからです。
KPIを設定する4つのメリット
- 社員一人ひとりが取るべき行動がクリアになる
- 会社全体のモチベーションの向上につながる
- 目標達成までのプロセスが可視化できる
- 評価基準が統一されわかりやすくなる
それぞれのメリットについて確認しておきましょう。
社員一人ひとりが取るべき行動がクリアになる
KPIを設定すると、社員一人ひとりが日々何をすべきかが具体的になります。「売上を伸ばす」という漠然とした目標よりも「今週中に新規顧客へ10件アポイントを取る」という目標のほうが、次に取るべきアクションは明確です。
具体的な行動指針があることで社員は迷わず業務に集中でき、管理職も進捗を追いやすくなります。結果として、組織全体の生産性向上が期待できるのです。
会社全体のモチベーションの向上につながる
社員が共通の目標に向かうための一体感を醸成しやすい点もKPIを設定するメリットです。
多くの企業では、KPIに対する各人の進捗状況がチーム内で共有されます。数値として自身の成果が認められることは、仕事への誇りややりがいにつながります。
また、同僚の頑張りに刺激され「自分も目標を達成しよう」と意欲が湧く場合もあるでしょう。KPIには組織の意思統一を行い、全体のモチベーションを高める効果があります。
目標達成までのプロセスが可視化できる
目標設定までの道のりを具体的に描き出せる点も、KPIがもたらす効果といえるでしょう。KPIを設定する過程で最終目標から逆算して必要なステップを洗い出すため、業務の全体像が明らかになります。
プロセスが可視化されると「どの業務を優先すべきか」「どこに課題が潜んでいるか」といった重要なポイントを発見しやすくなります。見つけた課題に対して具体的な改善策を講じるなど、より小回りの利いたマネジメントが可能です。
評価基準が統一されわかりやすくなる
KPIの導入は、公平で透明性の高い人事評価制度の構築にも役立ちます。「頑張り」などの主観的な要素だけでなく、客観的な数値を評価基準にできるからです。結果として、社員は自らの評価に対する納得感を得やすくなります。
KPIに基づいた評価によって、社員は自身の「会社への貢献度」を具体的に把握できるようになります。評価の明確化は社員の成長を促し、全体のパフォーマンス向上にもつながるでしょう。
【職種別・部署別】KPI設定の具体例
KPIはどの職種や部署、業務内容でも同じというわけではなく、それぞれに取り上げるべき指標は異なります。以下では、部門ごとのKPI設定例とそれぞれの指標における注意点を解説します。
セールス(営業)
営業部門では、売上や利益に直結する活動をKPIとして設定するのが一般的です。
| KPIの例 | 概要・注意点 |
|---|---|
| 新規契約数 | 新たに契約を獲得した件数です。事業の成長性を示す重要な指標といえます。件数だけを追うと、低単価の契約ばかりになったり既存顧客へのフォローが疎かになったりする恐れがあります。顧客単価やリピート率とセットで管理しましょう。 |
| 顧客単価 | 1顧客あたりの平均売上額です。顧客単価の向上は少ない労力で売上を伸ばすための鍵となります。無理なアップセルやクロスセルは顧客満足度の低下を招きます。顧客のニーズを的確に捉え、価値ある提案ができているかをあわせて評価しましょう。 |
| 商談化率 | アポイントや問い合わせの中から、具体的に商談に進んだ割合を示すKPIです。見込み顧客の質や、初期アプローチの有効性を測ります。商談化率が低い場合、営業担当のスキルだけでなく、アプローチしている市場やリストの質に問題がある可能性も考えられます。 |
マーケティング
マーケティング部門では、見込み顧客の獲得や育成に関する指標がKPIの中心になります。
| KPIの例 | 概要・注意点 |
|---|---|
| コンバージョン率(CVR) | Webサイト訪問者のうち、商品購入や資料請求などの成果に至った割合です。施策の効果を測るうえで中心的な指標となります。集客チャネル(広告、SNS、自然検索など)ごとにCVRを分析すると、より効果的な改善策を見つけやすくなります。 |
| リード獲得数 | 展示会やWebセミナー、Webサイト経由で獲得した見込み顧客の連絡先の件数です。獲得した数だけでなく「質」も無視できません。その後の商談化率や受注率が低い場合、ターゲット層とずれている可能性があります。 |
| 顧客獲得単価(CPA) | 一人の顧客を獲得するためにかかった広告宣伝費などのコストです。「コスト÷コンバージョン数」で算出します。CPAは、その顧客が生涯にもたらす利益(LTV)と比較して評価する必要があります。CPAがLTVを上回らないように管理するのが基本です。 |
人事・採用
人事・採用部門では、人材の獲得から定着、組織の活性化に関する多様なKPIが設定されます。
| KPIの例 | 概要・注意点 |
|---|---|
| 従業員定着率 | 一定期間において、従業員が離職せずに在籍し続けている割合です。働きがいや職場環境の満足度を示す指標となります。定着率が低い場合は離職理由を分析し、労働条件や人間関係、評価制度などの課題を特定して改善策を講じる必要があります。 |
| エンゲージメントスコア | 従業員の会社に対する貢献意欲や愛着を、アンケート結果を基に数値化したものです。総合スコアだけでなく「上司との関係」「成長機会」などの項目別スコアを分析し、具体的な改善アクションにつなげましょう。定期的に測定し、変化を追い続けることが大切です。 |
| 採用単価 | 採用手法の費用対効果を測る指標で、従業員一人の採用にかかった総コストを指します。採用単価を抑えることだけが目的ではありません。コストを抑えられたとしても、入社後の活躍度や定着率が低い場合は採用手法の見直しが必要です。 |
従業員定着率を向上させるためには、会社の福利厚生を充実させるのもおすすめです。毎日の生活に役立つ福利厚生で、従業員満足度を上げませんか?
「freee福利厚生」なら、多様なニーズに応える福利厚生を月々400円から提供できます。
経営・事業企画
経営層や事業企画部門では、会社全体の財務状況や事業の成長性を示す指標がKPIとなります。
| KPIの例 | 概要・注意点 |
|---|---|
| 売上高 | 事業の規模を示す最も基本的な指標です。市場におけるシェアや影響力を測るうえで重要になります。ただし、売上高だけで企業の収益性はわかりません。必ず営業利益率などの利益指標とセットで評価し、事業の健全性を判断しましょう。 |
| 営業利益率 | 売上高に占める営業利益の割合で、会社の「稼ぐ力」を示します。このKPIが高いほど収益性が高く、競争力があるビジネスと判断できます。利益率の改善を急ぐあまり、将来への投資(研究開発費など)を削りすぎると、長期的な成長を損なう恐れがあるので注意が必要です。 |
| 新規事業売上比率 | 総売上高のうち、新たに開始した事業の売上が占める割合です。企業の将来性やイノベーションの取り組み姿勢を示します。新規事業の場合、立ち上げ当初は赤字になるケースも少なくありません。短期的な収益性だけでなく、長期的な視点で成長性を評価しましょう。 |
開発
製品やサービスの開発部門では、生産性や品質に関する指標がKPIとして重視されます。
| KPIの例 | 概要・注意点 |
|---|---|
| リリースサイクル | 新機能のリリースや製品アップデートをどのくらいの頻度で実施できるかを示します。リリース頻度を上げることだけを追求しすぎると、品質が低下するリスクがあります。バグの発生率など、品質に関するKPIとバランスを取ることが大切です。 |
| バグ修正時間 | システム上の不具合(バグ)が報告されてから、修正が完了するまでにかかる平均時間です。品質管理体制の効率性を示します。すべてのバグを同じように扱うのではなく、事業への影響度や緊急度に応じて優先順位をつけ、効率的に対応する体制が求められます。 |
| コードカバレッジ | 作成したプログラムコードのうち、品質保証のためのテストが実施された割合です。テストの網羅性を示します。カバレッジ率が高いからといって、必ずしも品質が高いとは限りません。テストの内容そのものが重要であり、あくまで品質を測るひとつの目安と捉えましょう。 |
カスタマーサポート
カスタマーサポート部門では、顧客からの問い合わせに迅速かつ的確に対応できているかを測る指標がKPIになります。
| KPIの例 | 概要・注意点 |
|---|---|
| 顧客満足度 | サポート対応後に実施するアンケートで、顧客がどの程度満足したかを数値化する指標です。一時的な感情で評価が変動しやすい側面もあるため注意が必要です。顧客ロイヤリティを示すNPS(ネットプロモータースコア)など、他の指標と組み合わせて評価するとよいでしょう。 |
| 問題解決率 | 1回の問い合わせで顧客の問題が解決した割合です。サポート担当者のスキルやナレッジ共有の仕組みが反映されます。この数値が低い場合、担当者のスキル不足だけでなく、マニュアルが整備されていない、FAQがわかりにくいといった原因も考えられます。 |
| 平均応答時間 | 顧客からの問い合わせに対して、オペレーターが最初に応答するまでにかかる平均時間です。顧客を待たせない体制が整っているかを示します。応答時間の短縮だけを追うと回答の質が低下する恐れがあります。問題解決率や顧客満足度とセットで評価しましょう。 |
KPI設定の流れを3ステップで解説
KPIは思いつきで設定するものではありません。最終的なゴールから逆算し、論理的に導き出す必要があります。必ず最終目標(KGI)を先に設定してからKPIを検討しましょう。
KPI設定の流れ
- STEP1:「KGI=最終目標」を設定する
- STEP2:「KSF=成功のために必要な要因」を特定する
- STEP3:「KPI=中間目標」を設定する
それぞれのステップについて詳しく解説します。
STEP1:「KGI=最終目標」を設定する
まずは、最終目標となるKGIを設定します。会社やチームが何を目指すべきかを明確にし、決まったKGIは必ず関係者全員で共有しておきましょう。
KGIは抽象的な概念ではなく、ある程度具体性を持った数値(定量目標)の設定が推奨されています。たとえば、営業職においては「売上高」「営業利益」「成約率」などを指標とするケースが一般的です。
期間はKPIより長く、年単位(期単位)で設定するとよいでしょう。
STEP2:「KSF=成功のために必要な要因」を特定する
次に、KGIからKSF(成功のために必要な要因)を特定します。KSFを特定するにはKGI自体をよく見つめ、「何をしたら達成できるのか」というプロセスを熟考する必要があります。
KSFは数値目標ではなく、目標達成に必要な具体的アクションや方針を言語化するのがポイントです。たとえば「年間売上高10億円」というKGIに対し、「新規顧客の開拓」「既存顧客の単価アップ」「顧客満足度の向上」などがKSFとして考えられます。
STEP3:「KPI=中間目標」を設定する
KGIとKSFが決まったら、最後にそれぞれのKSFを具体的な数値目標であるKPIに落とし込みます。KSFで定めたアクションをどの程度実行すればKGIを達成できるかを考え、必要なKPIの数値にそれぞれ落とし込みましょう。
たとえば「新規顧客の開拓」というKSFに対しては「月間の新規商談数20件」「アポイント獲得率30%」のようなKPIが設定できます。
KPIは日々の行動に直結するような、具体的で現実的な数値目標にすることが重要です。期間はKGIより短く、内容に応じて週・月・四半期・半期などの単位で設定するとよいでしょう。
KPIをうまく設定するためのポイントと注意点
せっかくKPIを導入しても、何となく数値を決めてしまうとうまく機能しない可能性があります。KPIをより有効に活用するため、設定する際に大切なポイントを3つ紹介します。
KPIをうまく設定するためのポイントと注意点
- 「SMARTモデル」を活用する
- 「KPIツリー」でフローを可視化する
- 複雑に考えない
「SMARTモデル」を活用する
KPIを設定する際は、「SMARTモデル」を活用しましょう。SMARTモデルとは、以下の5単語の頭文字を取った思考法を表す枠組みのことです。
- Specific=明確な
- Measurable=測定可能な
- Achievable =達成可能な
- Related=関連性がある
- Time-bound=期限がある
たとえば、Webサイトの売上を伸ばしたい場合を例として考えてみましょう。「売上を増やす」という目標をSMARTモデルに当てはめて具体化すると、「3ヶ月以内に、オーガニック検索からのWebサイト売上を15%向上させる」といったKPIが設定できます。
このように、5つの要素を満たせば誰にとってもわかりやすく、行動につながるKPIが設定できます。
「KPIツリー」でフローを可視化する
KPIをスムーズに設定するには「KPIツリー」の活用も有効です。KPIツリーとは、KGI(最終目標)からKPI(中間目標)までをツリー状に図示したものです。目標達成までのプロセスが構造的に可視化されるため、KGIとKPIの論理的なつながりを一目で把握できます。
また、KPIツリーを作成する過程で、目標達成のために必要な要素の抜け漏れや指標同士の矛盾にも気づきやすくなります。KPIツリーでフローを可視化し、会社やチームの中で共有すれば、認識のズレを減らせるだけでなく、目標達成への道筋も明確に示せるでしょう。
複雑に考えない
KPIをうまく設定する秘訣は、指標をできるだけシンプルにする点にあります。
目標達成を焦るあまり、多くの要素をKPIとして設定してしまうという失敗は意外に少なくありません。しかし、KPIの数が多すぎると管理が煩雑になり、同じ目標を持つメンバーは何を優先すべきか混乱してしまいます。
また、KPIを達成する行為自体が目的化し、本来のゴールを見失う「目的と手段の入れ替わり」にも注意が必要です。KPIは可能な限りシンプルに考え、誰もが簡単に理解できる設計を心がけましょう。
KPI設定後のマネジメント方法
KPIは設定して終わりではありません。むしろ、設定後の運用と改善が目標達成の鍵を握っています。また、最初に立てたKPIが必ず最適であるとも限りません。市場環境の変化や、実際に運用する中で見えてくる課題もあるからです。
ここでは、KPI設定後に欠かせないマネジメント方法を紹介します。
PDCAサイクルを回す
KPIは、KGI・KSFとともにPDCAサイクルを回し、一定期間ごとに改善できるような仕組みにしておきましょう。特に、PDCAの中でも重要な「Check」と「Action」を意識して行うことが大切です。
たとえば月次のKPIを設定した場合、月末に進捗を確認(Check)します。その際に、ただ達成・未達成を判断するだけでなく「KPIは適切だったか」「もっと適した指標はないか」といった視点で振り返るのが重要です。
もしKPIが機能していないと判断すれば、指標の変更や修正(Action)を行います。新しいKPIの案が出た場合は、KGI・KSFとの兼ね合いを考慮しながら追加します。最初のKPIはあくまで仮説として考え、PDCAサイクルを回しながら最適化していくことが重要です。
KPIは必要に応じて修正する
PDCAサイクルとは別に、外部環境の変化に応じてKPIを修正する柔軟性も大切です。
たとえば競合他社が新商品を発売した場合、自社の「市場シェア」や「顧客流出率」といったKPIを注視し、必要であれば目標値を引き上げるなどの対策が必要になるかもしれません。
ビジネスを取り巻く環境は、常に変化します。設定したKPIに固執せず、状況に応じて臨機応変に見直すマネジメントを心がけましょう。
まとめ
KPIは、ビジネスの最終目標(KGI)を達成するための中間指標です。KPIを導入すると、社員が取るべき行動が明確になり、生産性の向上や公平な評価基準の確立につながります。
ただし、KPIは「一度設定して終わり」ではありません。PDCAサイクルを回しながら継続的に見直し、改善を繰り返すのがビジネス成功の鍵といえるでしょう。
これからKPIの導入を検討している場合は、本記事で紹介した設定の流れやポイントを参考に、まずはひとつのチームやプロジェクトから試してみてはいかがでしょうか。
従業員エンゲージメントを高め、組織を活性化する福利厚生とは
「優秀な人材の定着」「生産性の向上」といった組織課題の解決に向けて、新たな施策をお探しではありませんか
これらの課題解決の鍵として、今「福利厚生」のあり方が見直されています。
しかし、制度設計の手間やコストを考えると、すぐに行動に移すのは難しいと感じる方も少なくありません。そこで近年、選択肢として広がっているのが、アウトソーシング型の福利厚生サービスです。
月額400円から、最短即日で導入が可能
福利厚生サービス「freee福利厚生ベネフィットサービス」なら、 月額400円から、最短即日で導入が可能 です。制度設計や運用の手間もかからないため、専任の担当者がいなくてもすぐに始めることができます。
提供されるのは、全国10万店舗以上の優待や、カフェ・コンビニ・ネットショッピングなどで使えるデジタルギフト。誰もが日常的に使えるサービスなので、全従業員が公平にメリットを実感し、満足度の向上に直結します。
満足度向上と採用活動のアピールポイントに
採用活動でのアピールポイントとなり、エンゲージメント向上にも繋がる福利厚生。
気になった方は是非、 福利厚生サービス「freee福利厚生ベネフィットサービス」をお試しください。
よくある質問
KPIの定義とは?
KPIとは「Key Performance Indicator」の略称で、「重要業績評価指標」と訳されます。企業の最終目標(KGI)の達成度を測るための中間的な指標です。
詳しくは記事内の「KPIとは」をご覧ください。
KGIとKPIの違いは?
KGIとは「Key Goal Indicator」の略称で、「重要目標達成指標」と訳されます。KPIがそのゴールに至るまでのプロセスを測る中間指標であるのに対し、KGIはゴールを示す最終的な指標という点が異なります。KGIを達成するために、複数のKPIが設定されるのが一般的です。
詳しくは記事内の「KGIとの違い」をご覧ください。
KPIの欠点は?
KPIの欠点は、指標の数が多すぎると管理が複雑になり、本来の目的を見失ってしまいやすい点です。また、数値化しにくい定性的な要素(従業員の創造性や頑張りなど)は、KPIとして設定しにくい側面もあります。
詳しくは記事内の「複雑に考えない」をご覧ください。
どの職種や部署でも同じKPIを設定するもの?
KPIは、セールスやマーケティング、人事など、部署の役割によって設定する指標が異なります。
たとえば、セールスなら「新規契約数」、人事なら「従業員定着率」などが代表的なKPIです。それぞれの業務内容に即した指標を設定すれば、組織全体の目標達成がよりスムーズになります。
詳しくは記事内の「【職種別・部署別】KPI設定の具体例」をご覧ください。


