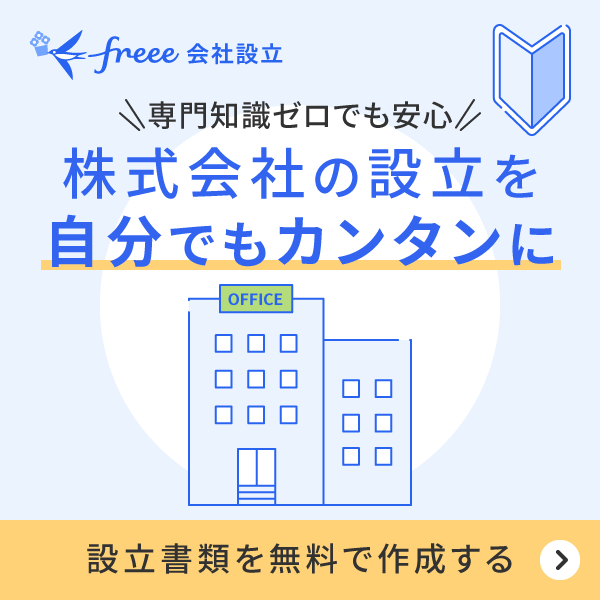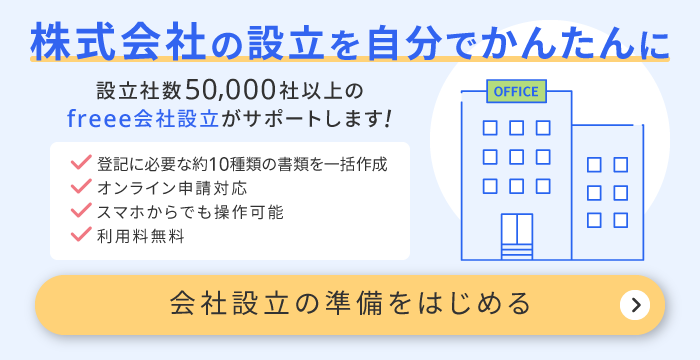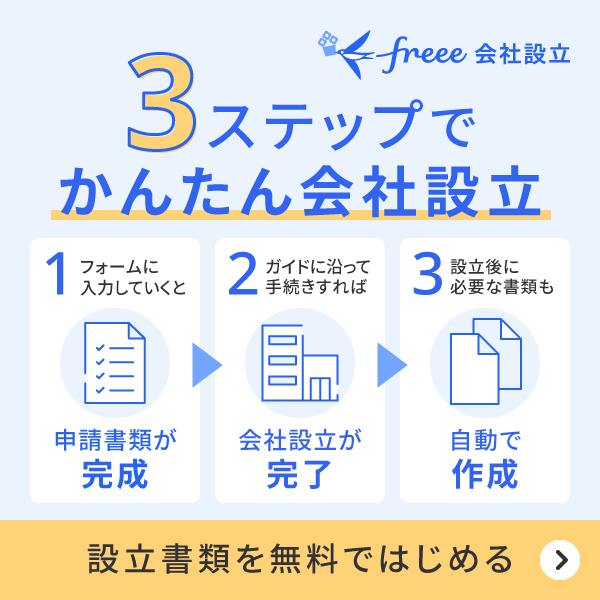監修 北田 悠策 公認会計士・税理士
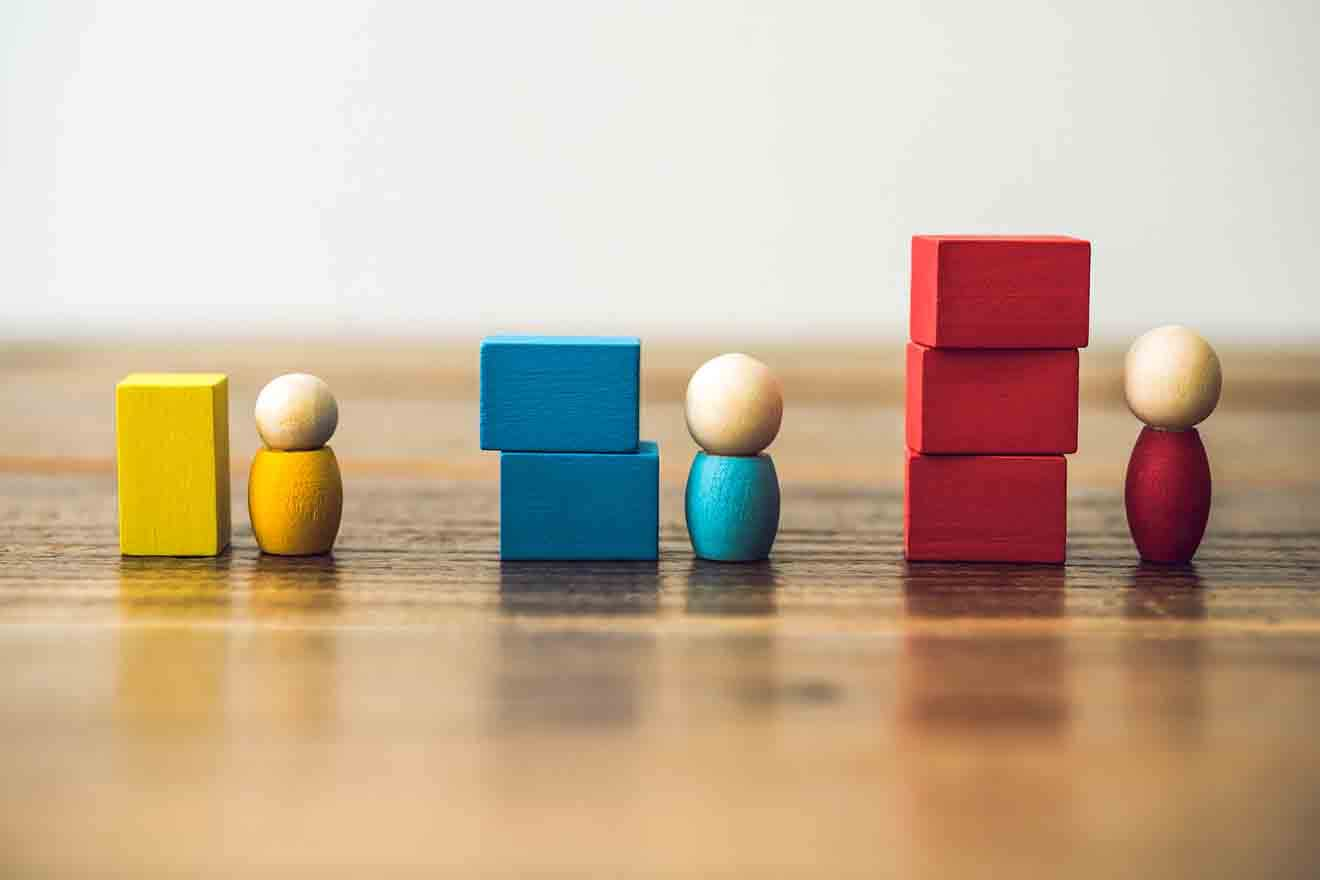
持ち株比率とは、会社の発行済み株式数に対して、任意の株主が保有する株式数の割合のことです。持ち株比率が高くなるほど議決権など行使できる権利が大きくなり、経営への影響力が強くなります。
創業者や代表者の持ち株比率が低ければ、自分の会社であるにも関わらず自分で経営のかじ取りができない可能性もあります。そうならないために、創業者以外の株主の持ち株比率が想定以上に高くならないよう、常に管理が必要です。
本記事では、持ち株比率の概要や計算方法のほか、持ち株比率に応じた権利や創業者が維持すべき持ち株比率の目安まで解説します。持ち株比率が低い場合の対処法も紹介するので、会社経営の参考にしてください。
目次
持ち株比率とは
持ち株比率とは、発行済み株式数に対して特定の株主が所有する株式数の割合です。割合が高いほど行使できる権利が大きくなり、会社経営への影響力が高くなります。
株式会社は、1株だけの所有で行使できる権利もあれば、一定数株を所有していなければ行使できない権利もあります。
持ち株比率の計算方法
持ち株比率は以下の計算式で計算されます。
持ち株比率(%)= (保有株式数 ÷ 発行済み株式数)× 100
上記の式の「保有株式数」は、任意の株主が保有する株式数です。「発行済み株式数」には、企業が発行したすべての株式数が含まれます。ただし、自己株式は含みません。
たとえば、ある企業の発行済み株式数が1万株あり、株主Aが1,200株を保有している場合、Aの持ち株比率は以下です。
Aの持ち株比率 = (1,200 ÷ 10,000)× 100 = 12.0 %
議決権比率との違い
議決権比率とは、行使できる議決権の合計数に対する保有議決権の数をあらわした比率のことです。持ち株比率と議決権比率の違いは、計算の対象とする株式の種類です。
株式には議決権のある株(普通株)と議決権のない株(無議決権株)があります。たとえば、株主総会での議決権がない代わりに配当が通常の株より高い配当優先株式は、無議決権株です。
持ち株比率では議決権の有無を区別しませんが、議決権比率では議決権の合計数に対する保有議決権の数で計算します。
議決権比率は以下の式で計算されます。
議決権比率(%)= (保有する議決権の数 ÷ 行使できる議決権の合計数)× 100
たとえば、ある企業の発行済み株式数が1万株あり、そのうち7,000株が普通株だとします。株主Aがこの企業の普通株を1,000株、無議決権株を200株保有している場合で計算しましょう。
Aの持ち株比率 = (1,200 ÷ 10,000) × 100 = 12.0 %
Aの議決権比率 = (1,000 ÷ 7,000) × 100 = 約14.3 %
このように、無議決権株が発行されている場合は、持ち株比率と議決権比率に違いが出ることがあります。持ち株比率が高い株主であっても、大半が無議決権株であれば経営への影響力は小さくなります。
持分比率との違い
持ち株比率と持分比率の違いは、間接的な資本の保有を含むかどうかです。
持ち株比率はその会社の株式の保有数で計算しますが、持分比率では直接または間接的に保有する資本の持分を計算します。また、持ち株比率の母数は発行済み株式数ですが、持ち分比率の母数は議決権を有する普通株です。
持分比率は以下の式で計算されます。
持分比率(%) = (保有株式数 ÷ 行使できる議決権の合計数) × 100
持分比率は、グループ会社がある際に連結決算の計算で用いられます。
出資比率・出資割合との違い
持ち株比率と出資比率・出資割合の違いは、株式数を基準にするか資本を基準にするかという点です。また、出資比率には、比率に応じた権利の付与はありません。
出資比率とは、出資金に対する特定の株主の出資割合です。出資比率は以下の式で計算されます。
出資比率(%)= (出資した金額 ÷ 全体の出資金額) × 100
株式会社では原則、持ち株比率は出資比率と同じです。一方、合同会社では、定款によって議決権や利益分配に出資比率と異なる比率を定められます。出資者間の不公平感につながる場合もあるので、異なる比率を定める際は慎重に進めましょう。
持ち株比率ごとの株主の権利
持ち株比率が大きくなると、株主が行使できる権利は増えていきます。持ち株比率ごとの株主の権利は以下の通りです。
| 持ち株比率 | 株主の権利 |
|---|---|
| 1%以上 | 株主総会の議案を取締役に提案できる(提案権) |
| 3%以上 | 株主総会の招集を取締役に請求できる 会計帳簿等の開示を請求できる |
| 33.4%以上 | 単独で特別決議を否決できる |
| 50.0%超 | 単独で普通決議を可決できる |
| 66.7%以上 | 単独で特別決議を可決できる |
| 90.0%以上 | ほかの株主からの強制的な株式買い上げ(スクイーズアウト)ができる |
上記の表の特別決議とは、事業譲渡や定款の変更・増資など会社の存続に関わる議案が該当します。普通決議とは、役員報酬の変更や取締役の解任・剰余金の配当など、経営陣や株主の権利に関わる議案です。
また、上記の比率は原則であり、定款によって異なる比率を定めることもできます。
創業者に必要な持ち株比率は?
適切な持ち株比率を維持することで安定した経営権を保持し、スピーディーな経営方針の決定が可能になります。これから創業する人や株式を発行する代表者は、以下の持ち株比率を参考にしましょう。
創業者に必要な持ち株比率は
- 経営への影響力を守るなら2/3以上
- 出資を受ける予定があるなら多めにもつ
経営への影響力を守るなら2/3以上
代表者の持ち株比率が66.7%以上(2/3以上)であれば、普通決議も特別決議も単独で通せます。定款変更など、事業の方針に関わる決断を周囲との調整なしに実行できるので、自分の裁量で会社経営ができるでしょう。
また、共同創業者がいる場合でも、代表者が2/3以上をもつことをおすすめします。共同創業者の中で持ち株比率を公平にすると不公平感は生まれませんが、経営への意見が対立した際に方針決定や調整に時間がかかる可能性があります。
特に創業期は、スピード感のある施策実行と試行錯誤が重要です。意思決定をスムーズに行えるよう、代表者ひとりに2/3以上の持ち株比率を配分しておくとよいでしょう。
出資を受ける予定があるなら多めにもつ
新規の出資を受けたり株主が増えたりすると、創業者を含む既存株主の持ち株比率は下がります。すでに予定がある場合は、あらかじめ余裕をもった持ち株比率を維持しておきましょう。
たとえば持ち株比率67%の状態で新規の出資を受けると、比率が66.7%(2/3)未満に下がるリスクがあります。単独での特別決議が通せなくなってしまうので、受ける予定の出資額などから逆算して持ち株比率を調整しておきましょう。
上場企業各社の代表者の持ち株比率と調べ方
上場企業各社の代表者の持ち株比率は、四季報や企業のIRで調べられます。
以下は、上場企業役員の持ち株比率の一例です(2024年3月時点)。
| 企業 | 役職 | 持ち株比率 |
|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 会長 | 0.144% |
| 三菱UFJフィナンシャルグループ | 執行役会長 | 0.000203% |
| ソニーグループ | 代表執行役 | 0.0000289% |
出典:株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ「有価証券報告書」
出典:ソニーグループ株式会社「有価証券報告書」
大企業では、銀行や保険会社、投資会社などがほとんどの株を保有していて、代表者を含む役員の持ち株比率は低い傾向があります。
持ち株比率が低いときの対処法
持ち株比率が低い場合、単独での議案可決が難しくなります。しかし以下の対処法によって、安定した経営への影響力を保持できます。
持ち株比率が低いときの対処法
- ほかの株主との信頼関係を築く
- 持ち株比率を上げる
ほかの株主との信頼関係を築く
代表者の持ち株比率が低いときは、ほかの株主と信頼関係を築き、経営への協力を促しましょう。
株主から信頼されていないと、新しい施策を提案しても意図が伝わらなかったり、感情的に反対されたりする可能性もあります。信頼感をもってもらえていれば、懸念点に対する建設的な指摘や代案の提案など、前向きな議論が行えます。
信頼関係の構築は一朝一夕にはかないません。持ち株比率が高いときから経営方針の説明やコミュニケーションを怠らず、独断的な経営にならないように心がけることが重要です。
持ち株比率を上げる
株主が多いなど個々の信頼関係構築が難しいときは、低くなってしまった持ち株比率自体を上げることも可能です。
持ち株比率を上げる方法
- 株式を新規発行する
- ほかの株主から買い取る
株式を新規で発行して代表者が保有すれば、持ち株比率を上げられます。しかし株式発行は特別決議が必要なので、そもそもほかの株主に新規発行を認めてもらわなければなりません。また、発行した株式を購入しなければならないので、まとまった購入資金も必要です。
一方、ほかの株主から買い取る場合は、普通決議によって譲渡の承認を受けます。特別決議よりハードルは低いものの、代表者への権限集中を忌避する株主もいるため、承認されるのは簡単ではありません。また、新規発行分の購入と同じく、買い取るための資金も必要です。
上記の通り、いずれの方法でもほかの株主の承認や資金が必要です。一度下がってしまった持ち株比率をすぐに上げることは難しいので、普段から比率が下がりすぎないよう注視しておきましょう。
持ち株比率が変わっても登記変更は不要
持ち株比率が変わっただけであれば、基本的に登記事項の変更は必要ありません。ただし、発行株式数に変更があった場合は、登記事項の変更が必要です。持ち株比率が変わった理由が株式の新規発行であるなら、登記変更を行いましょう。
株式に関する手続きは、譲渡事由や株主総会での決議内容によっても必要な手続きが異なります。持ち株比率が変わる、あるいは比率を調整したいときは、前もって司法書士に相談して手続きを進めてください。
まとめ
持ち株比率とは、発行済み株式数に対して特定の株主が所有する株式数の割合です。割合が高いほど株主総会での権限が強くなり、会社経営への影響力が高まります。
創業者や代表者の持ち株比率が低くなりすぎると、事業のスムーズな運営が阻害される可能性もあります。経営への影響を安定させるためには、発行数の2/3となる66.7%以上の持ち株比率を維持するようにしましょう。
もし比率が低い場合でも、ほかの株主との信頼関係があれば経営権を安定させることが可能です。ほかの株主の意見は、個人の誤った判断で会社が傾くことを防ぐ抑止力としても働きます。普段からコミュニケーションを取り、より良い経営判断ができる体制を整備することが重要です。
自分でかんたん・あんしんに会社設立する方法
会社設立の準備から事業開始までには、多くの書類や手続きが必要になります。書類の転記をするだけでもかなりの時間がかかってしまいます。
freee会社設立は株式会社だけでなく、合同会社の設立にも対応しています。設立件数30,000社以上の実績をもつfreee会社設立なら、初めての方もあんしんしてご利用いただけます。
起業ダンドリコーディネーターが完了までサポートしてくれるからあんしん!
初めての会社設立では、書類の書き方や提出先、設立後の手続きなどさまざまな場面で不安を抱えてしまうこともあるでしょう。
freee会社設立では、会社設立に詳しい起業ダンドリコーディネーターが常駐しており、設立準備から登記後に必要な手続きまでを完全無料で並走・サポートします。
相談方法はオンライン面談、LINE相談、電話、メールなどから選べます。まずお気軽に問い合わせフォームからおためし相談(最大30分)の予約をして、ご自身のスケジュールや設立手続きに関する疑問や不安を解消しましょう。
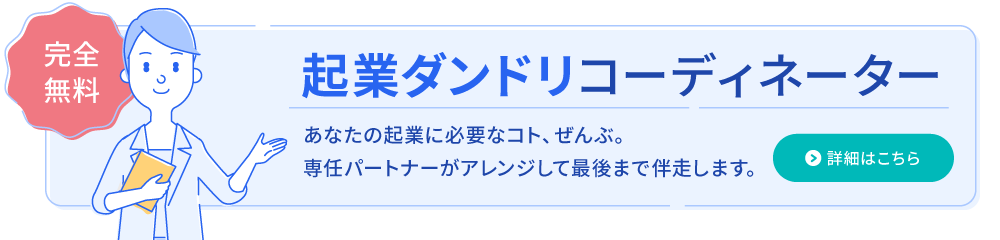
入力項目・次にやること、すべて画面上で把握できる
freee会社設立では、必要項目を記入していくだけで会社設立に必要な書類を作成することができます。また、登記の際に必要となる会社印も同時に購入が可能です。

freee会社設立は株式会社だけでなく、合同会社の設立にも対応しています。
会社名や資本金額など必要項目を入力すると、定款(ていかん)をはじめとする会社設立に必要な約10種類の書類を自動で作成します。
<freee会社設立で出力できる書類の一例>
- 定款
- 登記申請書
- 印鑑届出書 など
設立にかかるコストを削減できる
設立費用を削減したい方には電子定款がおすすめです。紙の定款では、収入印紙代40,000円がかかりますが、電子定款ではこれが不要となります。
freee会社設立は電子定款にも対応しており、電子定款作成に必要な機器やソフトの準備なども必要がないため、自分で作成するよりもコストを抑えることができます。
<設立にかかる費用の比較例>

(1)freee会計を年間契約すると、無料になります。
(2)紙定款の印紙代(40,000円)
会社設立の準備を進めながら、バーチャルオフィスの申し込みが可能!
会社設立するためにオフィスの住所が必要になります。
自宅をオフィス代わりにしている場合は、自宅の住所でも問題ありませんが、公開情報となってしまうので注意が必要です。
自宅兼オフィスのように実際の住所を公開したくない場合や、管理者や所有者に物件の法人登記が認められていない場合は、バーチャルオフィスを利用するのがおすすめです。
freee会社設立では、会社設立に必要な書類を無料で作りながら、バーチャルオフィスの申し込みもできます!
まずはこちらからfreee会社設立に無料で登録してみてください!
自分で手続きする時間のない方には「登記おまかせプラン」がおすすめ!
「初めての会社設立で不安」、「自分で手続きする時間がない」という方には、司法書士が手続きまで代行してくれる登記おまかせプランがおすすめです。
設立代行の費用相場は10万円前後ですが、freeeの登記おまかせプランは一律5万円で利用できます。※海外在留者が出資者・役員の場合等の特殊ケースを除く
登記おまかせプランの利用方法等の詳細は、freee会社設立の無料登録が完了後にメールにてご案内します。
会社設立の準備をお考えの方は、ぜひ登録無料のfreee会社設立をお試しください。
よくある質問
代表者は自社株の何%を保有するべき?
安定した経営権を保持するためには、66.7%以上の保有が目安です。66.7%以上の持ち株比率があれば、普通決議・特別決議とも単独で通すことが可能です。
詳しくは「創業者に必要な持ち株比率は?」をご覧ください。
持ち株比率が低いとどうなる?
持ち株比率が低いと、決議を単独で通せないため経営方針を単独で決めることが難しくなります。比率によっては議案の提案もできなくなるため、経営への影響力が下がり、やりたい施策がすぐに実行できないなどの弊害が出る可能性があります。
詳しくは「持ち株比率が低いときの対処法」をご覧ください。
監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)
神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。