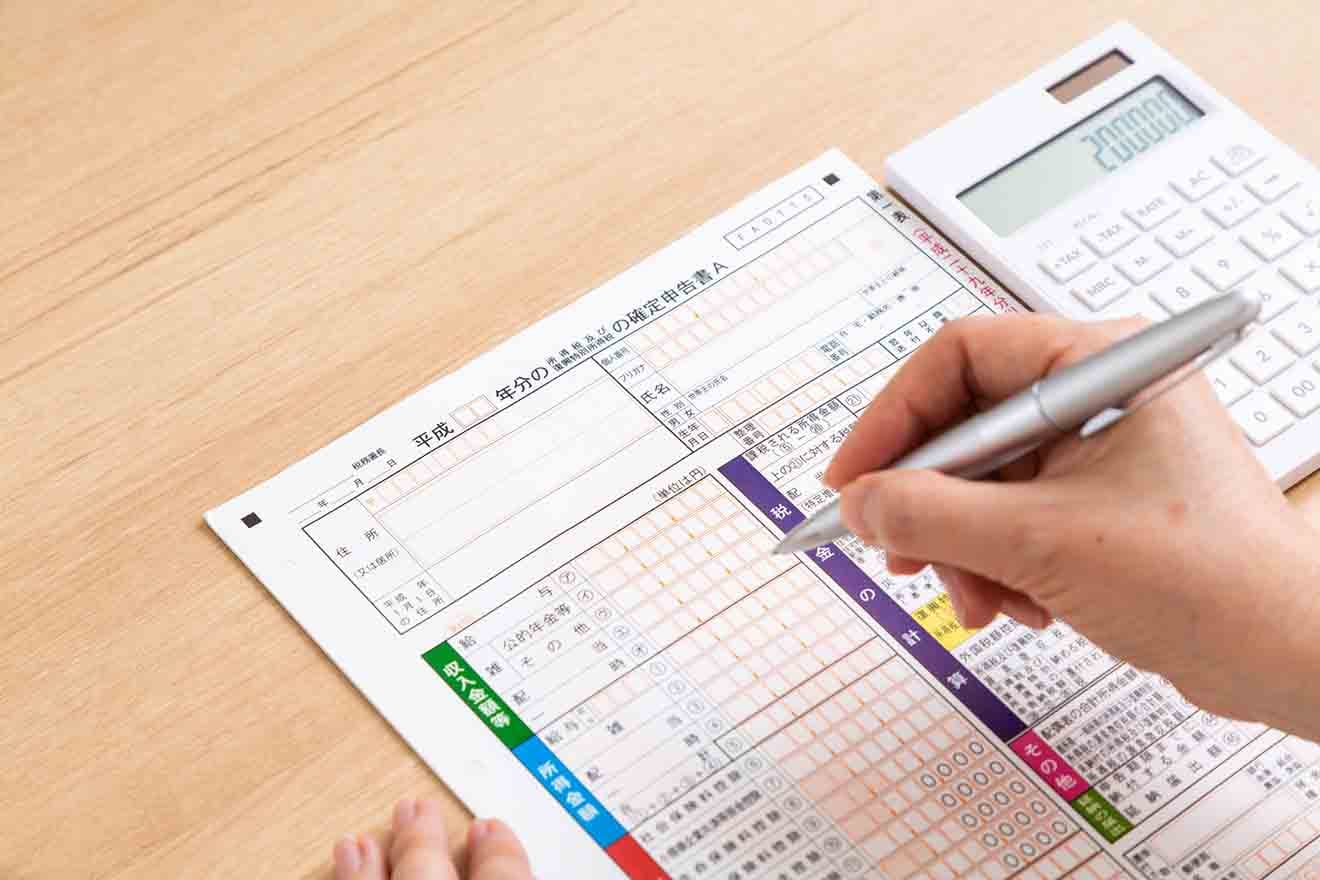
サラリーマンでも年の途中で転職した場合や、退職して就職活動をしている場合は確定申告が必要になることがあります。
ここでは、サラリーマンが確定申告をしなければいけないケースや、還付申告をすることで税金が戻ってくるケースなどについてご紹介します。
2023年最新情報を知りたい方は、別記事「退職金をもらったら確定申告は必要?したほうがいいケースや還付申告について解説」をご覧ください。
目次
freee会計で電子申告をカンタンに!
freee会計は〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポート!口座とのデータ連携によって転記作業も不要になり、入力ミスも大幅に削減します。
サラリーマンの所得税の精算は「年末調整」で実施
所得税は、1月1日~12月31日までの収入を対象に計算されます。
しかし、サラリーマンの場合は源泉徴収制度により、毎月の給与支払い時に、前もって所得税を仮の金額で納めています。それを精算する手続きが「年末調整」と「確定申告」です。
12月31日の時点で企業に所属しているサラリーマンでしたら、税金の計算は原則会社の年末調整で済むため、個人で確定申告をする必要はありません。一般的には、12月分の給与明細と一緒に年末調整の結果を記した源泉徴収票が渡されます。
毎月のお給料から源泉徴収されている所得税額の合計が、計算した1年分の所得税の金額より多すぎれば還付されます。12月分のお給料が他の月よりちょっとだけ増えていることが多いのは、給料が増えたわけではなく、払いすぎた所得税が還付されたためです。
サラリーマンが「確定申告」をしたほうがいい場合
サラリーマンが退職・転職をした場合、所得税の還付を受けるには自身で確定申告をする必要があります。
年末調整を受けていない場合
退職をしたその年の12月31日までに転職し、新しい会社で年末調整をしたものの、何らかの理由で前職の源泉徴収票を提出しなかった場合は、自分で確定申告をすると所得税が還付されることがあります。
転職先で年末調整したが、前職の源泉徴収票を提出しなかった場合
退職をしたその年の12月31日までに転職し、新しい会社で年末調整をしたものの、何らかの理由で前職の源泉徴収票を提出しなかった場合は、自分で確定申告をすると所得税が還付されることがあります。
原則として、退職したその年に以前勤めていた会社から受け取った給与が、20万円以下であれば確定申告の必要はありません。ですが、20万円を超えている場合は確定申告をしましょう。
以前勤めていた会社の源泉徴収が含まれているか確認する際は、転職後の会社から受け取った源泉徴収票の「支払金額」の欄を見ましょう。こちらに金額が含まれていなかった場合は、確定申告を行う必要があります。
以前の会社から源泉徴収票を受け取っていないという方は、連絡をして発行してもらいましょう。なお、確定申告で源泉徴収票を提出する際は、原票が必要となります。
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合
退職の際に「退職所得の受給に関する申告書」の書類を会社に提出しないと、税金が非常に高くなります。もし提出せずに退職した場合、確定申告で還付を受けられます。
「退職所得の受給に関する申告書」は国税庁のホームページからダウンロードすることが可能です。
確定申告をしたほうが得になるケースは?
退職をして、その年の12月31日までにどこの会社にも所属していない場合、ほとんどの方が確定申告(還付申告)をすることで、払いすぎた税金の還付を受けられます。
所得税の計算をする際は、生命保険料控除の適用を受けることができます。サラリーマンであれば年末調整でこれらの控除の計算をしてもらえますが、退職した場合は自分で確定申告をしないと適用されません。控除対象となる生命保険や医療保険などに加入している方は、忘れずに確定申告をしましょう。
また、退職後に国民年金や国民健康保険の保険料を支払った場合は、社会保険料控除の対象になります。国民年金は控除証明書の添付が必要になりますので、準備をしておきましょう。
下記では、退職して会社には所属をしていないけど、失業保険をもらっていたりアルバイトをして収入を得ているケースに関して紹介します。
失業保険をもらっているケース
退職はしてからどこにも所属はしていないけど失業保険を受け取っている場合、これを収入として申告するべきか悩まれる方もいらっしゃると思います。ですが、失業保険には所得税は発生しないので、確定申告をする必要はありません。
アルバイトをして収入があるケース
正社員ではないが、アルバイトをして収入を得ている方もいらっしゃるかと思います。もしアルバイト先が、前職の源泉徴収票を元に年末調整をしてくれた場合は、確定申告をする必要はありません。
ですが、アルバイトを2社以上掛け持ちしている場合は、自身でサラリーマン時代の給与所得とアルバイトで得た給与所得を合算して確定申告をしましょう。
退職金をもらった場合は確定申告で得することも!
退職金を受け取った場合、確定申告で税金が戻ってくることがあります。退職金の金額が多いほど戻ってくる金額も多くなりますので、しっかりチェックしましょう。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出
退職する際、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、所得税と住民税を正確に計算して源泉徴収してもらうことができます。退職所得の受給に関する申告書を提出せずに退職金を受け取った場合、退職金の額の20.42%(復興特別所得税を含む)の額が一律で源泉徴収されてしまいます。
退職金は、長年その会社に貢献した結果として受け取るものなので、税金はそれほどかからない仕組みになっています。確定申告をして払いすぎた税金の還付を受けましょう。
退職金に対する所得税の計算方法
退職金の場合、本来は退職金から退職所得控除額を引いて2分の1を掛けた退職所得に対して所得税が課税されます。
退職金が500万円、勤続年数が10年の場合を例にとって所得税の計算をしてみましょう。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合の所得税
500万円×20.42%=102万1,000円 - 「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合の所得税
税金がかかる元である退職所得は次の計算式で算出します。退職所得=退職金の額-退職所得控除額÷2
退職所得控除額の計算
退職所得控除額は、以下の計算で算出します。
勤続20年以下は1年ごとに40万円、勤続年数が20年を超えた場合は下記の計算で算出できます。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
| 20年以下 | 40万円×勤続年数 |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
注1:勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年として計算します。
注2:上記の算式によって計算した金額が80万円未満の場合は、退職所得控除額は80万円になります。
注3:障害者となったことに直接基因して退職した場合は、上記により計算した金額に、100万円を加算した金額が退職所得控除額です。
令和2年分所得税額の税額表
退職金に対する所得税は下記の表で算出できます。
通常の給与やボーナスとは税率や控除額が異なります。
退職金に対する所得税額=A×B-C
| A.課税退職所得金額 | B.税率 | C.控除額 |
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
※ここで算出した所得税額については、端数処理は行いません。
参考:国税庁「退職金と税|税について調べる」
<所得税の計算例>
勤続10年で退職金額500万円にかかる所得税額を計算してみます。
・退職所得控除額:40万円×10年=400万円
・退職所得:(500万円-400万円)÷2=50万円
・所得税の額:50万円×5%=25,000円
このように、本来ならば25,000円の所得税のはずが、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合、102万1,000円も源泉徴収されていることになり、確定申告をすることで99万6,000円もの所得税が還付されます。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しても、確定申告で得する?
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば所得税は正確に計算されていますが、それでも確定申告をすれば得になるケースもあります。
年の途中で退職をした場合、その年の収入が非常に少ないということがあります。所得税を計算する際は、給与所得から配偶者控除や扶養控除、基礎控除、生命保険料控除や地震保険料控除、社会保険料控除などを所得控除として差し引くことが可能です。
給与所得の額が少なくて所得控除が引ききれなかった場合は、余った分の金額を退職所得から差し引くこともできます。
この場合も確定申告をすることで所得税の還付を受けることができますので、忘れずにチェックしてください。
まとめ
サラリーマンであっても転職・退職をした場合、確定申告をしなければならないケースや、確定申告をすることで所得税が還付されるケースがあります。転職・退職をした方はしっかり確認しましょう。
確定申告をかんたんに終わらせる方法
確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。
ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。
そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。
freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。また、所得額や控除額の計算は自動で行ってくれるため、計算・入力ミスの削減できるでしょう。
ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。
1.銀行口座やクレジットカードは同期して自動入力が可能!
確定申告を行うためには、1年間のお金にまつわる取引を正しく記帳しなければなりません。自身で1つずつ手作業で記録していくには手間がかかります。
freee会計では、銀行口座やクレジットカードの同期が可能で、利用した内容が自動で入力されていきます。
日付や金額を自動入力するだけでなく、勘定科目も予測して入力してくれるため、日々の記帳がほぼ自動化でき、工数削減につながります。

2.現金取引の入力もカンタン!
会計ソフトでも現金取引の場合は自身で入力し、登録しなければなりません。
freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿付けが可能です。
自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、会計処理の経験がない人でも正確に記帳ができます。

さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになるので、わからないことがあったらすぐに相談できます。また、オプションサービスには電話相談もあるので、直接相談できるのもメリットの1つです。
freee会計の価格・プランについてはこちらをご覧ください。
3.〇✕形式の質問に答えるだけで各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!
各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。
freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。

4.確定申告書を自動作成!
freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。
また、freee会計はe-Tax(電子申告)にも対応しています。e-Taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。
e-Tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。



