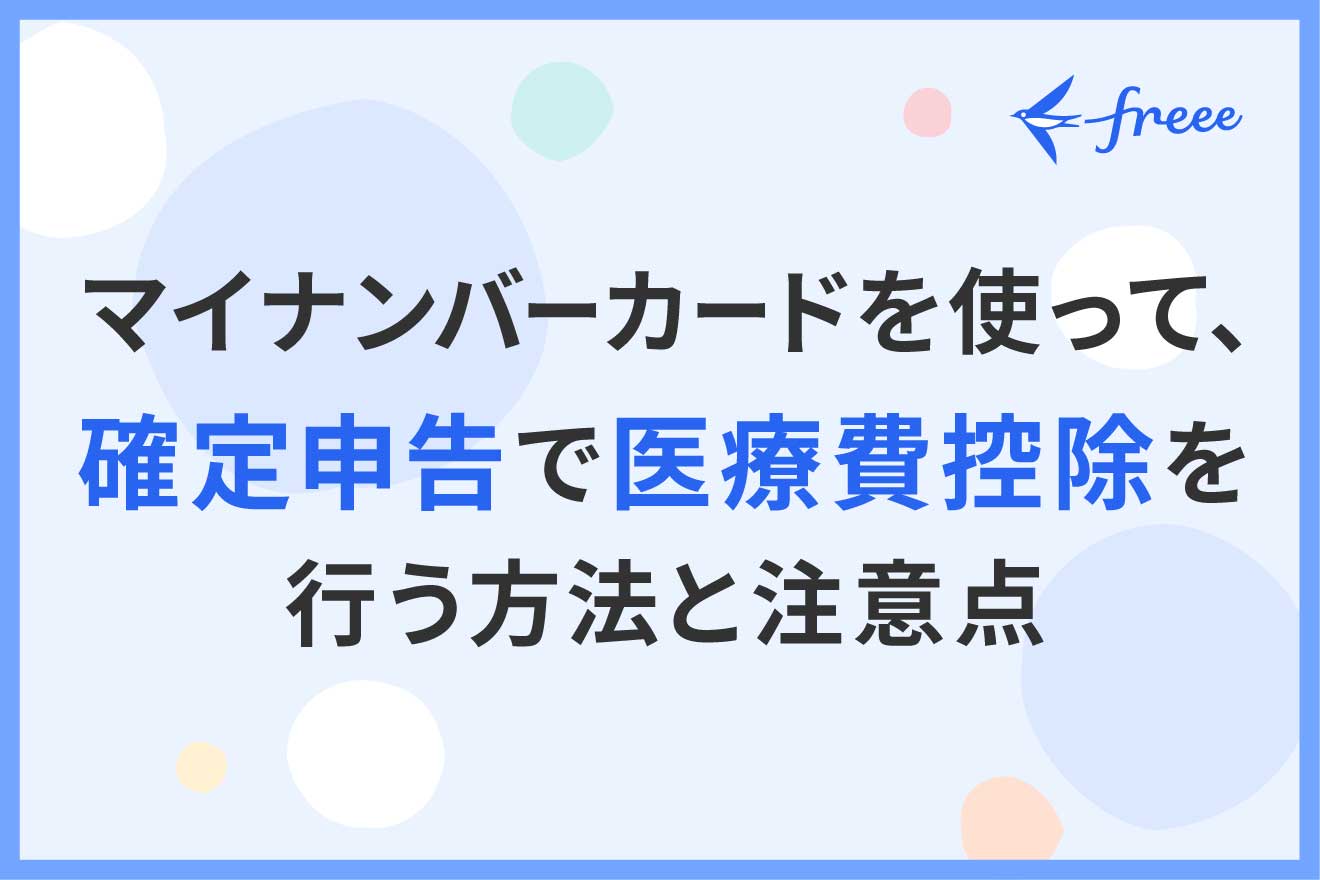
2021年10月から、「マイナ保険証」(マイナンバーカードを利用した健康保険証)が医療機関の窓口や薬局などで使えるようになりました。そして2023年4月からは、厚生労働省がマイナンバーカードを健康保険証として使えるシステムの導入を原則義務化しています。
マイナンバーカードを健康保険証と紐づければ、通院だけでなく医療費控除の手続きも簡単になります。本記事では、医療費控除の仕組みやマイナ保険証を使って医療費控除の申請をする手順、申請時の注意点まで解説します。
目次
- 医療費控除の仕組みを解説
- 医療費控除とは
- 医療費控除の要件
- 医療費控除で控除される金額
- マイナンバーカードの保険証利用について
- マイナンバーカードで医療費控除を申告する手順
- STEP1:マイナンバーカードを取得する
- STEP2:マイナンバーカードを健康保険証として登録する
- STEP3:マイナポータル上で医療費通知情報を確認する
- STEP4:確定申告書等作成コーナー(オンライン)で申告書を作成する
- マイナンバーカードで医療費控除を申告する際の注意点
- 保険診療以外は反映されない
- 1年分のデータが反映されるのは2月9日
- 領収書の保存が必要なケースがある
- 家族分の申告には代理人設定が必要
- まとめ
- 確定申告を簡単に終わらせる方法
- よくある質問
医療費控除の仕組みを解説
はじめに、医療費控除の仕組みを解説します。
医療費控除がある場合は確定申告時に明細書を作成し、金額を記載しなければなりません。そのため、仕組みや控除の条件などをあらかじめ理解しておくことが重要です。
医療費控除とは
医療費控除は所得控除のひとつで、1年間に10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等×5%)以上の医療費を支払った場合において最大200万円の控除が受けられる制度のことです。自分はもちろん、「自分と生計を一にする(日常生活において財産を共有している)配偶者や家族・親族」のために支払った医療費も対象になります。
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができます。
出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
医療費控除の対象期間は、その年の1月1日から12月31日までです。会社員は所得税の還付を受けることができ、個人事業主は所得税の節税につながります。控除を受けるには確定申告が必要なので、普段は年末調整のみの会社員の場合でも忘れずに確定申告を行いましょう。
医療費控除の要件
控除の対象となる医療費は以下の通りです。
- 納税者が、自分または自分と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費であること
- その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること(未払いの医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象になる)
医療費控除で控除される金額
医療費控除の上限金額は200万円です。実際に控除される金額は、以下の式を使って計算できます。
医療費控除が適用される金額の計算式
「実際に支払った医療費の合計額」 - 「保険金などで補填される金額(※1)」- 10万円(※2)
※1:保険金などで補てんされる金額は、給付目的となった医療費の金額を限度として差し引かれるため、引ききれない金額が生じてもほかの医療費からは差し引かれない
※2:総所得金額が200万円未満の場合は、総所得の5%にあたる金額
出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
マイナンバーカードの保険証利用について
2023年4月より、医療機関におけるマイナンバーカードを健康保険証として使えるシステムの導入が原則義務化され、「マイナ保険証」が使いやすくなりました。また、同年6月には改正マイナンバー法が成立し、2024年の12月2日に現行の健康保険証の新規発行が終了しました。
今後医療機関や薬局などではマイナンバーカードの利用が基本となっていきます。マイナンバーカードの取得やマイナンバーカードの健康保険証としての登録がまだの人は準備を検討しましょう。
マイナ保険証が使える医療機関や薬局には、目印にマイナ受付のステッカーとポスターが貼られています。対象の医療機関・薬局は以下のページから確認することも可能です。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ
【関連記事】
マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)とは?制度の概要やメリット・デメリット、登録方法をわかりやすく解説
マイナンバーカードで医療費控除を申告する手順
マイナ保険証を使えば、領収書の保管が不要になったり確定申告のデータ入力を省けたりするため、確定申告に関わる作業を効率化できます。また、各種行政手続きのオンライン窓口である「マイナポータル」を使って、通院歴・入院歴やかかった費用なども閲覧可能です。
以下では、マイナンバーカードの取得から医療費控除の申告までの手順を解説します。
STEP1:マイナンバーカードを取得する
マイナ保険証を使って医療費控除の手続きをするには、まずマイナンバーカードを取得する必要があります。マイナンバーカードを持っていない人は、初めにカードの交付申請をしましょう。
◆マイナンバーカードの申請
申請の方法は4種類です。申請時来庁方式・通知カード(個人番号通知書)に同封された交付申請書などで郵送する方法・オンライン(パソコン・スマートフォン)で行う方法・街中の証明写真機を使う方法があります。
| 項目 | 申請方法 |
| 来庁 | 指定の本人確認書類を持参し、直接窓口で手続きをする(持っている場合は「通知カード」と「住民基本台帳カード」も持参) |
| 郵送 | 個人番号カード交付申請書に従って各種項目を記入し、顔写真を貼り付けて投函する |
| オンライン | 専用サイトにアクセスしてメールアドレスを登録し、続けて顔写真と申請に必要な各種情報を入力する |
| 街中の証明写真機 | タッチパネルから「個人番号カード申請」を選び、お金を入れ、交付申請書に記載されたQRコードをバーコードリーダーにかざしてから顔写真を撮影・送信する |
◆交付通知書の受け取り
申請後、審査を経て1ヶ月程度でマイナンバーカードが発行されます。発行後に交付のための作業が行われ、各市区町村から交付準備ができたことをお知らせする個人番号カード交付通知書が届きます。
なおカードを受け取る前に申請を行った市区町村外に引っ越した場合は、新居のある市区町村で再度申請しなければなりません。
◆マイナンバーカードの受け取り
交付通知書が手元に届いたら、以下を持参して市区町村の窓口でカードを受け取ります。
- 交付通知書(はがき)
- 通知カード(持っている人のみ)
- 本人確認書類
- 住民基本台帳カード(持っている人のみ)
最後に窓口で本人確認を行い、暗証番号を設定したらカードが交付されます。
なお、申請時来庁方式の場合は申請時に役所に行き、後日郵送(本人限定受取郵便または簡易書留)で受け取ります。
STEP2:マイナンバーカードを健康保険証として登録する
マイナンバーカードを健康保険証として使うために「初回登録」を行います。初回登録はパソコンやスマートフォンだけでなく、セブン銀行ATMでも対応可能です。
◆スマートフォンを使ったやり方
- マイナポータルアプリをインストールする
- アプリを起動して「健康保険証利用申込」をタップする
- 「マイナポータル利用規約」を確認し、「同意して次へ進む」をタップする
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)を入力する
- スマートフォンを使ってマイナンバーカードを読み取る
◆パソコンを使ったやり方
- マイナポータルウェブサイトにアクセスする
- ページ内の「利用を申し込む」をクリックする
- 「マイナポータル利用規約」を確認し、「同意して次へ進む」をクリックする
- ICカードリーダーにマイナンバーカードを挿入し、「申し込む」をクリックする
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)を入力する
◆セブン銀行ATMを使ったやり方
- ATMの画面にある「マイナンバーカードでの手続き」をプッシュする
- 「健康保険証利用の申込み」をプッシュする
- 利用規約を確認し、マイナンバーカードを挿入する
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)を入力する
STEP3:マイナポータル上で医療費通知情報を確認する
マイナ保険証の登録作業が完了したら、マイナポータル上で医療費の情報を確認できるようになります。これは、マイナポータルが国税庁の電子申告・納税システム「e-Tax」と連携しているためです。
マイナポータルでは、2021年9月以降の毎月の医療保険の医療費通知情報を閲覧・取得できます。また、マイナ保険証に対応していない医療機関・薬局の医療費通知情報も閲覧可能です。医療費通知情報は医療機関などを受診した月の翌々月の11日から閲覧できるようになります。
出典:デジタル庁「マイナポータルの機能追加について(令和3年11月)」
STEP4:確定申告書等作成コーナー(オンライン)で申告書を作成する
医療費に関する情報を確認したら、申告書を作成します。マイナポータルは国税庁の「確定申告書等作成コーナー」と連携しているため、医療費通知情報のデータを自動で転記することが可能です。1年間の医療費を確定申告書に自動で入力できることから、資料作成の効率化につながります。
なお、「確定申告書等作成コーナー」からオンラインで申請した場合、マイナポータルから自動転記した医療費に関しては領収書の保存義務はありません。
マイナンバーカードで医療費控除を申告する際の注意点
マイナンバーカードを利用して医療費控除を行うと、医療費は確定申告書に自動入力されるほか、領収書の保存義務もないので非常に効率的です。
保険診療以外は反映されない
マイナポータル上では、医療機関の窓口や薬局で支払った「保険診療」にかかる医療費のみ管理できます。そのため、自費診療の支払いや通院費、ドラッグストアでの医薬品購入など、マイナ保険証と連携していない情報は反映されません。
1年分のデータが反映されるのは2月9日
確定申告時に記載する1年分の医療費通知情報は、原則として翌年の2月9日に一括で取得できます。確定申告の申告期限は通常、「2月16日から3月15日まで」です。税金が戻ってくる場合の申告(還付申告)は2月16日より前に可能ですが、早めに還付申告をしたくても、2月9日まで医療費の自動入力はできないので注意しましょう。
領収書の保存が必要なケースがある
「確定申告書等作成コーナー」でオンライン申請した場合、マイナポータルから自動転記した医療費については領収書の保存義務がありません。ただし、それに該当しない医療費の領収書(自費診療の支払い・通院費・ドラッグストアでの医薬品購入など)は自宅で5年間保存する必要があります。マイナポータルのWeb画面やPDFを印刷・ダウンロードしたものは原本にはあたらないため、手元にある領収書を大切に保存してください。
家族分の申告には代理人設定が必要
医療費控除は、「自分と生計を一にする配偶者や家族・親族」の分をまとめて申告できますが、マイナポータル上で取得可能な医療費通知情報は本人分のみです。家族・親族分の医療費も合算して申告したいなら、マイナポータル上で代理人設定をしなければなりません。また、本人・家族間で代理人設定をする場合には、家族もマイナンバーカードを取得している必要があります。
まとめ
マイナ保険証によって、煩雑だった確定申告の作業を効率化できます。2023年4月から医療機関においてマイナンバーカードを健康保険証として使えるシステムの導入が原則義務化し、2024年12月から現行の健康保険証の新規発行が廃止されました。「マイナ保険証」の登録がまだの人は早めに準備を考えておくとよいでしょう。
今回ご紹介した手順を参考に、マイナンバーカードを使って効率的に医療費控除の手続きを進めてみてください。
確定申告をかんたんに終わらせる方法
確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。
ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。
そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。
freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。また、所得額や控除額の計算は自動で行ってくれるため、計算・入力ミスの削減できるでしょう。
ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。
1.銀行口座やクレジットカードは同期して自動入力が可能!
確定申告を行うためには、1年間のお金にまつわる取引を正しく記帳しなければなりません。自身で1つずつ手作業で記録していくには手間がかかります。
freee会計では、銀行口座やクレジットカードの同期が可能で、利用した内容が自動で入力されていきます。
日付や金額を自動入力するだけでなく、勘定科目も予測して入力してくれるため、日々の記帳がほぼ自動化でき、工数削減につながります。

2.現金取引の入力もカンタン!
会計ソフトでも現金取引の場合は自身で入力し、登録しなければなりません。
freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿付けが可能です。
自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、会計処理の経験がない人でも正確に記帳ができます。

さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになるので、わからないことがあったらすぐに相談できます。また、オプションサービスには電話相談もあるので、直接相談できるのもメリットの1つです。
freee会計の価格・プランについてはこちらをご覧ください。
3.〇✕形式の質問に答えるだけで各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!
各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。
freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。

4.確定申告書を自動作成!
freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。
また、freee会計はe-Tax(電子申告)にも対応しています。e-Taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。
e-Tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。

freee会計を使うとどれくらいお得?
freee会計には、会計初心者の方からも「本当に簡単に終わった!」というたくさんの声をいただいています。
税理士などの専門家に代行依頼をすると、確定申告書類の作成に5万円〜10万円程度かかってしまいます。freee会計なら月額980円(※年払いで契約した場合)から利用でき、自分でも簡単に確定申告書の作成・提出までを完了できます。
余裕をもって確定申告を迎えるためにも、ぜひfreee会計の利用をご検討ください。
よくある質問
マイナンバーカードを使って医療費控除をするやり方を教えて!
「マイナ保険証」を使って医療費控除を申告する大まかな流れは以下の通りです。
- STEP1:マイナンバーカードを取得
- STEP2:マイナンバーカードを健康保険証として登録
- STEP3:マイナポータル上で医療費通知情報を確認
- STEP4:確定申告書等作成コーナーで申告書を作成
マイナンバーカードの申請や健康保険証として登録する方法は複数あるため、自分にあった方法で行いましょう。
詳しくは記事内の「マイナンバーカードで医療費控除を申告する手順」をご覧ください。
医療費控除をスマホから申請するにはどうすればいい?
新規に申請する場合は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から、「申告書等を作成する」の項目にある「作成開始」をクリックします。提出方法に関する質問に回答し、マイナンバーカードを持っている場合は、「スマートフォンを使用してe-Tax」から進みましょう。
「確定申告書等作成コーナー」とマイナポータルは連携しているため、医療費通知情報の自動転記が可能です。
詳しくは記事内の「STEP4:確定申告書等作成コーナー(オンライン)で申告書を作成する」をご覧ください。
マイナンバーカードで家族の医療費控除もできる?
「自分と生計を一にする配偶者や家族・親族」の申請は可能です。しかし、そのためにはマイナポータルで代理人設定をしておかなければならないなどの条件もあります。
詳しくは記事内の「家族分の申告には代理人設定が必要」をご覧ください。



