監修 安田亮 安田亮公認会計士・税理士事務所
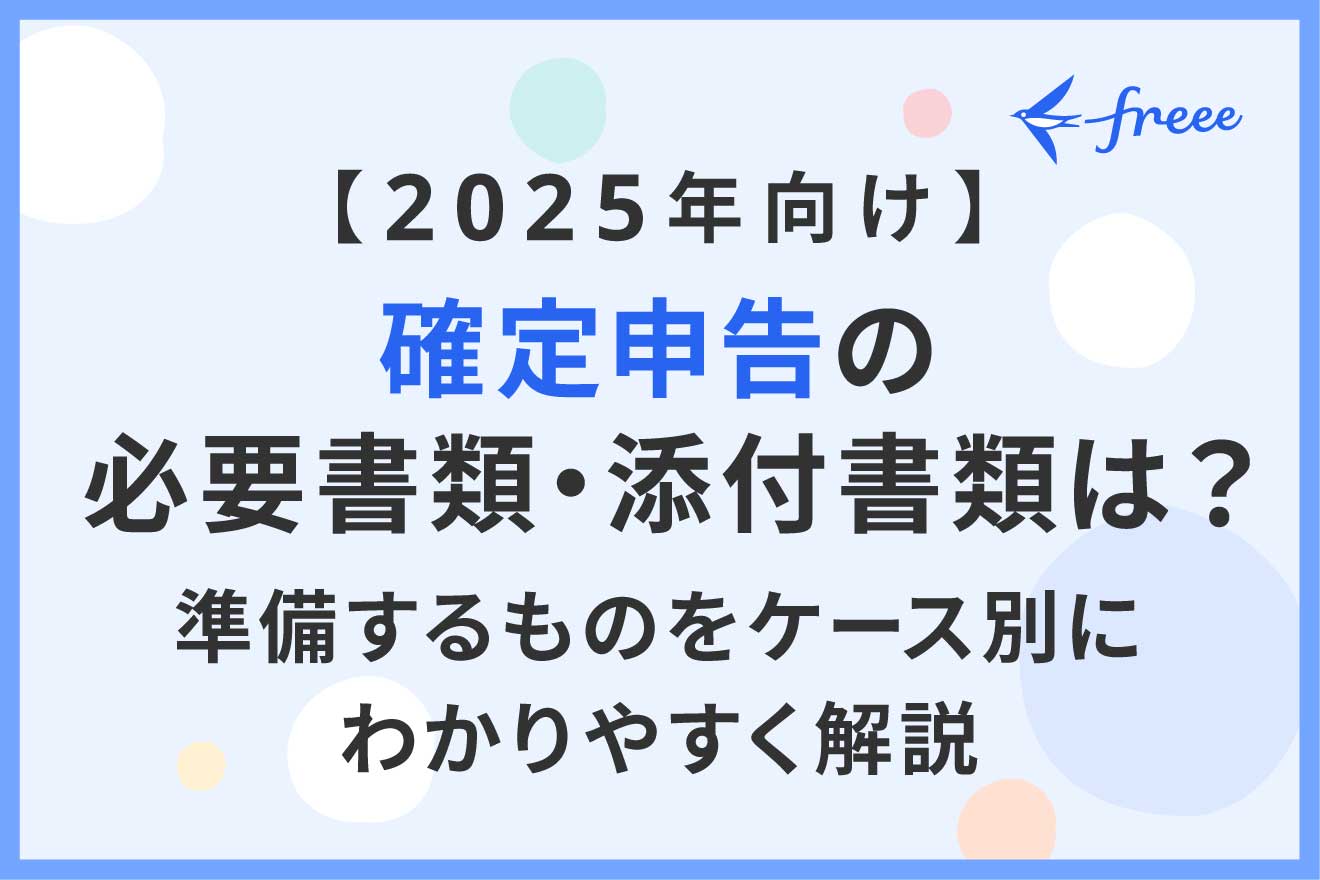
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得金額および所得税の金額を計算し、納税すべき税額を申告する手続きです。
申告期間は原則、対象年の翌年2月16日〜3月15日の間で、当該期間中に申告しなければなりません。確定申告の際は、納税額を計算するために必要な書類や申告書への添付が必要な書類があるため、申告期間が始まる前に準備しておきましょう。
本記事では、確定申告書の作成に必要な書類や添付書類、添付不要になった書類について詳しく解説します。また、書類の添付方法も紹介しますので参考にしてください。
目次
- 確定申告に共通して必要な書類
- 確定申告書
- 本人確認書類
- 所得金額がわかる書類
- 各種控除申請に必要な書類
- 銀行口座がわかるもの
- 個人事業主やフリーランスが確定申告するときの必要書類
- 青色申告を行う際の添付書類と必要書類
- 白色申告を行う際の添付書類と必要書類
- 会社員が確定申告したほうがよい場合と各必要書類
- 雑損控除の適用を受けるとき
- 医療費控除の適用を受けるとき
- セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けるとき
- 寄附金控除を受けるとき
- 年金受給者が確定申告するときの必要書類
- 書類の添付方法
- 確定申告の必要書類を提出する方法
- 税務署へ持ち込む
- 税務署または業務センターへ郵送する
- e-Taxを利用する
- 確定申告をかんたんに終わらせる方法
- まとめ
- よくある質問
確定申告に共通して必要な書類
確定申告に必要な書類は、会社員や年金受給者、個人事業主など、所得や控除の種類などによってさまざまです。しかし、どの立場で確定申告をする場合でも、共通して必要な書類が存在します。まずは、確定申告に必要な共通書類を揃えましょう。
確定申告に必要な書類一覧
なお、2019年4月1日以降、確定申告をする人の作業負担軽減と手続きの簡素化を目的に一部の書類の添付および押印が不要になりました。提出が不要になった書類については以下の各見出し内で紹介します。
確定申告書
確定申告書は、1月1日から12月31日までの年間所得額や控除額とその種類、それらをもとに計算された所得税を記載した書類です。
以前は申告者の所得の種類に応じて申告書Aと申告書Bがありましたが、2023年1月からは申告書Bの様式に統合されました。
確定申告書は、税務署や確定申告会場、または市区町村の担当窓口や指導相談会場でも受け取れます。また、国税庁のホームページでダウンロードすることも可能です。
【関連記事】
【2025年最新】令和6年分確定申告書の見方と書き方を項目別にわかりやすく解説
本人確認書類
確定申告には、マイナンバーカードや通知カード(個人番号通知書)、個人番号が記載された住民票の写しなど、マイナンバーが記載された本人確認書類が必要です。
マイナンバーカードであれば単体で本人確認が完了しますが、通知カード(個人番号通知書)や個人番号が記載された住民票を利用する場合、追加で以下のような身元確認書類が必要になります。
確定申告に必要な本人確認書類
- 運転免許証
- 健康保険証
- パスポート
- 在留カード
申告書を直接税務署に提出する場合は、窓口で本人確認書類の提示、またはコピーの添付をします。確定申告書類を郵送する場合は、本人確認書類のコピーを一緒に送付します。
e-Taxで申告する際はマイナンバーカードを用いるか、事前に税務署でID・パスワードを発行する必要があるため、状況に応じて前もって準備を進めましょう。
所得金額がわかる書類
確定申告の対象年に得た所得金額がわかる、以下の書類を所得の種類に応じて添付します。
所得金額に関する添付書類
- 青色申告決算書
- 事業所得の内訳を記載している収支内訳書など(白色申告の場合)
- 株の取引による年間取引計算書
- その他、収入を明らかにできる書類
2019年4月1日以降は、給与所得の源泉徴収票や退職所得、公的年金等の源泉徴収票は添付不要になりました。
各種控除申請に必要な書類
給与所得がある人は、年末調整で生命保険料控除・医療費控除・社会保険料控除などの15種類の所得控除を受けられます。すでに年末調整で申告が済んでいる書類は、確定申告では添付不要です。
ただし以下の控除は、年末調整ではなく確定申告時に申請しなければいけません。
| 控除の種類 | 概要 | 控除額 |
|---|---|---|
| 雑損控除 | 災害や盗難、横領などによる損害を受けたとき |
・(差引損失額)-(総所得金額等)× 10% ・(差引損失額のうち災害関連支出の金額)- 5万円 上記のいずれか多いほう |
| 医療費控除 |
一定額以上の医療費を支払ったとき (本人および同一生計の配偶者や親族の医療費も含める) |
(支払った医療費-保険金などで補填される金額) - 10万円※ ※その年の所得金額が200万円未満の場合は、所得金額 × 5% |
| 寄附金控除 | ふるさと納税や認定NPO法人等に対して寄附をしたとき | (「寄附金支出合計額」と「所得 × 40%」のいずれか少ないほう)- 2,000円 |
出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
出典:国税庁「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
それぞれの控除の手続きに必要な書類は以下の通りです。
| 控除の種類 | 必要書類 |
|---|---|
| 雑損控除 |
提示または添付書類 ・災害に関しての支出を証明する書類 (請求書や領収書など) |
| 医療費控除 |
添付書類 ・医療費控除の明細書 ・医療費通知 保管書類 ・医療費の領収書 |
| 寄附金控除 | 寄附金額を証明する書類 |
出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
出典:国税庁「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
また、以下の書類についても2019年4月1日より添付が不要となりました。
添付が不要になった書類
- オープン型証券投資信託の収益分配の支払通知書
- 配当等の支払通知書
- 上場株式配当等の支払通知書
- 特定口座年間取引報告書 など
また、e-Taxで電子申告する場合には、郵送や窓口で申告するよりも添付不要とされる書類の種類が多くあります。マイナポータル連携を利用することで、さらに添付書類を減らすことも可能です。
確定申告で受けられる所得控除について詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。
【関連記事】
税金の控除制度とは? 所得控除・税額控除の種類や違いを解説
銀行口座がわかるもの
所得税が還付される場合は確定申告書に銀行口座を記載する必要があるので、通帳やカードといった口座番号がわかるものを用意しましょう。申告書提出時の添付は不要です。
確定申告では、不足分の税金を納めるだけでなく、払いすぎた税金が還付されることがあります。還付されるのは次のようなケースです。
| 対象者 | 還付対象となる場合 |
|---|---|
| 総合課税の対象所得がある人 | 年間所得額が一定以下の場合 |
| 給与所得者 |
年末調整対象外の控除を受ける場合 ・医療費控除 ・寄附金控除 ・1年目の住宅ローン控除 年末調整で申請が漏れた控除がある場合 |
| 公的年金の受給者 | 各種控除を受ける場合 |
| 対象年の途中で退職し、再就職していない人 | 退職した会社の給与所得の分の年末調整を受けていない場合 |
| 退職所得がある人 |
以下の項目に該当する場合 ・「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない ・再就職先での年末調整時に前職の源泉徴収票を提出していない ・退職所得以外の所得から所得控除を差し引いたときに赤字になる |
所得税の還付金が発生するのは、予定納税や源泉徴収で納めた金額が、実際に納めるべき税額よりも多いときなどです。
会社員や公務員の人は、年末調整により、すでに税金の源泉徴収が済んでいます。上表のような所得控除の対象であれば、確定申告を通じて還付を受けられるケースが一般的です。
還付金額は提出する確定申告書の「還付される税金」の欄に記入します。
【関連記事】
還付申告とは?対象となるケースや確定申告・年末調整との違いを解説
個人事業主やフリーランスが確定申告するときの必要書類
事業所得がある個人事業主やフリーランスが確定申告をする場合は、青色申告または白色申告のどちらかで申告します。青色申告と白色申告には以下のような違いがあります。
青色申告と白色申告の違い
- 税制上の優遇措置
- 事前手続きの有無
- 提出書類
- 保存帳簿
- 帳簿の記載方法 など
青色申告で確定申告をする人は、その年の3月15日までに開業届と青色申告承認申請書を、管轄の税務署に提出しなければいけません。
青色申告を行う際の添付書類と必要書類
青色申告の承認を得ると、55万円(要件を満たした場合は65万円)と10万円の控除のどちらかを選んで税制上の優遇措置を受けられます。また青色申告では特別控除を受けられるだけでなく、次のようなメリットもあります。
青色申告のメリット
- 青色事業専従者給与を経費として計上できる(家族に対する給与)
- 純損失の繰越しと繰戻しができる
- 30万円未満で取得した資産は一括で経費計上できる
青色申告で確定申告をする場合は、確定申告書と以下の書類を準備しましょう。
| 55万円控除(最大65万円) | 10万円控除 | |
|---|---|---|
| 提出する書類 |
・確定申告書 ・青色申告決算書 ・賃借対照表 ・損益計算書 ・第三表(分離課税用、事業所得に加え譲渡所得がある場合) ・第四表(損失申告用、赤字で青色申告する場合) |
・確定申告書 ・青色申告決算書 ・損益計算書 ・第三表(分離課税用、事業所得に加え譲渡所得がある場合) ・第四表(損失申告用、赤字で青色申告する場合) |
| 保存する書類 |
・総勘定帳 ・仕訳帳 ・現金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・固定資産台帳 ・決算に関して作成した棚卸表 |
・現金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・固定資産台帳 ・経費帳 ・決算に関して作成した棚卸表 |
出典:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」
それぞれの帳簿や書類の保存期間は次の通りです。
| 帳簿・書類 | 保存期間 |
|---|---|
|
各種帳簿
・仕訳帳 ・総勘定元帳 ・現金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・経費帳 ・固定資産台帳 など | 確定申告期限の翌日から7年間 |
|
各種書類
・損益計算書 ・貸借対照表 ・棚卸表 ・領収証 ・小切手控 ・預金通帳 ・借用証などの現金預金取引等関係書類 | 確定申告期限の翌日から7年間 |
|
その他
・請求書 ・見積書 ・契約書 ・納品書 ・送り状 など | 確定申告期限の翌日から5年間 |
青色申告の必要書類について詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。
【関連記事】
青色申告とは?白色申告との違いや豊富なメリット、必要な準備・書類を解説
白色申告を行う際の添付書類と必要書類
白色申告では、青色申告のように事前の申請は不要です。税制の優遇措置はありませんが、簡易簿記だけで済み、手続きしやすいメリットがあります。
白色申告で必要な書類は以下の通りです。
| 提出する書類 | 保存する書類 |
|---|---|
| ・確定申告書 ・収支内訳書 | ・法定帳簿 ・任意帳簿 |
白色申告で保存すべき帳簿や書類の期間は、下記をご覧ください。
| 帳簿 | 法定帳簿 (収入金額や必要経費に関するもの) | 確定申告期限の翌日から7年間 |
| 任意帳簿 (業務に関係するもの) | 確定申告期限の翌日から5年間 | |
| 書類 | 決算に関係する書類 | 確定申告期限の翌日から5年間 |
|
業務上作成または受領した以下の書類
・請求書 ・納品書 ・送り状 ・領収書 など |
申告書の作成に必要であるものの添付不要な書類は、青色申告と同様です。青色申告は白色申告に比べて手続きや記帳が複雑ですが、要件を満たすと最大65万円の控除が受けられるなど、大きな節税効果を得られます。
【関連記事】
確定申告は青色申告と白色申告の2種類!それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説
会社員が確定申告したほうがよい場合と各必要書類
原則として、給与所得者は年末調整により年間の所得税の精算を行いますが、以下の項目に該当する場合は確定申告が求められます。
会社員で確定申告が必要な場合
- 給与収入が2,000万円を超えている
- 副業や株式売買による所得が20万円を超える
2ヶ所以上から給与所得を受け取り、本業の会社以外の所得が20万円を超える場合は確定申告をする必要があり、申告をすることで所得税の還付が受けられる場合もあります。
控除を受ける条件や必要書類についてより詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
【関連記事】
会社員で確定申告が必要な人とは?ふるさと納税や副業など事例別にやり方を解説
会社員の副業はいくらから確定申告が必要?副業の開始前に知るべき手続きや注意点について解説
また確定申告をすると、以下のような所得控除を受けられます。
それぞれ詳しく解説します。
雑損控除の適用を受けるとき
雑損控除とは、災害や盗難、横領などによって損害を受けたときに適用される所得控除です。「雑損控除の対象になる資産の要件」にあてはまる資産について損害を受けた場合に、一定の金額の所得控除を受けられます。
なお、受けられる雑損控除の金額は、以下のうちいずれか多いほうの金額です。
- (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
- (災害関連支出の金額-保険金等の額)- 5万円
また、雑損控除の対象者や対象物は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 雑損控除を受けられる対象者 |
・納税者 ・納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の人 |
| 雑損控除を受けられる対象資産 | 棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産 |
| 損害の原因 |
・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害 ・火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害 ・害虫などの生物による異常な災害 ・盗難 ・横領 |
雑損控除の申請をする際には、確定申告書に雑損控除に関する事項を記載し、支出の金額の領収を証する書類を添付するか提示する必要があります。
医療費控除の適用を受けるとき
医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日までの間)で支払った医療費が一定の金額を超えたときに適用される所得控除です。
自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合で、支払った医療費が以下の金額を超えたときに適用されます。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
保険金などで補てんされる金額
(2)10万円
ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%の金額
出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
たとえば、年間に支払った医療費が20万円で、保険金で補填される金額がなければ「20万円-10万円=10万円」が所得控除の対象です。この場合、「10万円×所得税率」が還付されます。
医療費控除の適用を受けるには、確定申告書と医療費控除の明細書を提出します。
【関連記事】
確定申告で医療費控除を受けるには?やり方・計算方法をわかりやすく解説
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けるとき
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例とは、ドラッグストアやコンビニなどで「特定一般用医薬品等」を購入したときに適用される所得控除です。
年間の「特定一般用医薬品等購入費」が12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)が控除の対象となります。たとえば、年間で5万円の特定一般用医薬品等購入費がある場合、38,000円の所得控除を受けられます。
確定申告時に、確定申告書とセルフメディケーション税制の明細書を提出しましょう。
寄附金控除を受けるとき
寄附金控除とは、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して「特定寄附金」を支出したときに受けられる所得控除です。
ふるさと納税をしたときに受けられる控除が、寄附金控除にあたります。寄附金控除の金額の計算式は以下の通りです。
次の(1)または(2)のいずれか低い金額 -2,000円 = 寄附金控除額
(1) その年に支出した特定寄附金の額の合計額
(2) その年の総所得金額等の40パーセント相当額
出典:国税庁「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
なお、ふるさと納税では納税者の負担を軽減するために「ワンストップ特例制度」が用意されています。
ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。1年間(1月1日から12月31日まで)のふるさと納税の寄附先が5自治体以内で、確定申告を行う必要がない人が利用できます。
寄附先の自治体に、寄附した翌年1月10日までに必要書類を提出すれば、ワンストップ特例制度を利用できます。
ワンストップ特例制度を利用すると、寄附先の自治体が必要な手続きを進めてくれるため、確定申告が不要です。
【関連記事】
確定申告でふるさと納税の控除を受けるには?やり方や必要書類についても解説
年金受給者が確定申告するときの必要書類
年金受給者は、年金の受取額が400万円以下かつその他副収入(雑所得など)が年間20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。
ただし、各種控除を申告する場合や、公的年金以外の収入が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。年金受給者が確定申告する際に必要な書類は以下の通りです。
年金受給者が各種控除申請する場合に必要な書類
- 確定申告書
- 本人確認書類
- 各種控除に必要な書類
公的年金以外の収入がある場合に必要な書類
- 確定申告書
- 本人確認書類
- 所得を証明する書類
年金から税金が源泉徴収されている人でも、住宅ローン控除や雑損控除、医療費控除などを受けられる場合は確定申告をすることで税金の還付が発生する可能性があります。
【関連記事】
年金受給者は確定申告が必要?必要な人・不要な人を事例別に解説
書類の添付方法
確定申告の添付書類は、紙での提出とe-Taxとで異なります。
紙で申請するときは、添付書類台紙に各種添付書類を貼り付けます。添付台紙は2枚あり、1枚目に本人確認書類のコピーを、2枚目に社会保険料や生命保険料などの控除証明書を添付します。
原則として、書類はのり付けして提出しますが、書類の大きさなどの関係でのり付けが難しい場合はホチキスやテープの使用も可能です。
e-Taxで確定申告をする場合は添付を省略できる書類も多く、添付が必要な場合も電子データで提出ができます。
確定申告の必要書類を提出する方法
確定申告の手続き方法は、税務署への持ち込み・郵送での提出・e-Taxを用いた申請の3つです。
それぞれの提出方法について、メリット・デメリットを詳しく解説します。
税務署へ持ち込む
必要書類を用意したうえで、税務署の窓口に持参する方法があります。税務署では確定申告の時期になると特設窓口を設けており、書類の書き方や帳簿の付け方などに関するサポートを受けることが可能です。
直接持ち込めば、税務署の職員に内容をチェックしてもらえるため、「正しい申告ができているか不安」という人におすすめです。
ただし、確定申告の時期は窓口が混むため、提出する際は時間に余裕を持って訪れましょう。提出のみの場合は、税務署にある時間外収受箱への投函も24時間可能です。
税務署または業務センターへ郵送する
確定申告書と添付書類を揃えたうえで、納税地の税務署または業務センターへ郵送で提出する方法があります。郵送の場合、直接税務署へ足を運ぶ必要がありません。
ただし、郵送や信書で送る場合は「通信日付印」が提出日とみなされるため、期限間際の提出にならないように注意しましょう。
なお、確定申告書は「信書」扱いになるため、「郵便物(第一種郵便物)」または「信書便物」で送付してください。
【関連記事】
確定申告書は郵送できる?郵送方法や封筒の書き方・注意点について解説
e-Taxを利用する
e-Taxを利用すれば、税務署に出向くことなく、自宅や事務所にいながら好きな時間に確定申告ができます。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーやe-Taxと連携している会計ソフトウェアから手続きを進めることができます。
e-Taxと連携する会計ソフトウェアを活用すれば、申告の際に数値を入力する手間も省け、入力漏れやミスも防げて便利です。
また、e-Taxは窓口や郵送での申告と比べて還付金の処理が早く、スムーズに還付金を受け取れるメリットもあります。
【関連記事】
e-Tax(電子申告)で確定申告をするやり方とは?スマホでの流れや必要書類を解説
確定申告をかんたんに終わらせる方法
確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。
ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。
そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。
freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。また、所得額や控除額の計算は自動で行ってくれるため、計算・入力ミスの削減できるでしょう。
ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。
1.銀行口座やクレジットカードは同期して自動入力が可能!
確定申告を行うためには、1年間のお金にまつわる取引を正しく記帳しなければなりません。自身で1つずつ手作業で記録していくには手間がかかります。
freee会計では、銀行口座やクレジットカードの同期が可能で、利用した内容が自動で入力されていきます。
日付や金額を自動入力するだけでなく、勘定科目も予測して入力してくれるため、日々の記帳がほぼ自動化でき、工数削減につながります。

2.現金取引の入力もカンタン!
会計ソフトでも現金取引の場合は自身で入力し、登録しなければなりません。
freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿付けが可能です。
自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、会計処理の経験がない人でも正確に記帳ができます。

さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになるので、わからないことがあったらすぐに相談できます。また、オプションサービスには電話相談もあるので、直接相談できるのもメリットの1つです。
freee会計の価格・プランについてはこちらをご覧ください。
3.〇✕形式の質問に答えるだけで各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!
各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。
freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。

4.確定申告書を自動作成!
freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。
また、freee会計はe-Tax(電子申告)にも対応しています。e-Taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。
e-Tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。

freee会計を使うとどれくらいお得?
freee会計には、会計初心者の方からも「本当に簡単に終わった!」というたくさんの声をいただいています。
税理士などの専門家に代行依頼をすると、確定申告書類の作成に5万円〜10万円程度かかってしまいます。freee会計なら月額980円(※年払いで契約した場合)から利用でき、自分でも簡単に確定申告書の作成・提出までを完了できます。
余裕をもって確定申告を迎えるためにも、ぜひfreee会計の利用をご検討ください。
まとめ
確定申告の添付書類は申告の種類によって異なりますが、本人確認書類や所得金額がわかる書類、各種控除申請のための書類などが求められます。
書類の中には、納税者の利便性向上を目的として添付不要になったものもあります。また、添付が不要でも、一定期間の保管が必要な書類もあるため、自身の申告内容に応じた必要書類を確認してから準備を進めましょう。
よくある質問
確定申告の添付書類は?
確定申告に必要な添付書類は、本人確認書類や所得金額がわかるもの、各種控除申請に必要な書類などです。
ただし申告書の提出時に添付が不要でも、保管が必要な書類もあるため、事前に保管書類について確認しておきましょう。
詳しくは、「確定申告に共通して必要な書類」をご覧ください。
確定申告で添付が不要になった書類は?
確定申告では、源泉徴収票・上場株式配当等の支払通知書・特定口座年間取引報告書などの書類の添付は不要になりました。
詳しくは、「確定申告に共通して必要な書類」をご覧ください。
監修 安田 亮(やすだ りょう)
1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。




