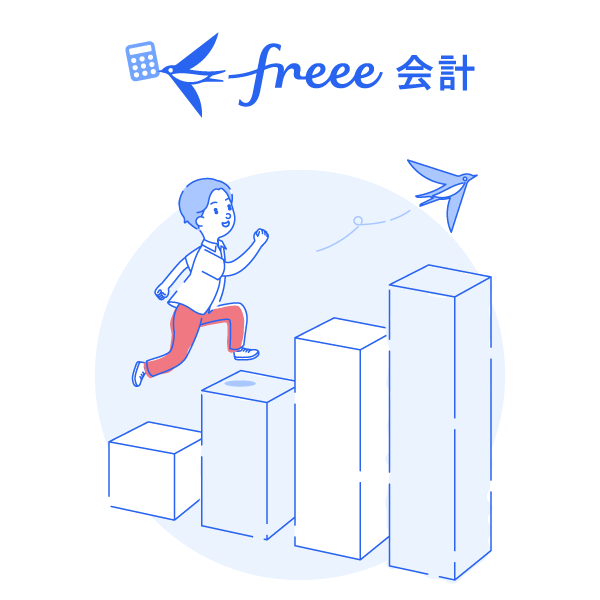監修 前田 昂平(まえだ こうへい) 公認会計士・税理士
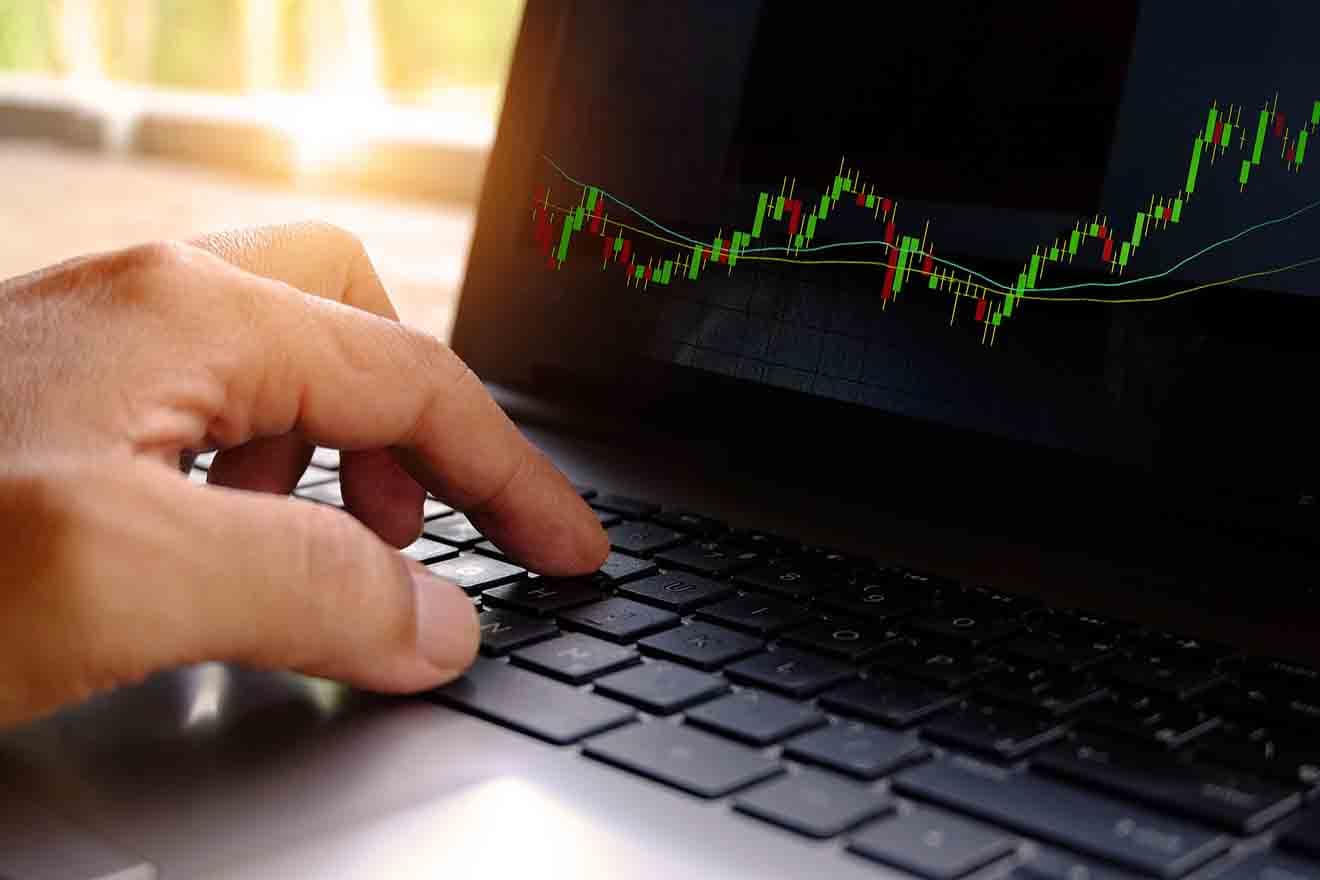
税制適格ストックオプションとは、企業が役員や従業員に付与できる自社株式の購入制度です。通常のストックオプションとは異なり、権利行使時の課税が免除されることで、税負担を軽減し、インセンティブ効果を高める特徴があります。
本記事では、税制適格ストックオプションの基本的な仕組みから、税制非適格ストックオプションや有償ストックオプションとの違い、そして令和6年度税制改正による新たな要件などを実務に即して解説します。
目次
税制適格ストックオプションとは
税制適格ストックオプションとは、ストックオプションのうち一定の要件を満たして税制優遇を受けられる制度です。
ストックオプションは、役員や従業員が将来、あらかじめ決められた価格で自社の株式を購入できる権利のことです。従業員の業績向上や企業価値向上へのモチベーションを高めるインセンティブとして、多くの企業が活用しています。
通常の無償ストックオプションは、権利行使時に時価と権利行使価額との差額が給与所得とみなされ課税対象となりますが、税制適格ストックオプションの場合、権利行使時には課税されないという大きな特徴があります。ただし、取得した株式を売却する際には、売却益に対して20.315%の譲渡所得税が課されます。
このように、税制適格ストックオプションは、適切な要件を満たすことで従業員と企業の双方にメリットのある制度として機能しています。
【関連記事】
ストックオプションとは? 制度の仕組みやメリット・デメリットを分かりやすく解説
税制非適格ストックオプションとの違い
税制非適格ストックオプションとは、税制適格ストックオプションの要件を満たしていない無償ストックオプションを指します。この2つの最も大きな違いは、課税タイミングにあります。
税制非適格ストックオプションにおいては、権利行使時に時価と権利行使価格の差額に対して最大55%(復興特別所得税を除く)の課税が発生します。さらに、株式売却時には税制適格ストックオプションと同様に20.315%の譲渡所得税が課されます。
このように2回にわたる課税が発生するため、税制非適格ストックオプションは税制適格ストックオプションと比べて、手取り額が大幅に少なくなる可能性があります。
有償ストックオプションとの違い
有償ストックオプションは、役員や従業員が発行価格を支払って新株予約権を取得する制度です。無償で権利付与される税制適格ストックオプションとは異なり、初期費用の負担が発生することから「有償」と呼ばれています。
ただし、有償ストックオプションには独自のメリットもあります。費用を支払って株式取得することから金融商品として扱われるため、権利行使時には課税されません。ただし、株式売却時には譲渡所得税が発生します。
税制適格ストックオプションのメリット
企業がストックオプションを取り入れる際に「税制適格ストックオプション」を採用することで、役員や従業員側が得られるメリットを2つ説明します。
- 税金の負担を減らせる
- 確定申告の計算が簡単
ストックオプションは従業員へのインセンティブとしても機能するため、税負担の軽減や確定申告の簡素化は、制度の魅力を高めるうえで重要な要素といえます。
税金の負担を減らせる
税制適格ストックオプションは、税制面で大きなメリットがある制度です。
税制非適格ストックオプションは権利行使時に時価と権利行使価額との差額が給与所得として扱われるため、権利行使時と株式譲渡時の2回にわたって課税が発生します。特に権利行使時には復興特別所得税を抜いても最大55%という高い税率が課税される可能性があります。
しかし税制適格ストックオプションなら、課税されるのは株式を売却して利益が出たときの1回のみで、税率は20.315%です。税金の負担を減らすことは、従業員の実質的な利益やインセンティブとしての魅力も高めているといえます。
【関連記事】
ストックオプションには税金がいつかかる?計算方法や信託型の注意点を紹介
確定申告の計算が簡単
税制適格ストックオプションで取得した株式を売却した際は、譲渡益が発生した場合に確定申告が必要となります。もっとも、所得金額の計算方法はシンプルなため、計算や申告の手間は少なく済むでしょう。
申告に必要な所得金額の計算式は以下のとおりです。ここで算出される所得金額に対して、譲渡所得税(20.315%)が課税されます。
所得金額 =(売却価格 - 権利行使価格)× 売却株数
また、確定申告には以下4つの書類が必要です。
- 申告書第一表
- 申告書第二表
- 申告書第三表(分離課税用)
- 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
税制適格ストックオプションでは、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(特定権利行使株式分及び特定投資株式分がある場合)を使用しましょう。
ストックオプション税制の適用要件
税制適格ストックオプションの制度は、以下の要件を満たすことで適用されます。
なお、2024年度(令和6年度)の税制改正により見直しが図られている要件もあります。ただし、この見直しによる経過措置は2024年12月31日をもって終了している点に注意しましょう。
出典:経済産業省「ストックオプション税制」
付与対象者の範囲
税制適格ストックオプションの付与対象者は「会社およびその子会社の取締役・執行役・使用人であること」と定められています。社外の監査役や大口株主およびその特別関係者は除かれるため、オーナー社長は付与対象者に含まれません。
ただし「一定の要件を満たす社外の高度人材」には付与が認められています。具体的には、スタートアップ企業の成長に貢献するプログラマーやエンジニア、弁護士、会計士といった国家資格保有者です。
令和6年度税制改正では上図のとおり、ストックオプション税制の対象となる社外高度人材の範囲が拡充されています。新たに、国家資格保有者などに求められる実務経験年数の要件を削除し、非上場企業の役員経験者や教授および准教授が追加されているのが特徴です。
権利行使期間
権利行使期間については「付与決議日後2年を経過した日から付与決議日後10年を経過する日まで」と明確に定められています。この期間内に権利行使しない場合は、ストックオプションの権利自体が消失してしまうため注意しましょう。
なお、令和5年度の改正時点で、設立後5年未満の非上場企業の場合は「付与決議日後2年を経過した日から付与決議日後15年を経過する日まで」と期間が延長されています。スタートアップ企業で働いている場合は期限が長い可能性があるため、よく確認しましょう。
権利行使価額
税制適格ストックオプションを適用するには、権利行使価額の要件も満たす必要があります。定められている要件は「権利行使価額が契約締結時の株式の価額相当額以上」です
例えば、契約締結時の時価が1,000円である場合、権利行使価額は1,000円以上で設定しなければなりません。インセンティブ効果で株価上昇を狙うのが企業側の目的であるため、最初から時価よりも低い金額に設定することはできないと覚えておきましょう。
権利行使価額の上限
権利行使価額は、年間合計1,200万円と上限が定められています。
令和6年度税制改正では、スタートアップ企業の人材獲得力の向上を目的に、一定の企業が付与する分については限度額が引き上げられています。ただし、このメリットを享受するには、2024年12月31日までに税制改正を反映した契約内容に変更した場合のみである点に注意しましょう。
会社区分と年間の権利行使価額の上限は、以下のとおりです。
| 会社区分 | 年間の権利行使価額の上限 |
|---|---|
| 設立5年未満の株式会社 | 2400万円 |
| 設立5~20年未満の株式会社 | 3600万円(非上場) |
| 3600万円(上場後5年未満) | |
| 上記を除く株式会社 | 1200万円 |
企業の担当者は、権利行使限度額を超えないように年間を通して注意しましょう。万が一、限度額を超えてしまうと、そのとき行使した分は全額控除や税制優遇が適用されなくなってしまいます。
譲渡の禁止
ストックオプションは、特別なルールが設けられていない場合、配偶者や親族などへ譲渡できます。しかし、税制適格ストックオプションの場合は異なります。租税特別措置法でも譲渡が禁止されているため、一般的な株式の仕組みと混同しないよう注意しましょう。
株式の管理
ストックオプションによって権利行使して取得した株式は、一般的に証券会社などの金融取引業者に保管を委託します。
令和6年度税制改正では、2024年12月31日までに税制改正を反映した契約内容に変更した場合は、従来の保管委託に代わる方法として、発行会社での管理が可能となりました。
税制適格ストックオプションの会計処理上の注意点
これまで、非上場企業におけるストックオプションの発行においては、会計処理は不要とされていました。理由としては、権利行使価額と株価が同額とみなされていたためです。
しかし、2023年7月に国税庁が非上場企業における「純資産額方式」や「配当還元方式」などの手法を用いた評価について「1株あたりの価額」とみなすと明示しました。これを、セーフハーバールールといいます。
このセーフハーバールールによって権利行使価額を決める場合、DCF法などを用いて算定した株価との間に差額が生じる可能性があります。この差額については、会計上は株式報酬費用として認識し、対象期間で按分計上する必要性がでてきます。
ただし、IPO準備中の企業の場合はその限りではありません。上場を条件に権利行使できるケースが存在するなど、ストックオプションを発行した時点では行使期間が決まらない場合もあります。このような場合は、株式報酬費用として発行時に全額を一括計上する場合もあると覚えておきましょう。
【関連記事】
IPO(株式上場)準備とは?企業が対応すべきスケジュールやタスクを解説
まとめ
税制適格ストックオプションは、自社株の購入権利を役員や従業員へ付与する制度です。一定の要件を満たすことで権利行使時の課税が免除されるなど、税負担を軽減できる点がメリットといえます。適用要件については税制改正により見直しが図られているポイントもあるため、よく確認してください。
役員や従業員に自社株を取得してもらうことで、株価の成長を期待したい企業は、税制適格ストックオプション導入の検討をおすすめします。IPOを目指す企業にとっても、従業員のモチベーション向上に効果的な制度といえるでしょう。
freeeで内部統制の整備をスムーズに
IPOは、スモールビジネスが『世界の主役』になっていくためのスタート地点だと考えています。
IPOに向けた準備を進めていくにあたり、必要になってくる内部統制。自社において以下のうち1つでも該当する場合は改善が必要です。
- バックオフィス系の全てのシステムにアクセス権限設定を実施していない
- 承認なく営業が単独で受注・請求処理を行うことができる
- 仕入計上の根拠となる書類が明確になっていない
freee会計のエンタープライズプランは内部統制に対応した機能が揃っており、効率的に内部統制の整備が進められます。
内部統制対応機能
- 不正防止(アクセスコントロール)のための、特定IPアドレスのみのアクセス制限
- 整合性担保(インプットコントロール)のための、稟議、見積・請求書発行、支払依頼などのワークフローを用意
- 発見的措置(モニタリング)のための、仕訳変更・承認履歴、ユーザー情報更新・権限変更履歴などアクセス記録
- 国際保証業務基準3402(ISAE3402)に準拠した「SOC1 Type2 報告書」を受領
詳しい情報は、内部統制機能のページをご確認ください。
導入実績と専門性の高い支援
2020年上半期、freeeを利用したマザーズ上場企業は32.1%。freeeは多くの上場企業・IPO準備企業・成長企業に導入されています。
また、freeeではIPOを支援すべく、内部統制に関する各種ツールやIPO支援機関との連携を進めています。
内部統制を支援するツール・連携機能
IPOに向けた準備をお考えの際は、freeeの活用をご検討ください。
よくある質問
ストックオプションの税制適格・非適格の違いは?
どちらも無償ストックオプションに分類されます。ただし、税制非適格ストックオプションは権利行使時にも課税される点に注意が必要です。
詳しくは記事内「税制非適格ストックオプションとの違い」で解説しています。
税制適格ストックオプションは監査役に付与できる?
税制適格ストックオプションの付与対象者は「会社およびその子会社の取締役・執行役・使用人であること」と定められています。そのため、社外の監査役へは付与できません。
詳しくは記事内「付与対象者の範囲」をご覧ください。
監修 前田 昂平(まえだ こうへい)
2013年公認会計士試験合格後、新日本有限責任監査法人に入所し、法定監査やIPO支援業務に従事。2018年より会計事務所で法人・個人への税務顧問業務に従事。2020年9月より非営利法人専門の監査法人で公益法人・一般法人の会計監査、コンサルティング業務に従事。2022年9月に独立開業し現在に至る。