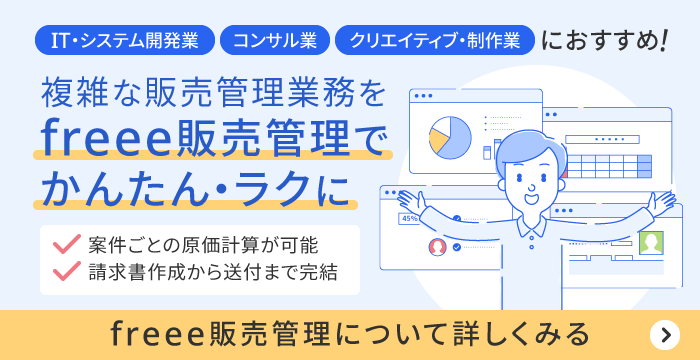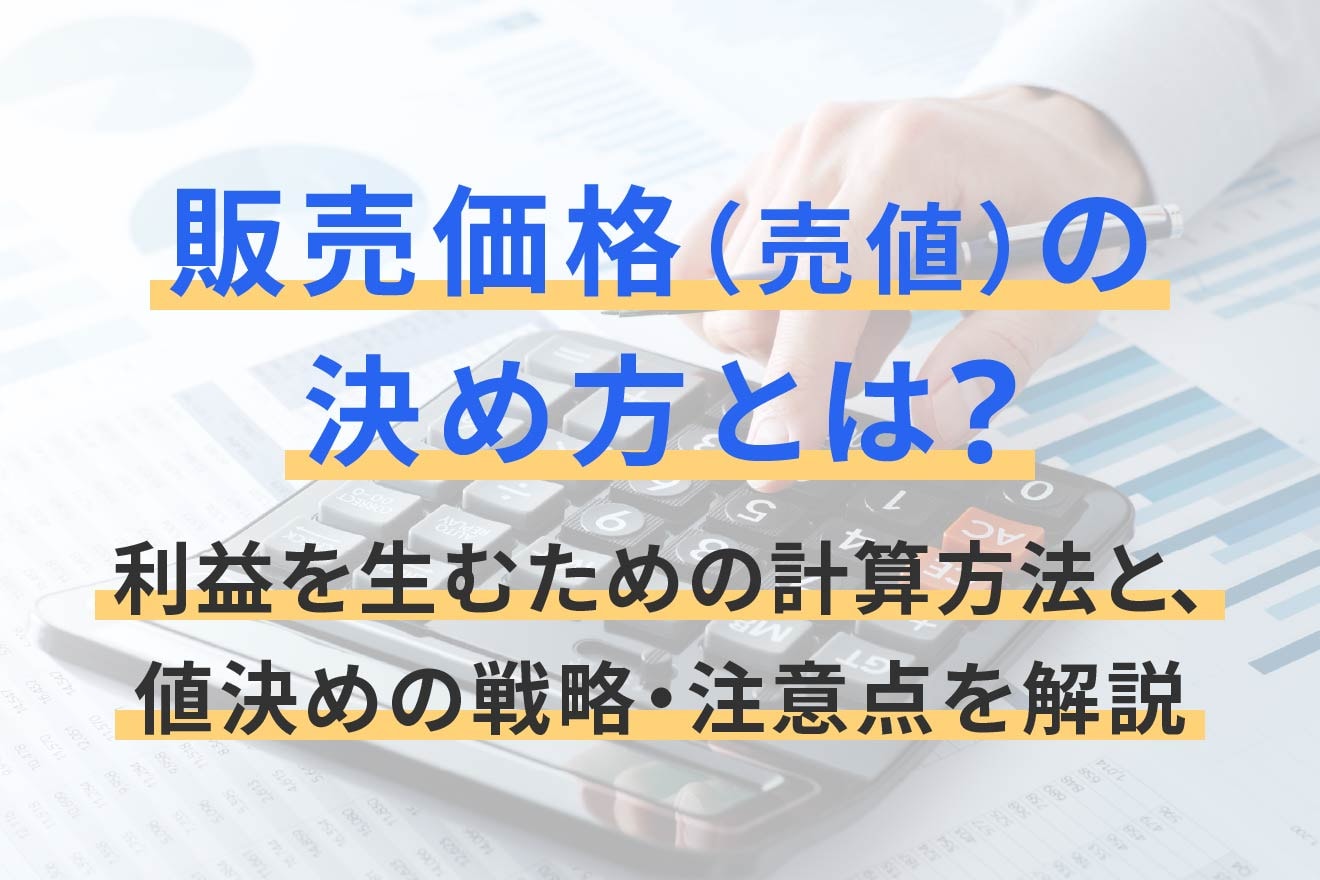
販売価格とは、商品やサービスを販売する際の値段のことです。適切な価格設定は、利益の確保やブランドイメージの向上、事業の長期的な安定化に直結します。
本記事では、販売価格の一般的な決め方から顧客心理を活用した価格設定の戦略的アプローチまでわかりやすく解説します。根拠のある価格設定方法を知りたい方や、新製品の利益最大化を図りたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
販売価格(売値)とは
販売価格とは、企業が商品やサービスを市場で販売する際に設定する値段(売値)のことです。企業の売上や利益に直結するため、ビジネスにおいて極めて重要な要素といえます。
販売価格は、商品の仕入れ値や製造にかかった原価に適切な利益を上乗せしたり、同業他社の価格や市場の相場、競争状況などを総合的に考慮しつつ決定したりします。そのため、「この金額で売りたい」といった希望や曖昧な理由だけで決めるものではありません。
なお、販売価格は基本的に以下の構造で成り立っています。
- 原価 + 諸費用 + 利益 = 販売価格
原価とは商品を作ったり仕入れたりするための費用のことで、利益は企業が事業を継続しながら成長していくために必要な「儲け」のことです。諸費用には、事務所の家賃、配送費、通信料などの「経費」や広告宣伝費などの「販売管理費」が含まれます。
販売価格の構成要素
適切な販売価格を設定するには、まずその構成要素を正しく理解することが重要です。主に販売価格を構成する「原価」と「利益」をそれぞれ詳しく把握することで、根拠のある価格設定につながります。
原価とは
原価とは、商品やサービスを提供するために直接的・間接的にかかった費用を指します。原価を構成するのは、大きく「材料費」「労務費」「製造経費」の3点です。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 材料費 | 商品を作る過程で使用する原材料や部品の費用 |
| 労務費 | 製造に関わる従業員の人件費(給与や賞与)や福利厚生費など |
| 製造経費 | 設備の減価償却費や光熱費、修繕費など |
原価率は、以下の計算式で求めることができます。
- 原価 ÷ 売上 × 100 = 原価率(%)
原価が500円で販売価格が1,000円の製品の場合、原価率は50%です。業界によって適正な原価率は異なるため、自社の業界に合わせた目標原価率を設定しましょう。
【関連記事】
原価率とは?計算方法や業種別の目安、販売価格の決め方について徹底解説
利益とは
利益とは、販売価格から原価を差し引いて手元に残った金額のことです。企業が事業活動によって獲得する「儲け」を意味します。企業の持続的な成長に欠かせない原資となるのが利益です。
利益を考える際には、「目標とする利益額」と「利益率」の両方を考慮しましょう。利益額は具体的な金額ベースでの目標であり、事業計画や投資計画に直接関わります。一方の利益率は売上に対する利益の割合を示し、事業の収益性を測る指標として活用されます。
利益率を求める計算式は以下です。
- 利益 ÷ 売上 × 100 = 利益率(%)
たとえば、販売価格が1,000円の商品があったとします。販売して300円の利益が出たとすると、その商品の利益率は30%になります。
売上に対する構成要素である利益率と原価率は表裏一体の関係にあり、原価率が高いほど利益率は低くなります。
販売価格の基本的な決め方
販売価格を設定する方法は一つではありません。企業の事業特性や商品の性質、市場環境の状況などを考慮して、適切なアプローチを検討しましょう。
以下では、一般的な販売価格の決め方である「コストプラス法」「マーケットアプローチ」「バリューベースアプローチ」について解説します。
コストプラス法(原価基準方式)
コストプラス法は、商品の原価を基準に価格を設定するシンプルな方法です。原価に企業が望む利益を上乗せし、販売価格を決定します。計算式は以下のとおりです。
- 原価 +(原価 × 利益率) = 販売価格
コストプラス法のメリットは、確実に利益を確保できること。また、計算がシンプルでわかりやすく、価格設定にかかる時間や労力を抑えられる点でも有用です。
デメリットとしては、市場の需要や競合他社の価格を考慮しないため、顧客が支払いたいと思う価格や市場相場から外れてしまうリスクが挙げられます。「価格が高すぎて売れない」「安すぎてもっと高く売れる機会を逃してしまう」などの恐れがあると覚えておきましょう。
販売価格シミュレーション
原価1,000円の商品に20%の利益率を設定した場合の計算例を紹介します。
- 1,000 +(1,000 × 20%)= 1,200円
この場合、商品を1,200円で販売することで、原価1,000円に対して200円の利益を確保できます。
マーケットアプローチ(市場追随方式)
マーケットアプローチは、競合他社や市場全体の価格相場を調査し、それを基準として自社の価格を設定する方法です。市場の実情に合わせた現実的な価格設定が可能になります。
メリットは、競争力のある価格を設定しやすい点です。競合他社の価格情報は比較的入手しやすく、価格調査の手間もそれほどかかりません。一方、価格競争に陥りやすいのがこの方法のデメリット。自社商品が持つ独自の価値やブランド力を価格に反映させにくく、差別化が困難になる可能性も考慮しなければなりません。
販売価格シミュレーション
競合A社が1,450円、B社が1,500円、C社が1,600円、D社が1,650円で類似商品を販売している市場での販売価格を考えてみます。
| 会社 | 金額 |
|---|---|
| A社 | 1,450円 |
| B社 | 1,500円 |
| C社 | 1,600円 |
| D社 | 1,650円 |
4社の価格から、市場平均は1,550円とわかります。この場合、市場平均と同程度の1,550円で設定するという選択肢のほかに、「やや安い1,400円で価格優位性を打ち出す」「品質に自信があるので1,700円で付加価値を訴求する」といった判断もできるでしょう。
バリューベースプライシング(価値基準方式)
バリューベースアプローチは、顧客が商品やサービスに対して感じる価値をベースに価格を検討する方法です。顧客がその商品に対して「いくら支払ってもよいと考えているか」を重視します。
この方法は、顧客が価値を感じてくれるほど高い利益率を確保できる可能性があります。原価にかかわらず販売価格を設定できるため、ブランド価値の向上にもつながります。
一方で、顧客が感じる価値を正確に測定するのが難しい点はデメリットです。価値は主観的で個人差があるため、定量化が困難です。また、顧客に対して価値を伝えなければならないため、そのためのマーケティングやブランディング、営業活動が必須となります。
販売価格シミュレーション
独自の技術を用いた高機能な商品や、手厚いアフターサポートを提供するサービスで考えてみましょう。
たとえば、一般的な商品の市場価格が2,000円の分野で、独自の省エネ技術により電気代を年間5,000円節約できる商品があるとします。顧客にとって年間5,000円の節約は大きな価値であるため、商品価格を3,000円や4,000円に設定しても十分な価値を提供できると判断できます。
利益を伸ばすための価格戦略
販売価格を決めるプロセスにはさまざまな方法がありますが、利益を追求するには、基本的な決め方に加えて「顧客の購買心理を活用した戦略的なアプローチ」が重要です。購買心理に働きかける価格戦略について確認しておきましょう。
心理的価格設定
心理的価格設定とは、顧客の価格に対する心理的な反応を考慮して価格を決定する手法です。顧客は価格に対して単なる数値ではなく、心理的要因によって「お得」「高級」「適正」といった印象を抱いています。
心理的価格設定にはいくつか種類があります。
心理的価格設定の例
- 端数価格:980円のように端数をつけて実際の価格以上に安さを演出する
- 名声価格:高く価格を設定することで品質や価値の高さを印象づける
- 抱き合わせ価格:複数の商品をセットにして個別購入よりもお得感を演出する
- 慣習価格:長年にわたって市場に定着した価格水準に合わせる
- 均一価格:商品の種類にかかわらず同一価格で販売する
プライスライン設定
プライスライン設定は別名「松竹梅の法則」とも呼ばれ、3段階の価格帯を用意して顧客の選択行動をコントロールする手法です。複数の選択肢がある際に極端な判断を避け、中間を選ぶ「極端の回避性」という心理的特性を利用しています。
「980円」「1,480円」「1,980円」といった3つの価格帯を用意したとします。この場合、多くの顧客は最安値の980円だと品質面で不安を感じ、最高値の1,980円は高すぎると判断します。その結果、中間の1,480円が選ばれやすくなるのです。
プライスライン設定を効果的に活用するには、売りたい商品を中間価格帯に配置するのがポイントです。また、各価格帯の商品には明確な差別化要素を設け、顧客が価格差に納得できるような価値の違いを示すとよいでしょう。
販売価格の決め方に関する注意点
適切な販売価格を設定するには、計算式や手法だけでなく、注意点も押さえておく必要があります。見落としがちなポイントや落とし穴をあらかじめ把握しておき、実際の価格設定に役立てましょう。
原価(コスト)を正確に把握する
販売価格が原価を上回らなければ、利益が生まれません。注意すべきは、「隠れコスト」の存在です。プライスライン設定は別名「松竹梅の法則」とも呼ばれ、3段階の価格帯を用意して顧客の選択行動をコントロールする手法です。
具体的には、製造や販売に関わる人件費、商品を包装する梱包材費、顧客への配送料、商品の広告宣伝費、事業運営に必要なオフィスの家賃や光熱費などがあります。また、在庫管理のための費用や返品処理にかかるコスト、決済手数料なども見落としがちな要素です。
価格設定時にはこれらすべてのコストを洗い出し、それぞれの商品にどれだけの費用かかっているのかを正確に計算するようにしましょう。
顧客が感じる「価値」を見極める
価格は単なる数字ではなく、顧客がその商品・サービスに対して「支払ってもいい」と感じる価値の表れです。この価値の見極めが、価格設定の成否を左右します。
重要なのは、原価の高低と顧客が感じる価値は「必ずしも比例しない」ということです。原価が安くても、顧客にとって価値の高い商品であれば高い価格設定が可能ですが、原価が高くても顧客が価値を感じなければ、高い価格では売れません。
特に専門的で技術力の高い商品は、顧客が価格から品質を推測する傾向があります。あまりに安い価格を設定すると「品質が悪いのではないか」という不安を与えてしまい、かえって売れなくなる可能性があるため注意が必要です。
競合の価格を「参考にしすぎない」
競合調査は価格設定において不可欠ですが、調査結果を鵜呑みにして競合に安易に追随するのは避けるべきです。
特に気をつけたいリスクが、価格競争へ巻き込まれることです。競合が価格を下げたという理由だけで自社も価格を下げると、「利益の削り合い」が始まります。価格競争が始まると抜け出すのは困難で、業界全体の収益性が悪化する恐れもあります。
競合価格を調査する際は単純な金額比較だけでなく、「なぜその価格なのか」を分析することが重要です。また、自社の販売価格設定を行う際は、差別化要因を価格に反映させることで価格競争を回避しやすくなります。
ブランドイメージと一貫性を持たせる
価格設定はブランドイメージに影響します。価格とブランドイメージが矛盾すると、顧客の信頼を失う可能性があるため注意が必要です。
たとえば、セールや割引を頻繁に行っていると「安くないと売れない店」といったイメージが定着してしまいます。このイメージが定着すると通常価格では商品が売れにくくなり、常に値下げを検討しなければなりません。かといって高品質な素材や丁寧な手仕事を売りにする商品に安すぎる価格を設定すると、顧客に「本当に良いものなのか」「何か問題があるのではないか」という不信感を与えてしまいます。
ブランドポジショニングと価格戦略を一致させることは、顧客の期待と実際の商品・サービスとの整合性を保ち、長期的な信頼関係を築くことにつながります。
「一度決めたら終わり」にしない
価格設定は、一度決めれば永続的に有効というわけではありません。市場環境は常に変化しており、それに応じて価格も定期的に見直す必要があります。
市場の状況や仕入れ値、顧客のニーズは時間とともに変化するものです。原材料費の高騰や為替変動、競合の市場への参入、技術革新など、価格に影響を与える要因も数多く存在します。
定期的な価格見直しでは、データに基づいた判断が求められます。どの商品がどれくらい売れているか、どれくらいの利益が出ているか、顧客の反応はどうかなど、定量的な情報を収集・分析し、価格改定の判断材料として活用することが欠かせません。
まとめ
販売価格とは、企業の利益確保や持続的な成長に欠かせない重要な要素です。適切な価格設定を行うために、まずは原価と利益といった構成要素を正確に把握し、基本的な手法から最適な金額を考えていきましょう。
利益を追求したい場合は、「顧客の購買心理を活用した戦略的なアプローチ」が重要です。心理的価格設定やプライスライン設定を活用し、顧客の購買意欲を高めましょう。ただし、原価の正確な把握や顧客価値の見極め、競合との適切な距離感など注意点も多くあります。顧客が納得する適正価格を追求するには、設定した価格を定期的に見直しながら、自社の事業特性に合った価格戦略を講じることが大切です。
よくある質問
販売価格とは?
販売価格とは、企業が商品やサービスを販売する際の売値です。商品の仕入れ値や製造にかかった原価に利益を上乗せするほか、同業他社の価格や市場相場などを考慮して決定されます。
詳しくは、記事内の「販売価格(売値)とは」をご覧ください。
販売価格の決め方は?
販売価格の基本的な決め方として「コストプラス法(原価基準方式)」「マーケットアプローチ(市場追随方式)」「バリューベースプライシング(価値基準方式)」などがあります。どの方法が適しているかは、事業特性や商品の性質などを考慮しながら検討しましょう。
詳しくは、記事内の「販売価格の基本的な決め方」をご覧ください。
利益を伸ばすにはどうしたらいい?
利益を追求するには、基本的な決め方に加えて、顧客の購買心理を踏まえた価格設定が有効です。顧客の心理的な反応に応じて「お得感」や「高級感」を演出しましょう。
詳しくは、記事内の「利益を伸ばすための価格戦略」で解説しています。