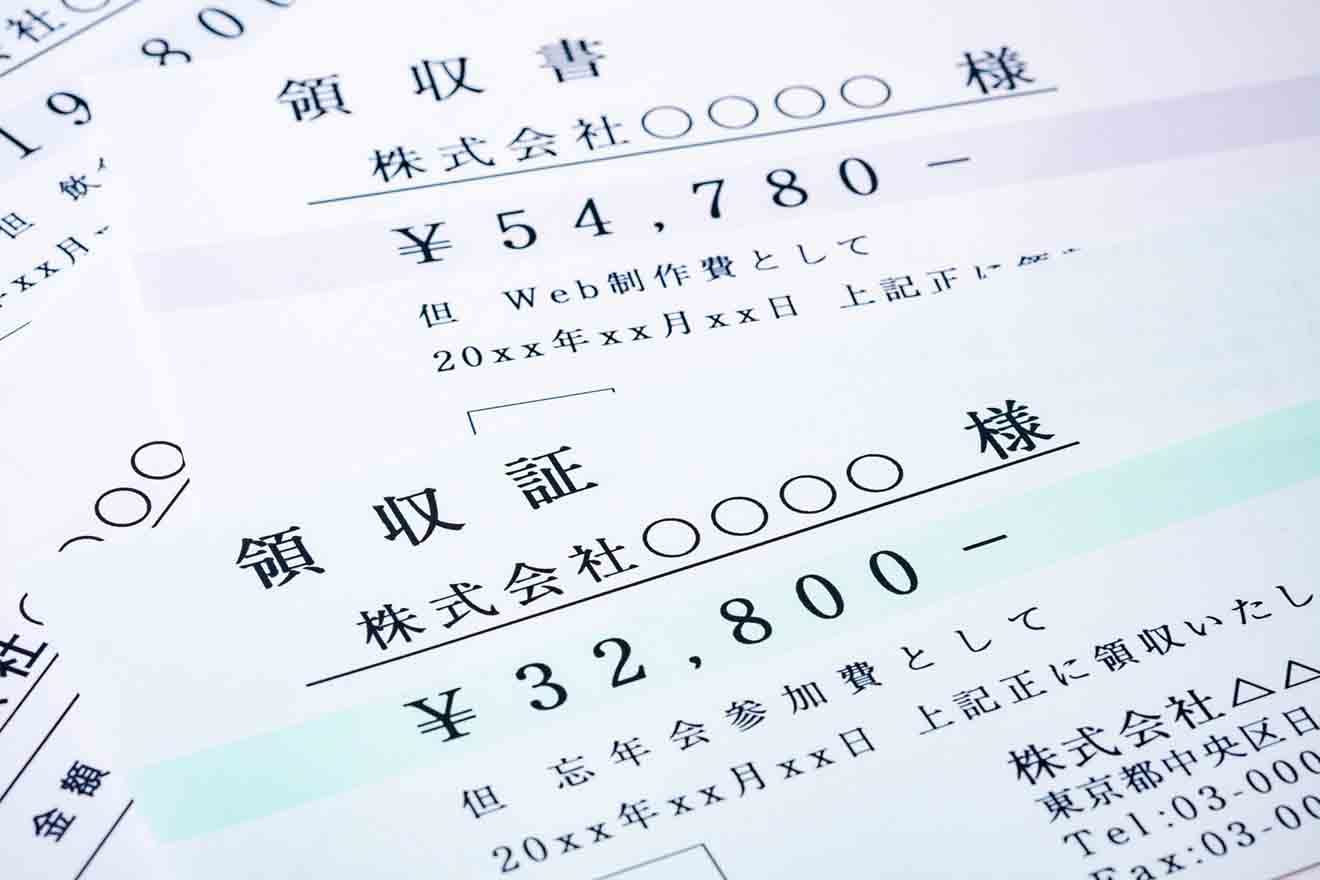
領収書は法人、個人事業主問わず保管が義務付けられています。保管期間などのルールが守られていない場合は、税務上のトラブルなどが発生する恐れがあるため注意が必要です。
本記事では、法人の領収書の保管期間、個人事業主の領収書の保管期間、領収書の保管方法と守らなかった場合の影響、領収書の保管にあたって注意すべきポイントを解説します。
【関連記事】
帳簿や領収書等の保存義務
請求書の保管期間とは?保管方法や注意すべきポイントを解説
請求書の管理・保管方法は?効率的なやり方を解説
目次
- 法人の領収書の保管期間
- 原則の保管期間
- 繰越欠損金の控除を受ける場合の保管期間
- 領収書を発行した際の控えの保管期間
- 個人事業主の領収書の保管期間
- 青色申告の場合
- 白色申告の場合
- 消費税の仕入税額控除を受ける場合
- 領収書の保管方法
- 紙の領収書の保管方法
- 電子データの領収書の保管方法
- 領収書の保管期間を守らなかった場合の影響
- 消費税額を控除できない
- 罰則や追徴課税を受ける恐れがある
- 領収書の保管にあたり注意すべきポイント
- インボイス制度の導入によって領収書の保管ルールが変更している
- 領収書のデータ保管には電子帳簿保存法に則る必要がある
- 紙の領収書はコピーではなく原本を保管する
- まとめ
- 面倒な経費精算を秒速で終わらせる方法
- よくある質問
法人の領収書の保管期間
法人の領収書の保管期間について、原則と異なるケースおよび領収書の控えの保管について説明します。
原則の保管期間
法人の領収書の保管期間は、原則として7年間です。この保管期間は、法人税法で定められています。
この7年間の保管義務は、領収書を受け取った日(領収書が発行された日)から7年間ではありません。領収書を受け取った事業年度の確定申告書提出期限の翌日から7年間で計算します。原則として事業年度末から2ヶ月後が、法人税の確定申告書の提出期限です。
たとえば、事業年度末が2025年3月31日である法人の場合は以下のようになります。
- 領収書の保管期間は法人税の申告期限:2030年5月31日
- 領収書の保管期間:2032年5月31日
繰越欠損金の控除を受ける場合の保管期間
繰越欠損金の控除を受ける場合、領収書の保管期間は10年になります。
繰越欠損金の控除とは、税務申告を行う年度の過去10年以内に生じた赤字額について利益から差し引くことができる制度のことです。赤字額の根拠を示す書類として、対象年度の領収書が必要になります。
領収書を発行した際の控えの保管期間
領収書を発行する際は、控えが発行されることが一般的です。領収書の発行側は、この領収書の控えを所定の方法で管理したうえで保存する必要があります。
領収書の控えも領収書と同様に、基本的に7年間保存する義務があります。期間は領収書の発行日から7年ではなく、事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年です。
個人事業主の領収書の保管期間
個人事業主における領収書の保管期間は所得税法で定められていますが、青色申告と白色申告で保管期間が異なることに注意が必要です。
保管期間は法人の場合と同様、確定申告提出期限の翌日から計算します。青色申告と白色申告、それぞれの場合について解説します。
青色申告の場合
青色申告の場合、領収書保管期間は原則として7年です。ただし、申告した前々年の所得が300万円以下であれば、保管期間は5年になります。
白色申告の場合
白色申告の場合、領収書保管期間は原則として5年となります。ただし、帳簿の保管期間は青色申告と同様に7年間必要になりますので、注意が必要です。
消費税の仕入税額控除を受ける場合
消費税法で、仕入れに関する領収書は7年間保存することが義務付けられています。
消費税の仕入税額控除とは、仕入れや流通の段階で消費税が何重にも課税されるのを防ぐための制度です。この制度によって、納税者は仕入れにかかった消費税を納付すべき消費税から控除することができます。消費税の仕入税額控除については、別記事「消費税の仕入税額控除とは?基礎知識とインボイス制度での変更点をわかりやすく解説」もあわせてご覧ください。
前述のとおり、白色申告や一部の青色申告者は、所得税法で領収書の保存期間が5年と定められています。しかし、複数の法令における条件に当てはまる場合は、保存期間が長い法令の定めが優先されます。そのため、仕入税額控除を受ける場合は、領収書を必ず7年間保管しなければなりません。
なお、仕入税額控除の適用を受ける場合は帳簿や請求書、領収書などについて7年間にわたる保存義務が生じます。6年目と7年目は、帳簿または請求書(もしくは領収書など)のどちらか一方の保存を保存すれば良いとされています。
保管しておくべき請求書や領収書がないと、仕入税額控除が受けられない可能性もあります。役務の性質上、領収書が発行されないケースなど、やむを得ないと認められる場合を除き、基本的には領収書には保存義務があると考えましょう。
領収書の保管方法
領収書の種類には紙と電子データがありますが、それぞれの領収書の適切な保管方法を説明します。
紙の領収書の保管方法
紙の領収書を保存する場合、紙のまま保存する方法と、電子データにして保存する方法があります。
紙で保存する場合には以下のような方法で紛失を防ぎ、いつの領収書かがわかるように保管します。
- 台紙に貼り付ける
- 封筒や箱で小分けにする
- ファイリングする
電子データで保存する場合は紙の領収書をスキャン、もしくはスマートフォンなどで撮影して電子データにしたうえで保存します。電子帳簿保存法に則っていれば、原本は破棄して構いません。
以上のように、紙のまま保存する場合も電子化して保存する場合も、会計帳簿と対応して確認できるようにすることが重要です。電子帳簿保存法や請求書の原本の保存については、以下の記事もあわせてご覧ください。
【関連記事】
電子帳簿保存法とは?対象書類や保存要件・改正内容についてわかりやすく解説
【関連記事】
請求書の保存は原本(原紙)でないとダメなのか
また、適格簡易請求書に必要な事項が記載されていれば、インボイス制度上はレシートや領収書でも適格簡易請求書として扱えます。手書きのものであっても可能です。詳しくは以下の記事で解説しています。
【関連記事】
適格簡易請求書(簡易インボイス)とは?レシートや領収書の扱いも解説
電子データの領収書の保管方法
電子データの領収書を電子保存する場合には、社内のファイルサーバーやクラウドストレージ、会計システムなどを利用します。
領収書の電子保存にあたっては、電子帳簿保存法によって以下の保存要件が定められています。
- 真実性の確保:保存された電子データが改ざんされていないことを示す
- 可視性の確保:保存されたデータを検索できるようにする
なお、電子取引により電子データを保存する場合と、紙をスキャナで取り込んで電子データとして保存する場合とでは保存要件が異なりますので、注意してください。
保存要件については「電子帳簿保存法とは?対象書類や保存要件・改正内容についてわかりやすく解説」で解説しています。
領収書の保管期間を守らなかった場合の影響
領収書の保管期間を守らなかった場合に発生する、主な影響について解説します。
消費税額を控除できない
領収書が適格請求書に該当するものであって正しく保存されていない場合、消費税申告を一般課税(本則課税)で行っている事業者は、事業の仕入れ等で生じた金額に対する消費税額を控除できません。なお、簡易課税制度を選択している場合を除きます。
適格請求書発行事業者は消費税の課税事業者であるため、消費税の納付義務があります。適格請求書発行事業者である法人や個人事業主、副業を営む人は、消費税を納税しなければなりません。
その際の消費税額は、課税売上で受け取った消費税から仕入時に支払った消費税分を差し引いた金額を納付することになります。しかし、この仕入の消費税分を差し引くためには、2023年10月から適格請求書に該当する書類とルールに従った帳簿づけが必要となりました。
この書類に領収書も含まれるため、領収書を正しく保存していないと、本来受けられるはずの控除を受けられなくなってしまい、消費税額が増えてしまいます。
適格請求書については、以下の記事もあわせてご覧ください。
【関連記事】
適格請求書とは?書き方や保存期間、簡単に作成する方法について解説
罰則や追徴課税を受ける恐れがある
領収書が保管されていないと、税務調査が入った場合に追徴課税や罰則を受けることがあります。
税務調査では、最長で7年分さかのぼって調査されることがあります。領収書の保管期間が原則7年に設定されているのは、この調査対象の期間が関係しているのです。
そのため、7年以内の領収書が保管されていないことが税務調査によって発覚すれば、足りない分の領収書に追徴課税が発生する恐れがあります。
領収書の保管にあたり注意すべきポイント
領収書の保管にあたって注意すべき3つのポイントを解説します。
インボイス制度の導入によって領収書の保管ルールが変更している
インボイス制度の導入に伴い、3万円未満の領収書も保存が必要になりました。つまり、数百円程度の仕入額でも原則として領収書を受け取る必要があります。
中小事業者には、2023年10月1日から2029年9月30日までの期間で経過措置が設けられています。1万円未満の課税仕入れであれば、適格請求書・適格簡易請求書に該当する領収書などの保存がなくても、記載条件を満たした帳簿保存のみで仕入税額控除が適用されます。
領収書のデータ保管には電子帳簿保存法に則る必要がある
電子帳簿保存法の改正により、2024年1月以後は電子取引においてデータ保存が完全義務化されています。そのため、電子取引でやり取りをした取引書類は、要件に沿ってデータを保存しなければなりません。
メール添付などで受け取った領収書は、データのまま保存する必要があります。これを紙に印刷して保存することは電子帳簿保存法違反となるため、注意しましょう。
紙の領収書はコピーではなく原本を保管する
紙の領収書をコピーして保存する行為は、原則認められていません。そのため、スキャナでデータ化して保存しない場合は、原本を保管する必要があります。コピーを認めると改ざんや二重請求が多発する恐れがあり、正しい会計や課税が行われない恐れがあるためです。
万が一、領収書原本を紛失したり破棄してしまった場合、領収書発行から日が経っていなければ再発行できる可能性もあります。ただし、領収書の再発行は発行側(販売側)の義務ではないため、状況によっては断られるケースも考えられます。
インボイス制度では、原則的に買手側から求められたら、売手側は適格請求書(インボイス)を発行し、控えを保存しなければなりません。領収書が適格請求書に該当する場合も同様です。
万が一、適格請求書となる領収書を紛失するなどして再発行を依頼されたら、保存している控えに基づき、再発行を明示した領収書を作成することで対処できます。
なお、紙の領収書を要件に従ってスキャナでデータ化し保存している場合は、原本の破棄が可能です。
まとめ
領収書の保管は事業者にとって重要な義務ですが、適用されるルールは事業者の状況によって異なります。
近年の法改正とも関連しているため、本記事で紹介したポイントを押さえて適切に管理しましょう。
よくある質問
領収書の保管期間はどれくらいですか?
法人と個人事業主で、領収書の保管期間は異なります。法人の場合は原則7年間、個人事業主で青色申告の場合は原則7年間、白色申告の場合は原則5年間です。
詳しくは、記事内「法人の領収書の保管期間」「個人事業主の領収書の保管期間」で解説しています。
領収書の控えの保管期間は?
領収書の控えは、原則として領収書と同様の年数の保管が義務付けられています。
記事内の「法人の領収書の保管期間」「個人事業主の領収書の保管期間」で詳しく解説しています。
領収書の保管期間を守らなかったらどうなる?
該当の出費を費用計上できない、消費税額を控除できない、罰則や追徴課税のリスクが生じるなどの影響が考えられます。
詳しくは、記事内「領収書の保管期間を守らなかった場合の影響」をご覧ください。

