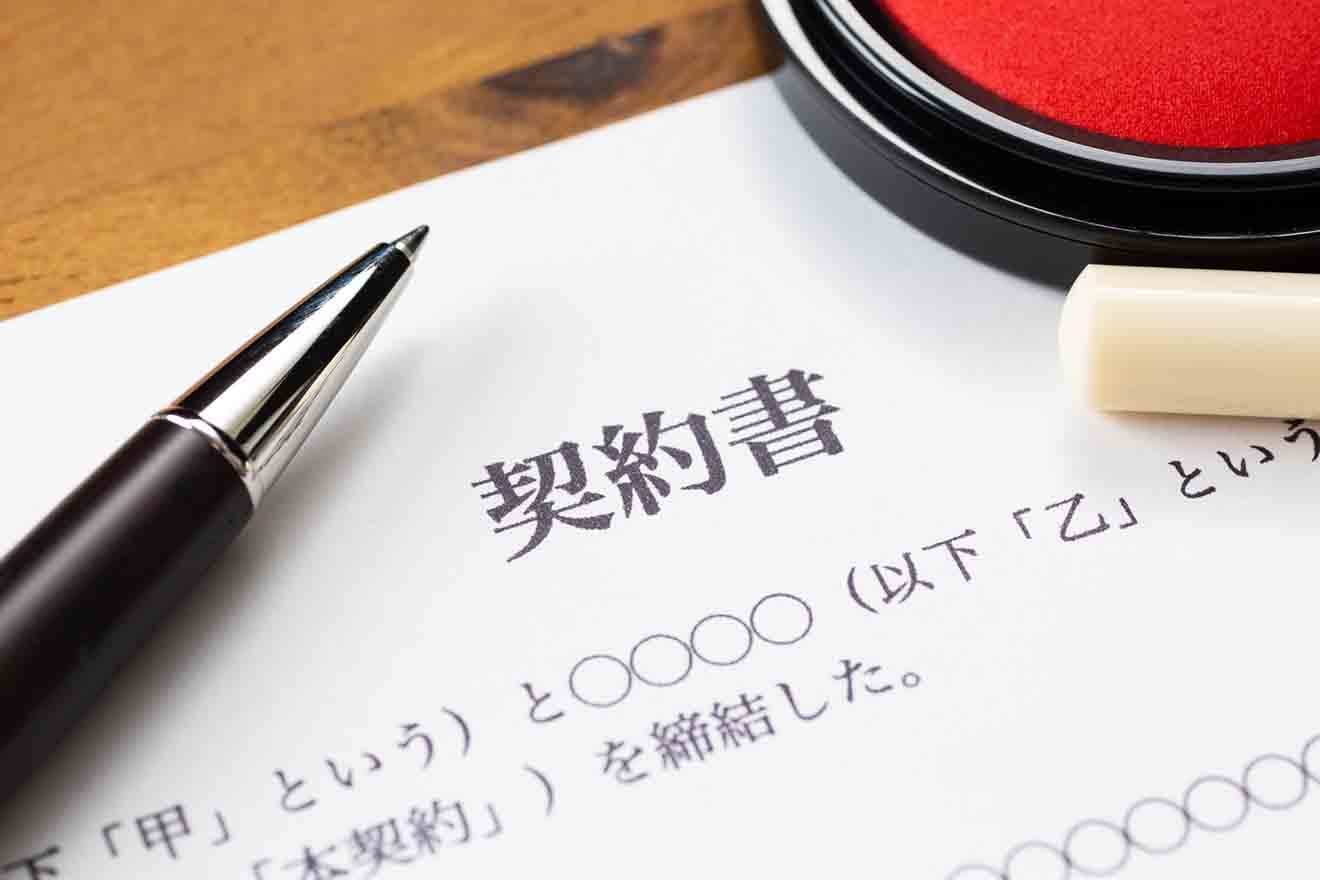
契約を締結する際、その契約書が印紙税法上の「課税文書」に該当する場合は、印紙税の納税義務が発生します。
印紙税は、契約書に適切な金額の収入印紙を貼り付けて消印を行う形で納税します。契約の種類や額に応じて収入印紙の金額が異なるため、適切に処理を行わなければ、予想外のペナルティを課せられるかもしれません。
本記事では、契約書における収入印紙の必要性や納税金額、貼り忘れてしまった場合の対処法について解説します。
目次
収入印紙とは
収入印紙とは、国が租税や手数料などを徴収するために発行している証票を指します。印紙税法に基づく経済取引に伴う書類(課税文書)の作成時や不動産登記時の登録免許税、免許の交付手数料を納める際など、さまざまな場面で使用されています。
収入印紙は1円から10万円まで31種類あり、法務局や郵便局、コンビニなどで購入可能です。ただし、コンビニでは200円以上、郵便局では5万円以上の高額な収入印紙を扱っていない場合があります。そのため、高額の収入印紙は法務局で購入しましょう。
【関連記事】
収入印紙とは?購入方法や正しい貼り方、注意点などを解説
契約書に収入印紙の貼付は必要
契約書は印紙税法上の「課税文書」に該当する場合があり、その際は印紙税の納税義務が発生します。
課税文書のなかには、不動産売買や工事請負などの契約書も含まれています。そのため、これらの契約書を作成する際は、収入印紙の貼付が必要です。
なお、印紙税の納税義務が生じるのは「課税文書の作成者」です。文書を法人名義で作成する場合は、その法人が納税義務を負うこととなります。
契約書に貼付する収入印紙の金額
契約書に貼り付ける収入印紙の金額は、契約書の種類や契約額によって異なります。
ここでは、事業内容にかかわらず発生頻度の高い契約として、不動産売買や金銭の貸し借りに関する契約を指す「第1号文書」と、請負に関する契約を指す「第2号文書」を例に挙げて解説します。
第1号文書の場合
第1号文書に該当する契約書は以下のとおりです。
- 不動産、鉱業権、試掘権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書
- 地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書
- 消費貸借に関する契約書
- 運送に関する契約書
出典:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
また、契約書に記載される契約金額に応じて発生する印紙税額は下記表のとおりとなります。ただし、「不動産の譲渡に関する契約書」については、2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成される場合は、軽減措置が適用されます。
| 契約金額 | 印紙税額 | 軽減措置が適用された印紙税額 |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 |
| 10万円以上50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円以上100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円以上500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円以上1千万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1千万円以上5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円以上1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円以上5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円以上10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円以上50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円以上 | 60万円 | 48万円 |
出典:国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」
第2号文書の場合
第2号文書に該当する契約は以下のとおりです。具体的には、請負にはプロ野球選手やプロボクサー、俳優、監督、演出家、音楽家などの役務提供における契約が含まれます。
工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
出典:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
なお、建設工事の請負に関する契約書で契約金額が一定額以上のものは、2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成される場合、第1号文書と同様に軽減措置が適用されます。
| 契約金額 | 印紙税額 | 軽減措置が適用された印紙税額 |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 | 200円 |
| 100万円以上200万円以下 | 400円 | 200円 |
| 200万円以上300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 300万円以上500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円以上1千万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1千万円以上5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円以上1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円以上5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円以上10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円以上50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円以上 | 60万円 | 48万円 |
出典:国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」
契約書に収入印紙を貼り忘れた場合の対処法
契約書をはじめ、課税文書には収入印紙の貼付が必須です。そのため、適切な金額を貼り付けていなかったり、貼付自体を怠ったりした場合はペナルティとして過怠税が課せられる可能性があります。万が一貼り忘れなどのミスに気づいたら、早急に対処する必要があります。
自発的に気付いた場合は、必要な金額の収入印紙を購入し、契約書に貼り付けて消印を行います。税務署から指摘を受けた場合は、その日から30日以内に対処しましょう。
30日以内に適切な収入印紙を貼り付けて税務署へ提出すれば、過怠税を減らせる可能性があります。仮に30日を過ぎて放置を続けた場合、「過怠税」が本来の税額よりも大きくなる恐れがある点に要注意です。
また、収入印紙の貼付方法や消印方法が正しく行われているかどうかも重要です。たとえば誤った場所に貼り付けていたり、消印を行っていなかったりする場合も過怠税を課される可能性があります。
特に、消印を行っていない場合はペナルティが厳しくなることがあります。印紙の再利用を疑われるなど、不正使用とみなされることで刑事罰の対象になりかねないため、誤った手順で処理しないように気を付けてください。
電子契約の場合は収入印紙が不要
電子契約とは、紙の契約書を使用せず、電子機器を使用して契約を締結することです。電子契約の場合、紙の文書を作成していないことから印紙税の納税義務は発生せず、収入印紙の貼付は不要とされています。収入印紙が不要とされる理由は、電子契約が印紙税法上の「課税文書の作成」に該当しないと解釈されているためです。
契約書が紙の状態で交付されない限りは課税文書に該当しないため、電子契約にて締結した際は電子データで保管します。ただし、電子契約書を印刷して交付し、書面で契約を締結した場合は印紙税が必要となるため注意しましょう。
電子契約サービスを利用すれば、収入印紙が不要であるうえに、契約書の作成から押印、管理までの一連の契約業務をオンラインで完結できます。収入印紙にかかるコストを削減し、業務効率化を図りたい場合は、電子契約サービスの利用を検討してください。
まとめ
契約書をはじめ課税文書を作成する際は、収入印紙を貼り付ける必要があります。納税金額は、契約の種類や金額に応じて異なるものと覚えておきましょう。
万が一、収入印紙の金額が足りなかったり、貼り方を間違えてしまったりした場合は、早急な対応が必要です。
税務署からの指摘から30日以上経過すると過怠税の金額が大きくなるなどのリスクが生じます。印紙税法や収入印紙の金額などの決まりを正しく理解し、安定した会社経営につなげましょう。
契約にまつわる業務を簡単にする方法
契約書の作成や押印、管理など、契約にまつわる作業は多岐に渡ります。リモートワークが普及した近年、コミュニケーションを取りづらくなってしまい、契約締結までに時間がかかってしまう場合や、押印のためだけに出社しなければいけない...なんてケースも少なくありません。
そんな契約まわりの業務を効率化させたい方には電子契約サービス「freeeサイン」がおすすめです。
freeeサインはインターネット環境さえあれば、PCやスマホで契約書作成から締結まで、契約にまつわる一連の業務を完結できます。さらに、過去の契約書類はクラウド上で保存できるので、紛失や破損の心配も解消します。
契約周りのさまざまな業務をクラウド上で完結!

契約書を簡単に作成!
契約によって書式が異なるので、一から作成すると工数がかかってしまいます。 freeeサインでは、テンプレートを登録し、必要な項目を入力フォームへ入力するだけで簡単に契約書を作成できます。
社内の承認作業がリモートで完了!
freeeサインでは、契約書の作成依頼から承認にいたるまでのコミュニケーションもオンラインで管理・完結。ワークフロー機能は承認者の設定が可能なので、既存の承認フローをそのまま電子化することができます。
文書に応じて電子サイン・電子署名の使い分けが可能!
電子契約サービスの中には、どんな文書であっても1通送信する度に100~200円程度の従量課金が発生するものも少なくありません。freeeサインでは、従量課金のない「電子サイン」と従量課金のある「電子署名」のどちらを利用するかを、文書の送信時に選択できます。
重要な契約書や、後に争いが生じる可能性が高い文書には「電子署名」を利用して、より強固な証跡を残し、それ以外の多くの文書には「電子サイン」を利用するといった使い分けができるので、コスト削減につながります。
電子契約で契約書作成にかかる手間・コストを削減
電子契約にすると押印や郵送、契約管理台帳へのデータ入力の必要がなく、契約に関わる手間が大幅に削減されます。さらに、オンライン上での契約締結は印紙税法基本通達第44条の「課税文書の作成」に該当しないため、収入印紙も不要です。
電子契約で完結することで、郵送する切手代や紙代、インク代なども不要となり、コストカットにつながります。
過去の契約書もクラウド上で保存してペーパーレス化
紙ベースで契約書類を作成すると、紛失や破損の恐れがあります。また、管理するための物理的なスペースを確保しなくてはなりません。また、電子帳簿保存法の改正でPDFでの保管にも制約が発生します。
freeeサインでは、過去の契約書もPDF化してタイムスタンプ付きで保存ができるので、今まで紙やPDFで保存していた契約書も一緒にクラウド上で管理することができます。クラウド上で管理することで紛失や破損の恐れも解消され、社内間での共有も楽になります。
気になる方は、無料登録でも書類の作成や電子締結ができる「freeeサイン」をぜひお試しください。
よくある質問
契約書に収入印紙を貼る必要はある?
契約書のなかでも印紙税法上の「課税文書」に該当するものは、契約金額に応じて収入印紙を貼り付ける必要があります。
詳しくは記事内「契約書に収入印紙の貼付は必要」で解説しています。
契約書に貼る収入印紙はいくら?
契約書に貼り付ける収入印紙の金額は、契約書の種類や契約金額に応じて異なります。
詳しくは記事内「契約書に貼付する収入印紙の金額」をご覧ください。

