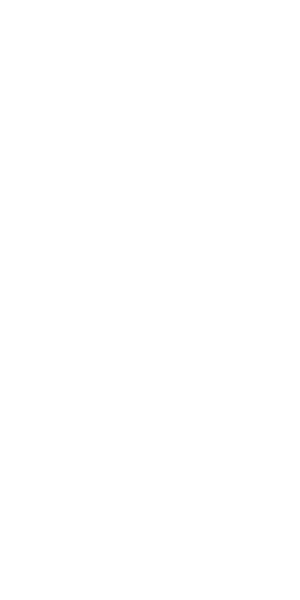社宅とは、企業が福利厚生として一般的な賃料よりも安い賃料で従業員に貸し出す住居のことです。
基本的に社宅は福利厚生費として経費の扱いになりますが、条件を満たさない場合はそのとおりではありません。
本記事では、社宅とは何か種類ごとに説明し、経費にするための条件や節税効果、取り扱いに際しての注意点を解説します。
目次
社宅とは
社宅とは、企業が福利厚生として、一般的な賃料よりも安い賃料で従業員に貸し出す住居のことです。
安い賃料による従業員の経済的な負担減や、勤務地の近くに社宅を構えることにより従業員の通勤の負担減が期待できます。
社宅の種類は、大きく「借り上げ社宅」と「社有社宅」に分けられます。
借り上げ社宅
借り上げ社宅とは、企業が契約した物件を従業員に転貸する社宅です。
企業がマンションやアパートを1棟丸ごと契約して社宅にすることもあれば、フロアだけの契約や数部屋だけの契約といったケースなどさまざまです。
また、従業員が選んだ賃貸物件を企業が契約して借り、借り上げ社宅として利用することもあります。従業員が物件を選ぶ場合、想定以上の経費や従業員間での不公平を生まないためにも、選べる物件に広さや間取りなどの規程を設けるのがおすすめです。
社有社宅
社有社宅とは、企業が所有している物件を社宅にするものです。
企業には物件取得の初期費用の負担がかかりますが、取得後は第三者のオーナーがいないため、スムーズに手続きが進められます。
住宅手当との違い
従業員の住宅に対する福利厚生には「住宅手当」もあります。
一般的に住宅手当とは、従業員の家賃補助のために支給されるものです。社宅は従業員が住む物件を支給するのに対して、住宅手当は金銭を支給する点で異なります。
それぞれの企業からみたメリットとデメリットは次のとおりです。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 社宅 | ・経費計上して節税になる | ・社有社宅は維持、修繕といった管理コストがかかる ・借り上げ社宅は、従業員がするべき賃貸契約を代わりに行う手間がかかる |
| 住宅手当 | ・金銭を支給するだけでよいため、手間がかからない | ・従業員の給与扱いとなるため、所得税や住民税が課税される |
社宅を経費にするための条件
社宅を経費にするためには、従業員から一定額の家賃を徴収しなくてはなりません。徴収する金額が一定額に満たない場合、給与とみなされます。
具体的に「一定額」とは、賃貸料相当額の50%以上の金額を指し、賃貸料相当額は次の3つを合計したものです。
- (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)× 0.2%
- 12円 ×(その建物の総床面積(㎡)/3.3(㎡))
- (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)× 0.22%
出典:国税庁「No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」
社宅を経費にした際の節税効果
社宅を経費にすると得られる節税効果について、3つのケースを紹介します。
賃貸料相当額が損金になる
社宅を経費にするための条件である「賃貸料相当額の50%以上」の金額を従業員から受け取っていれば、賃料相当額は給与扱いにならず税務上の損金扱いです。
この場合の仕訳としては、従業員から徴収した家賃を「家賃収入」として仕訳し、差額を「福利厚生費」として処理します。
もし無料で貸し出している場合は賃貸料相当額、賃貸料相当額の50%未満で賃料を受け取っている場合は差額を、それぞれ課税対象となる給与として処理しなくてはいけません。
購入した建物は減価償却費で計上できる
企業が社宅用の建物を購入した場合は、減価償却費として毎年の費用に計上できます。
社長が個人で物件を購入しても減価償却費として計上することはできず、法人だからこその節税効果だといえます。
【関連記事】
減価償却とは?償却できる資産や計算方法、耐用年数をわかりやすく解説
借入金利子が損金になる
法人が社宅用の物件を購入した際、購入資金を借入れで調達していると、利子も損金になります。
物件取得には初期費用が大きな金額となるケースもあり、利子を損金にできるのは大きな節税効果になるでしょう。
社宅を経費にする際の注意点
社宅を経費にする際の注意点を4つ紹介します。
法人名義で契約する
借り上げ社宅の費用を経費計上する場合は、物件を法人名義で契約しなくてはいけません。たとえ従業員が選んだ物件を社宅とする場合でも、契約は法人名義であることが必要です。
従業員が個人の名義で契約して家賃の補助を出すのは住宅手当にあたるため、社宅の節税効果は得られません。
社内規程を作成する
社宅に選べる物件の要件や、入退去の手続きなどに関する社内規程を作成するのがおすすめです。
たとえば、退職後の退去までの日数などを決めておき、従業員に周知しておくことで退職後も社宅に住んでいる従業員がいるといったトラブルを防げます。
また、社宅に選べる物件の要件を決めておけば、不要に広く賃料の高い部屋を従業員が借りるといったケースもなくなります。
光熱費や駐車場代は経費とならない
基本的に光熱費や駐車場代は従業員の負担となる点に注意が必要です。
規程を決めて企業が光熱費や駐車場代を負担すると、従業員への給与とみなされて課税対象になります。
これらの負担は節税にはならないため、企業側のメリットはありません。ただし、従業員の負担軽減の観点から、光熱費などを負担する企業もあります。
役員の社宅は賃貸料相当額が異なるケースがある
役員の社宅で豪華な社宅だとされる場合は、通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額です。豪華な社宅とは、床面積が240㎡を超えるもののうち、取得価額や支払賃貸料の額、内外装の状況などの要素で判定されます。
また、たとえ240㎡以下でもプールのような役員個人の嗜好を著しく反映した設備等を有するものは豪華な社宅とみなされます。
一方で、小規模住宅の場合も計算が異なります。
小規模住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132㎡以下、法定耐用年数が30年を超える場合には床面積が99㎡以下の住宅のことです。
小規模な住宅の賃貸料相当額は次の3つの合計から算定されます。
- (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)× 0.2%
- 12円 ×(その建物の総床面積(㎡)/(㎡))
- (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)× 0.22%
出典:国税庁「No.2600 役員に社宅などを貸したとき」
まとめ
社宅制度を活用すれば、企業・従業員の双方が節税などのメリットを得ることができます。企業側は節税効果を得られ、従業員側は家賃負担が軽減されるのが主なメリットです。
社宅制度を活用するには、契約方法や従業員から徴収する金額など注意すべき点もあります。規則に則った処理をしないと想定していた節税効果が得られなくなる可能性もあるため、正しく理解して社宅制度を活用しましょう。
よくある質問
社宅は経費になりますか?
条件を満たした場合、社宅は経費の扱いになります。
詳しくは記事内「社宅を経費にするための条件」をご覧ください。
社宅を経費にした際の節税効果は何ですか?
社宅を経費にした場合、次のような節税効果が見込めます。
- 賃貸料相当額が損金になる
- 購入した建物は減価償却費で計上できる
- 借入金利子が損金になる
詳しくは記事内「社宅を経費にした際の節税効果」をご覧ください。