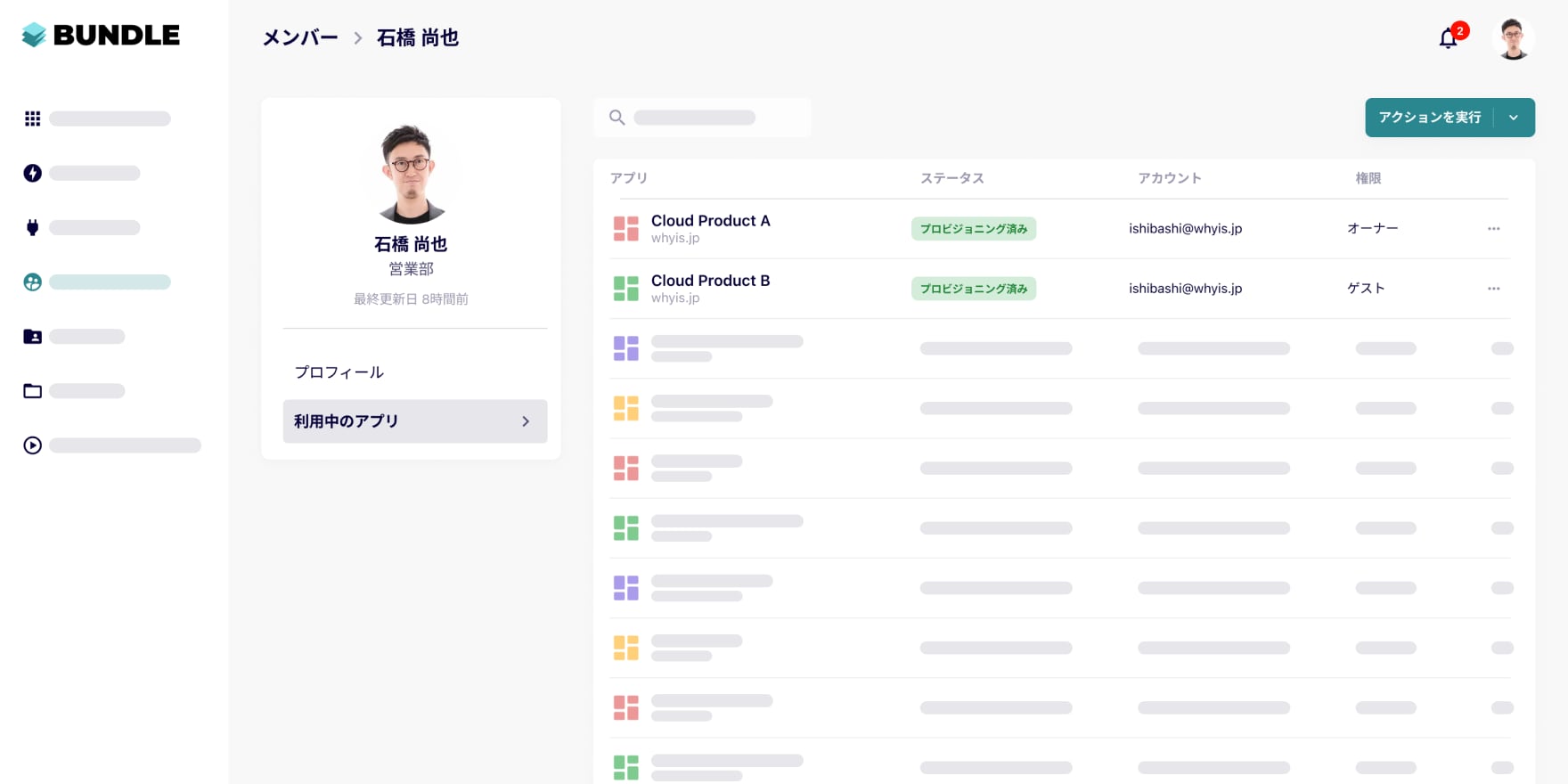プライバシーマーク(Pマーク)とは?認証を受けるメリットや取得までの流れを解説
最終更新日:2025年1月22日

プライバシーマーク(Pマーク)は、企業が個人情報を適切なルールに基づいて管理、利用していることを証明するマークです。プライバシーマークは第三者から認可されて初めて取得できるため、信頼性が高くさまざまなメリットをもたらします。
本記事では、プライバシーマークの基礎知識や取得して得られるメリット、取得するための方法などを詳しく解説します。
目次
- プライバシーマーク(Pマーク)とは
- プライバシーマーク制度が創設された背景
- プライバシーマークの付与対象
- プライバシーマーク認証を受けるメリット
- プライバシーマークを取得するまでの期間
- プライバシーマークを取得するのにかかる費用
- プライバシーマーク取得までの流れ
- プライバシーマークを効率良く取得するためのポイント
- よくある質問
- まとめ
プライバシーマーク(Pマーク)とは
プライバシーマーク(Pマーク)とは、日本産業規格であるJIS Q 15001の要件を満たしたマネジメントシステムを構築・運用していることが、第三者によって認められた証を意味します。
JIS Q 15001は個人情報保護を目的として、さまざまな組織が個人情報を適切に管理するのに求められるマネジメントシステムに関する項目を定めた規格です。
プライバシーマークは、日本産業標準調査会が制定した個人情報保護の基準を守っている状態であるときに与えられるため、個人情報を適切に管理していることのお墨付きを得たといえます。
プライバシーマークを取得している事業者は、自社が適切に個人情報を取り扱うことを消費者や取引先に伝える手段として活用しており、個人情報の保護と管理に取り組む姿勢を示せます。
プライバシーマークが適用される情報は事業に使用している個人情報で、適用範囲はすべての従業員です。
プライバシーマークと情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の違い
プライバシーマークと同様に、情報管理に関する認証を指すものとして情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)というものがあります。しかし、これらは対象範囲や保護対象、日本の規格か国際規格かどうかなどで違いがあります。
具体的な違いは、以下の表のとおりです。
| プライバシーマーク (Pマーク) | 情報セキュリティマネジメントシステム (ISMS) | |
|---|---|---|
| 規格 | 日本産業規格(JIS Q 15001) | 国際標準規格(ISO 27001) |
| 保護対象 | 個人情報 | 取得範囲における情報資産 (個人情報を含む) |
| 取得範囲 | 事業者全体(全従業員) | 部門やプロジェクト単位での取得が可能 |
| 更新タイミング | 2年ごと | 3年ごとに更新審査 更新審査の年を除く1年ごとに維持審査 |
プライバシー��マーク制度が創設された背景
プライバシーマーク制度誕生の背景は、個人情報の保護が重要視される時代に遡ります。
1990年代以降、インターネットをはじめとするネットワーク技術や情報処理技術が急速に進展した結果、企業や組織による大量の個人情報の収集・管理が可能になりました。この状況を受け、個人情報の不適切な利用や漏洩を防ぐための対策が強く求められるようになります。
それまでも、国の行政機関では1988年に「行政機関が保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」が制定され、行政レベルでの個人情報保護が進められていました。
しかし、民間企業においては具体的な指針がなく、早期かつ実効性のある個人情報保護の取り組みが必要とされていました。
このような背景の中、通商産業省(現経済産業省)の指導を受け、財団法人日本情報処理開発協会(現一般財団法人日本情報経済社会推進協会)が中心となり、1998年4月1日にプライバシーマーク制度が創設・運用開始されました。
この制度は、企業が個人情報を適切に保護・管理していることを第三者が認証する仕組みとして設けられ、現在では国内企業の信頼性向上や競争力強化の一翼を担っています。
プライバシーマークの付与対象
プライバシーマークの付与対象となるのは、活動拠点が日本国内にある事業者です。法人単位での付与となるため、個人単位での取得はできません。
プライバシーマークを取得する事業者は最低限以下の条件を満たし、事業活動における個人情報保護を推進していることが求められます。
プライバシーマークを取得する事業者が満たすべき最低限の条件
JIS Q 15001に基づいた「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針」に則り、個人情報マネジメントシステム(PMS)を定めていること
PMSに基づいた個人情報管理の体制が構築されており、個人情報を適切に扱っていること
プライバシーマーク付与に関する規約(PMK500)に定める欠格事項に該当しない事業者であること
従業員が2名以上であること
上記のとおり、プライバシーマークの付与対象は、個人情報保護に真摯に取り組んでいる法人に限られます。その結果、プライバシーマークを取得した企業が個人情報を安全に管理していることを対外的に証明できるのです。
プライバシーマーク付与の例外
通常、プライバシーマークは法人単位で付与されますが、医療法人や学校法人においては例外的な認定が認められるケースがあります。具体的には、次の条件を満たす場合に例外措置が適用されます。
医療法人等の場合
広域に活動している医療法人が以下の条件を全て満たしている場合、病院組織単位での認定が可能です。
医療法人等がプライバシーマーク付与を認定される条件
医療法人等を構成している病院組織であること
当該病院組織の運営の権限を与えられた病院長がいること
それらの病院組織は地域的に分散していること
これにより、大規模な医療法人が個別の病院単位でプライバシーマークを取得しやすくなっています。
学校法人等の場合
学校法人が以下の条件を満たす場合は、学校単位での認定が認められます。
学校法人等がプライバシーマーク付与を認定される条件
学校法人等を構成している学校であること
当該学校の運営の権限を与えられた学校長(または学長)がいること
学校は学校種別(小・中・高・大)が異なり個人情報の取り扱いにおいて独立的に運営されていること
この例外措置によって、複数の施設や学校を持つ法人が組織ごとに認定を受けられます。
プライバシーマーク認証を受けるメリット
プライバシーマーク認証を受けると、対外的にも社内的にもメリットが得られます。それぞれのメリットについて詳しく解説します。
個人情報をしっかり管理していることを外部に伝えられる
プライバシーマークの認証を取得すれば、企業は個人情報を適切に管理している姿勢を対外的に示すことが可能です。消費者にとっては、その企業がどの程度個人情報保護に取り組んでいるかを判断する基準のひとつになります。とくに、個人情報を提供する際に不安を感じやすい消費者に対して安心感を与えるための重要な要素になります。
企業間取引でも、プライバシーマークの有無は信頼性を判断するポイントになるこ�とが少なくありません。大手企業との取引では、相手先の情報管理体制を厳しくチェックするアセスメントが実施されることもあります。プライバシーマークを持っていれば、これらの審査をクリアしやすくなるといった効果があります。
さらに、委託先を選定する際にもプライバシーマークは判断材料になるでしょう。個人情報を扱う業務を外部に委託する場合は、適切に管理されているかは非常に重要です。プライバシーマークを取得している企業であれば、日頃から個人情報保護に関する教育や管理が徹底されていると判断され、安心して業務を任せられます。
社内の個人情報管理に関する事故未然防止につながる
プライバシーマークを取得する過程では、企業全体で個人情報保護に関する取り組みが進むため、事故の発生リスクを未然に防ぐことにもつながります。具体的には、適切な管理体制を構築し、社員一人ひとりの意識を高められます。個人情報を守る仕組みと文化が社内に根付けば、日常業務におけるミスや漏洩リスクを最小限にしていけます。
万が一事故が発生した場合でも、プライバシーマーク取得の過程で確立した管理体制によって迅速に対応できます。適切な記録や監査手順が整備されているため、問題発生時に速やかに原因を特定し、以降の改善策も講じられます。
このように、プライバシーマークを取得することで外部への信頼性を高めるだけでなく、内部の運用効率や安全性も向上します。
信頼性が高まりビジネスチャンスが広がる可能性がある
プライバシーマークを取得すると、第三者による客観的な評価を受けた証明として企業の信頼性が向上します。とくに取引先が情報管理体制を重視する場合において、プライバシーマークがあることは大きなアドバンテージです。
企業のなかには、プライバシーマークを取得していることを取引条件としているケースもあり、プライバシーマークを取得することによって商談の幅も広がります。
また、民間だけでなく公共案件で有利になるケースも少なくありません。官庁や地方自治体が実施する一般競争入札において、プライバシーマークの保有が条件になることもあります。認証を取得している企業は入札に参加できる機会が増え、ビジネスの可能性を広げられるのです。
さらに認証を受けた企業はブランドイメージが向上し、消費者や取引先からの信頼が厚くなります。新規案件の獲得やリピーターの増加といった形で、事業の成長によい影響を与える効果が期待できます。
プライバシーマークを取得するまでの期間
プライバシーマーク取得のためには、準備期間が必要です。企業はマネジメントシステムを構築し、申請前に3ヶ月程度の運用を行うことが求められます。その後問題がなければ、申請・審査・審査通過を経て平均7〜8ヶ月程度で取得可能です。準備の進行状況やシステム運用の成熟度によっては、この期間が前後することがあります。
例外的なケースとして、親会社が運用していた個人情報保護マネジメントシステムを子会社が引き継ぐ場合、1ヶ月程度の短期間で新規取得の申請が認められることがあります。ただし、この場合でも審査には親会社での運用記録が必要です。
取得期間をスムーズに進めるには、初期段階での準備を効率化し、申請書類の整備や運用の計画を適切に実施することがポイントです。また専門コンサルタントを活用することで、プロセス全体を円滑に進められます。
プライバシーマークを取得するのにかかる費用
プライバシーマークの取得にはさまざまな費用がかかり、事業規模によって審査にかかるコストが異なります。かかる費用としては、主に以下の3つのものがあります。
- 審査にかかる費用
- プライバシーマーク取得のコンサルティング依頼費用
- その他の費用
審査にかかる費用
プライバシーマーク取得の審査にかかる費用は、事業規模によってあらかじめ決まっています。事業規模は以下の基準で小規模〜大規模まで分類されます。
| 業種分類 | 資本金の額または出資の総額 従業員数 | 小規模 | 中規模 | 大規模 |
|---|---|---|---|---|
| 製造業・ その他 | 資本金の額または出資の総額 従業員数 | 2〜20人 | 3億円以下 または 21〜300人 | 3億円超 かつ 301人〜 |
| 卸売業 | 資本金の額または出資の総額 従業員数 | 2〜5人 | 1億円以下 または 6〜50人 | 1億円超 かつ 101人〜 |
| 小売業 | 資本金の額または出資の総額 従業員数 | 2〜5人 | 5千万円以下 または 6〜50人 | 5千万円超 かつ 51人〜 |
| サービス業 | 資本金の額または出資の総額 従業員数 | 2〜5人 | 5千万円以下 または 6〜100人 | 5千万円超 かつ 101人〜 |
事業規模ごとの審査にかかる費用は以下のとおりです。
単位:円(税込)
| 新規のとき | 更新のとき | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業者規模 | ||||||
| 種別 | 小規模 | 中規模 | 大規模 | 小規模 | 中規模 | 大規模 |
| 申請料 | 52,382 | 52,382 | 52,382 | 52,382 | 52,382 | 52,382 |
| 審査料 | 209,524 | 471,429 | 995,238 | 125,714 | 314,286 | 680,952 |
| 付与登録料 | 52,382 | 104,762 | 209,524 | 52,382 | 104,762 | 209,524 |
| 合計 | 314,288 | 628,573 | 1,257,144 | 230,478 | 471,430 | 942,858 |
プライバシーマーク取得のコンサルティング依頼費用
プライバシーマーク取得専門のコンサルタントにプライバシーマーク取得のコンサルを依頼した場合は、審査とは別に費用が必要です。コンサルタントに依頼するメリットとしては、自社のみで取得するのと比べて作業負担を圧倒的に軽減できることが挙げられます。
希望すれば、運用前の段階から依頼でき、会社の状況に合わせて取得までサポートをしてくれるのが一般的です。コンサルの費用目安としては、大体30〜100万円が相場となります。
その他の費用
プライバシーマークの取得には、審査費用やコンサルティング費用以外にもさまざまなコストが発生します。たとえば、以下の費用が挙げられます。
プライバシーマーク取得にかかるその他の費用例
社内ルールの変更に伴う教育費用
システムの更新費用
人件費
備品代
これらの費用は事前に見積もりを立て、計画的に予算を配分することが大切です。とくに中小企業では、これらの費用が全体の取得コストに大きく影響してきます。
プライバシーマーク取得までの流れ
プライバシーマーク取得は、個人情報保護マネジメントシステムの整備からスタートして、プライバシーマーク付与適格性審査を受ける流れとなります。
それぞれのステップについて詳しく解説します。
1. 個人情報保護マネジメントシステムを整備する
プライバシーマークを取得するには「プライバシ�ーマークの付与対象」で述べたとおり、PMS(個人情報保護マネジメントシステム)の構築が必要です。PMSは、個人情報の機密性・完全性・可用性を保つ仕組みで、継続的な改善を前提とした体制を整えることが求められます。
PMSは、計画(Plan)・実施(Do)・点検と評価(Check)・改善(Act)というPDCAサイクルを基礎にしています。このサイクルを運用することで、個人情報管理を組織的に行うことが可能です。
最初に個人情報保護方針を定め、経営層を含めた組織全体の体制を整備します。その後、個人情報の棚卸やリスクアセスメントを実施し、必要な対策を策定してルールを文書化します。
PMSは1年間の運用を想定しており、教育・内部監査・点検などのプロセスを回しながら、ルールが日常業務で守られているかの確認が必要です。この運用結果や記録が、審査を通過するための重要な証拠となります。
審査前には、運用の記録を基にPMSが適切に機能していることを証明できるよう準備を整えることが重要です。
2. プライバシーマーク付与適格性審査
プライバシーマークを取得するための最終ステップが、付与適格性審査です。この審査では、以下のことが確認されます。
付与適格性審査で確認されること
構築したPMSがJIS Q 15001に準拠しているか
実際の運用実績が伴っているか
まずは申請書類を作成し、必要書類をオンラインまたは郵送で提出します。オンラインと郵送では必要書類が異なるため、注意が必要です。
書類審査が通過すると、現地審査が行われます。この段階では審査員が職場を訪れ、定められたルールが現場で守られているか、記録が適切に残されているかを直接確認します
現地審査で不適合と判断されるケースは、ルールの未遵守やJIS規格への非準拠が主な原因です。不適合が指摘された場合は、審査員から詳細な説明を受け、改善策を講じたうえで再審査に備えましょう。
付与審査を通過するとプライバシーマークが付与され、2年間の有効期間が与えられます。その後は更新申請を行い、2年ごとに審査を受ける必要があります。更新する場合は、有効期間の終了する8ヶ月前から4ヶ月前までの間に申請が必要です。
プライバシーマークを効率良く取得するためのポイント
プライバシーマークを取得するためには、組織体制を入念に整えるなどの準備が欠かせません。効率よくプライバシーマークを取得するために押さえておきたいポイントを紹介します。
社内の体制を整える
プライバシーマークを取得するには、JIS Q 15001に基づいた組織体制の構築が必要です。個人情報保護管理者や個人情報保護監査責任者など、PMSの運用に必要な担当者を適切に割り当てることが求められます。
そのほかにも、以下の担当者を立てる必要があります。
PMSの運用担当者以外で立てる必要のある担当者例
教育担当者
問い合わせ担当者
開示請求などの担当者
苦情・相談担当者
監査員
各部門、階層の責任者・担当者など
また、組織体制の整備に合わせて社内ルールやシステムの見直しを行い、PMSに従った運用をスムーズに進められる環境を整備する必要があります。その結果、審査時の不適合を防ぐだけでなく、PMSを運用しやすい状態を維持できるのです。
コンサルタントに依頼する
プライバシーマーク取得において、すべてを自社で対応するのは大きな負担となる場合があります。とくに以下のような場合には、計画の頓挫やスケジュールの遅延が発生しかねません。
プライバシーマーク取得で困難が起こる可能性のあるケース
担当者が本業とプライバシーマーク取得業務を兼務している場合
担当者のPMSに関する知識が不足している場合
コンサルタントを活用することで、経験と知識に基づいた効率的な取得サポートが受けられます。具体的には必要な文書や記録の作成方法、スケジュール管理、審査指摘事項への対応策などを専門的にアドバイスしてもらえるため、作業時間��と負担が大幅に軽減されます。
さらに現地審査後のフォローも依頼でき、取得までの道のりを確実に進められることは大きなメリットです。
よくある質問
プライバシーマーク(Pマーク)とは?
プライバシーマーク(Pマーク)は、JIS Q 15001に基づいた個人情報保護の取り組みを第三者が認証した証です。
詳しくは記事内「プライバシーマーク(Pマーク)とは」で解説しています。
プライバシーマーク取得の流れは?
プライバシーマーク取得には、個人情報マネジメントシステム(PMS)の整備やプライバシーマーク付与適格性審査を受ける必要があります。
詳しくは記事内の「プライバシーマーク取得までの流れ」をご覧ください。
まとめ
プライバシーマーク(Pマーク)は、企業が個人情報保護に取り組んでいる証であり、取引先や消費者からの信頼を得るために重要なマークです。プライバシーマークを取得するには、PMSの整備や社内体制の構築など入念な準備が求められますが、必要に応じてコンサルタントを活用すれば、効率的かつ確実に取得を目指せます。
プライバシーマークを取得し、競争力の向上と信頼性の向上を図りましょう。
SaaS管理の成功事例集
増え続けるSaaS管理の参考に!Bundle by freeeを導入いただいた企業様の成功事例をご紹介。